|
時間というものは残酷だ。どんなに願ったって巻き戻ることも進むこともない。一定の周期を常に保ち続ける。それこそシステムみてえに、だ。もしかしたら、周りに中学生やら高校生やらが多いから余計にそう感じるのかもしれない。(まあ室長とかもいるけどそれは別。)それこそ俺もあいつらの年の頃は軽い気持ちでこの言葉を口にしていたけど、今じゃまったく笑えねえ。数年前の自分を殴りつけてやりたいくらいだ。俺なんかの力じゃダメージにもならないかもしれないけど。 「なに、まーだやってんの?」 「んー?当真お前訓練がどうとか言ってなかったか」 「それ何つったっけ、デバイス?」 「デバッグな」 「そうそう。朝からやってんだろ?」 「今何時だ?」 「八時」 危うく飲んでいた水をパソコンに吹きかけるところだった。パソコンの時計、携帯の待ち受け。最後に当真に顔を向けると当真は「ひでえ顔」と俺の顔を指差しながら呑気に笑う。「お前訓練は」と慌てて言う俺に当真はけろっとした顔でもうとっくに終わったと口角を上げた。 「いやあ大変だねえ隊長ってのも」 「殺される……」 オペレーターから死刑宣告のように告げられた「八時半まで」という声が頭で反響し続ける。一日が七十二時間ならよかったのにと頭を抱え込んだ俺の肩を当真がぽんぽんと叩く。「時間っつーのは残酷だな、隊長」当真はそう言い残して片手をひらひら揺らしながら扉の向こうへと消えていった。十八のガキが言う「時間は残酷」は俺が使うソレとは随分違うな。ディスプレイに顔を向けると相も変わらず歪な文字列が表示されたまま。……今の時間に俺の思い通りに直ってくれてりゃいいんだけどなあ。 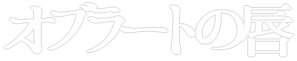
「あー……」 予定の時間から三時間。ようやく解放された。完成した報告だけ送って、反るように椅子にもたれる。働き盛りといえば働き盛りだが、三十手前の身体にはなかなか負担が大きい。それこそ、そのうち室長みたいなことになっちまいそうだ。何がとは言わねえけど。作業を始める前と比べてかたくなってしまった首と肩を動かしながら席を立つ。明日が休みでよかった。今夜はどっかで食って帰るか……。頭の中で店の候補を挙げながら廊下を歩く。流石のボーダーもこの時間になれば人はいなくなる。隊員がいる時はあんなに賑やかで、まるで学校みたいなのに。まあ隊員のほとんどが学校に通ってるやつだからそうなっても不思議でも何でもないけど。扉を開けるなり雨の匂いが肺一杯に入り込んできた。 「まだ止んでなかったか」 呟いてから今朝慌ててコンビニで買ったビニール傘を開く。バタバタと雨が落ちて来る衝撃はなかなか強くて、ズボンの裾がみるみる濡れていくのを感じた。明日も雨だろうし、家に居るのがいいか。まあ、晴れてても家に居るんだけど。住宅街に入ってしばらく歩いた後、店の軒下で人が空の機嫌を伺っているのが見えた。その見覚えがあるシルエットに思わず目を細めてもう一度確認する。いや、あの仕草は間違いない。 「」 ある程度近くなってから声をかけるとがぱっと俺に顔を向ける。冬島さん、と雨音の中で静かな声が響いた。シャワーを浴びたように湿った髪。水がしみ込んで色が濃くなった洋服。細身のズボンは完全に肌に張り付いている。両腕を使って胸の前でしっかり抱きしめられているバッグはかろうじてあまり濡れていないようだった。それでも、傘を持っていないことは一目瞭然だった。 「何してんだこの時間に……もしかして残ってたのか?」 「はい……冬島さんもですか?」 「ああ。残ってたの、もしかして例の補強開発か?」 「……鬼怒田室長から聞いたんですか?」 「まあな」 残ってやりたい気持ちはわかるけど遅くに帰るならタクシーでも使ったほうがいいんじゃねえの。つけ加えるとは困ったように笑って「はい」と答えた。出会った時とは比べ物にならない程大人びた雰囲気に反して、笑った顔は昔から幼いまま。少し迷ってから「傘、入ってくか?」と聞いてみる。は目を丸くして瞬きを数回繰り返してからしばらくここで止むのを待つからと俺の質問を優しく返した。別に気にすんなと言おうとした時、何となくの立ち方が普段と違うことに気付く。……なんか、やけに右脚に重心がかかってる、っつーか……。あまりにも完成されていて初めて会った時に思わず見惚れたくらいだ。こいつの立ち姿は目に焼き付いている。 「お前、左脚ケガしてんのか?」 「えっ」 力が籠ったのかシンプルなバッグがひしゃげる。は「あの」とか「えっと」とか言ながら目線を左足に落としたり道路に投げたり、かと思えば俺に戻したりして。俺が何も言わずにただを見ているからそのうち観念したように「はい」と頷いた。 「本部から走って帰ってる時、後ろから車がきて……クラクションにびっくりした時によろけちゃって」 「あー……捻挫か?」 「多分……」 は小さくため息を吐くと空を見上げながら「まだ止まないかなあ」と呟いた。履いたことないからよくわかんねえけどの履いてる靴は少しヒールがあるから、これで転んだら痛いんじゃないのか。に「足、見せてみろ」と言ってみるとはさっきよりも目を丸くした。 「言っとくけど変な意味じゃねえからな。捻挫より酷かったらまずいだろ」 「そ、そうですけど……」 「あれだ、嫌だったら別にいい」 慌てて言うとは俺をしばらく見つめて、それから「お願いします」と小さく声を出した。はバッグを抱えたまま身を屈める。片方の手がズボンの裾を捲っていくと靴下と素肌が顔を出した。傘を立て掛けて、俺とは段差に座り込む。恐る恐るのびてきた小さな足は俺の膝の上で大人しく俺の手を待っている。 「靴下脱がしていいか」 「はい」 急に緊張してきた。柔らかい生地の靴下に手をかける。色白の肌がどんどん現れて、最終的にの足が外の空気に晒された。深く考えずに言ったけどよくよく考えたら女の肌に直接触ったのなんか初めてだ。男のものとは全然違う。ごく、と喉が鳴った音がもしかしたら聞こえたかもしれない。それなりに仲がいいものの、今のは流石に引かれたかもしれない。様子を見ようと顔を上げる。すると少し顔が赤くなったが目に入って、ばっと顔を元に戻した。……まずい。まずいんじゃねえのか、これ。何がまずいって、俺が。 「……冬島さん、どうですか……?」 「あ、ああ……やっぱ捻挫だな。明日休んどけよ」 足首を気遣ってゆっくりと靴下を履かせてやるとがくすくす笑った。「冬島さん、くすぐったい」「文句言うなよ、俺だって慣れてねえんだ」「わかってます」が開発に入ってきたのは三年前。その時はまだ学生だったが今はもう世間的には社会人になる。昔は女ってだけでどう接していいかわからなかったけど、仲が良くなった今じゃ別の意味でどう接していいかわからない。……まあ、知り合った当時から失敗してるとこばっか見られてたから今更かっこつけらんねえけど。うるさくなった心臓の音と、乾いていく口内。客観的に考えても二九の男としては格好が悪いとしか言えない。 「冬島さん、わたしタクシー呼びます」 「……はあ?」 「どうせ夕ご飯食べずに作業してたんだろうし、お腹すいてるでしょう。早く帰ってください」 「そうは言ってもよ……せめてタクシー来るまで、」 「大丈夫です。わたし、もう大人ですから」 でも、と続けようとした俺の言葉を遮っては「大丈夫だ」と言い続ける。昔から女に対して強く発言できない性格が呪って、結局俺は傘を開いた。振り向いてもは「いいから」と強い視線を送ってくるだけ。とうとう角を曲がってが見えなくなった。……足、見るっつったのそんなにまずかったか。そんなことを考え始めた時、一台の車が俺のすぐ横を通って行った。水飛沫が飛び散って、膝の下が濡れる。雨は依然降り続ける。ばたばたと騒がしい音が降り続ける。 「……」 何だったのかわからない。何がきっかけだったのかもわからないけど、勝手に身体が今来た道を戻っていた。雨に濡れた身体と、声をかけられた時の瞳。「大人ですから」と笑った時の表情。全部がフラッシュバックみたいに再生される。角を曲がる。街頭の光に照らされて、軒下には段差に座り込んでいた。バッグは相変わらずきつく抱きしめられて身体を曲げている。ばしゃばしゃと音を立てても雨音に消されてにはわからなかったようだ。近付いた頃にようやくは顔を上げる。「どうして戻ってきたんですか」とは言われなかったけど、表情がその言葉を発していた。 「」 「はい」 「お前の家、レンタルショップ近くのマンションのまま変わってねえよな」 「え?はい、そうですけど……」 「わかった」 に背を向けて屈む。顔を後ろに向けるとは心底不思議そうな顔で「何してるんですか」と口にした。帰んぞ。一言だけ言うとは数回瞬きを繰り返して、それからやっと意味を理解したらしい。明らかに戸惑っているを見つめていると、は観念したように両腕の力を少し抜いた。 「あの、冬島さん」 「なんだよ」 「……えっと、わかりましたから、あっち向いててもらえませんか」 「は?」 「あの……雨で、ブラウス濡れちゃって……」 今度は俺がの言葉をすぐに理解できなかった。数秒経って、がバッグを必死に胸の前で握りしめてた理由をようやく理解する。気まずい空気を感じながら道路に顔を向けると、影が落とされた。 「冬島さん、本当に大丈夫ですか?わたし重いですよ」 いいから早く乗れと催促すると、「失礼します」と背中にの身体がくっついた。そのまま立ち上がろうとして、重心のかけ方がわからなくて一瞬ぐらついて、でもすぐに持ち直す。 「冬島さん、」 「いいから傘だけ差しといてくれや」 この年になって六歳年下を生身でおぶることになるとは思わなかった。さっき走って道を戻ったこともあって、もう既に体力が限界に近い。トリオン体になれたらまだマシだったか。体力もそうだけど、それよりも背中に直接伝わってくる胸の動きとか、腕にかかってる太腿の感触とか、そっちのほうが限界かもしれない。 「」 「はい」 「お前、タクシーほんとに呼ぶ気あったのか?」 「……」 やっぱりな。こいつの性格考えりゃなんとなくわかる。少し下に視線を落とすと、小さい手が必死に握りしめているバッグとさっき裸足になっていた足が宙に揺れていた。今は雨に濡れていないようだ。それだけでも俺が戻った意味はあったから、まあ、よかった。 「冬島さん、大丈夫ですか?」 「大丈夫じゃねえよ……勘弁してくれ」 「どうして戻ってきてくれたんですか?」 「俺が聞きたいくらいだ」 「意地悪なこと聞いてもいいですか?」 「内容によるな」 「わたしじゃなくても、こうしてましたか?」 聞いてどうすんだよ、それ。笑いたかったのに、疲れが溜まりに溜まって上手く笑えなかった。俺が女に慣れてないの差し引いても、お前といるとどうしていいかわからなかったと思う。どうしても想像になるけど。やっぱり俺が慣れてないのは事実だからどうしようもない。システムみたいにすぐ直ってくれればいいのに。 「お前じゃなかったら、そもそもこんなことできねえだろ」 俺の返事には小さく笑った。「そうですね」傘の中での大人びた声が反響する。お前、初めて会った頃はガキそのものだったのにいつの間にこんなことになったんだよ。三年前からずっと数日に一回は顔を合わせてたはずなのに。 「冬島さん、わたし大人になりたいです」 「もうなってんだろ」 「……ほんとに?」 「それ以上ならないでくれ」 半ば自棄になっていた。は堪えきれなくなったように吹き出す。俺の気も知らないで笑いやがって。どうせまた子どもっぽい顔してんだろ。雨がだんだん弱まってきた頃、もう少しで着くとの声が告げる。あの店からを背負って歩くのに実際どれくらいかかったのか。とんでもない時間が経ったように感じる。何か言わなきゃいけない気がするのに、何から話したらいいのかわからない。俺があと少し若かったら勢いだけでこいつに何か言うことが出来たのか。それでも時間というものは残酷で、俺がどんなに願ったってシステムみたいに直ることはない。 「冬島さん、お礼にはならないかもしれないけど、ご飯食べて行きますか?」 後ろからよくわからないけど女っぽい匂いがする。香水なのかシャンプーの匂いなのかも俺には分からない。、もう少し時間くれや。息を切らしながら言うと、の額がうなじに擦りつけられた。何に対して時間が欲しいと言っていないのに「はい」と言うこの女を、一体誰が子どもっていうんだ。 「もう夜遅いし、あんまり明日に響かないもの食べましょうか」 「すき焼きとかどうだ」 「明日に響かないものって言ったじゃないですか」 「あーわかったわかった」 「……それより冬島さん先にシャワー浴びた方が良さそうですね」 「悪かったな……」 冬島慎次/靴下を脱がせる
|