|
「?」 思いがけない声に重心がぐらりと揺れる。直後、「おっと」という声と一緒に後ろから腕が伸びてきて倒れかけたノートの山を支えた。顔をあげるのと、臼井くんがわたしの顔を覗き込んだのは同時だった。 「ありがとう臼井くん……危なかった……」 「いや、倒れなくてよかった」 臼井くんはそう言うと、驚かせて悪いなと小さく笑った。わたしがぶんぶんと頭を振ると臼井くんは可笑しそうに顔を緩ませて、それから肩にぶら下がっていたバッグをかけ直すと当然のようにわたしが必死に抱えているノートの山を崩し始める。「えっ」と声を出して戸惑うわたしを余所に臼井くんはノートをどんどん奪って行って、最終的にわたしの腕に残ったのは五冊ほど。ほとんど臼井くんの腕に移ってしまった。わたしが持っている時はあんなに重かったのに臼井くんが持っているとまったく重くなさそうに見える。 「大変だろ、手伝うよ」 「でも……これじゃあまりにも差があるっていうか……」 「大丈夫」 そう言ったけど、このままわたしが引き下がるような人間ではないことを臼井くんは知っているようだ。スタスタと教室に向かって遠ざかっていく背中と残された数冊の紙の束を交互に見てから諦めて彼を追いかける。走ってやっと追いついたけど、臼井くんの歩くスピードは変わらない。臼井くんが大股でいつにも増して早く歩いてるから、わたしは小走りの状態だ。どうしよう。このままじゃすぐに教室に着くだろう。みっともない感情が生まれて、結局その感情で全身がいっぱいになってしまった。斜め後ろから「ありがとう臼井くん」と声を出すと臼井くんはちらりとわたしを見てから満足気に口角を上げて、やっといつもと同じ速さで歩き始める。ほっとする反面、また臼井くんの思い通りになってしまったことに複雑な気持ちになる。 「って毎週これやってるのか?」 「うん。クラスの中じゃいつもわたしが一番最初に学校来るから」 「朝来ると前の日に提出した漢文のノートが戻ってきてるから誰がやってるのかと思ってたよ」 「先月からだけどね、最近やっと慣れてきた」 先月の朝に廊下を通りがかった漢文の先生に「っていつもこの時間に来てるのか?そしたら毎週提出のノート、俺の机の上に置いとくから登校したら取りに来てくれ」と頼まれたことを話すと臼井くんは心底気の毒そうな顔をした。 「俺が手伝えたらいいんだけどな」 「臼井くん、今日は朝練ないの?雨の日でも中で練習してたみたいだけど」 「屋内の練習場所が昼まで照明工事だからな、朝練だけなくなった」 「そっか」 「それにしても、よく知ってるんだな」 一瞬何を言われたのかわからなかった。ばっと隣を見上げると臼井くんはいつもの穏やかな顔、穏やかな仕草でわたしの目を覗き込む。しまった、やられた。身体が急に熱くなる。かろうじて「そんなに知らない」という言葉が出たけど、そんなもの臼井くんにとっては何のダメージにもならない。臼井くんは少し目を丸くして「それは残念だ」と白々しい口調でわたしの熱を上げる。 「……でもわたし、臼井くんがサッカー部って知ったの去年の冬だったよ」 「そうなのか?初耳だ」 「三年で同じクラスになるまで喋ったことなかったから」 「去年の冬ってことは知り合った直後か」 「うん。臼井くんって水樹くんとか猪原くんみたいに運動部っぽくないし」 「灰原は?」 「灰原くんも運動部っぽい」 「そうか……俺はがどの部活にも入ってないことはその前から知ってたけど」 臼井くんはどうしてこんなにわたしのペースを乱してくるんだろう。そんなに人をいじめるのが好きなんだろうか。意地になって臼井くんの顔も見なくなって「そうだったんだ」とだけ答える。まだ人もほとんどいない廊下を、臼井くんと二人並んで進んでいく。多分こんなことができるのは後にも先にもこの瞬間だけだろう。臼井くんは毎日朝練があるし、普段そんなに頻繁に話すわけでもない。「おはよう」とか「また明日」とかそういう挨拶と、何か特別な用があるときしか会話はない。臼井くん、いつも女の子に話しかけられてるから。 「教室戻った時って誰か他に登校してるのか?」 「んー……いたりいなかったりかな」 どうかまだ誰もいませんように。心の中で呟いてから教室の扉を開ける。中には誰もいなくて、わたしが登校した時に置いておいたバッグはぽつんと机の上に置いてあるだけだった。嬉しいはずなのに、緊張感も増してしまう。どうしたらいいのかわからない自分もいるみたいだ。わたしが言わなくても臼井くんはノートを本人の机の上に置き始めて、五冊しか持っていなかったわたしはそれを手伝った。その間わたしも臼井くんも何も言わなくて、ただただ外の雨の音だけが教室に響く。 「」 不意に臼井くんの声が鮮明に響く。わたしはノートを置きながら返事をする。今手と足を止めて臼井くんを見るのは危険な予感がしたから。ただでさえ臼井くんに乱されてるのに、もうこれ以上されたら今日一日……一日だけじゃない、しばらくダメになってしまいそうだ。こんなに話せることだって滅多にないんだから。 「もしかして緊張してるのか?」 臼井くんもノートを置く作業は続けているらしい。音でわかる。 「してないよ」 無意味に机の角にノートの角を合わせて時間を稼ぐ。さっきまで誰もいないでと願っていた教室にいち早くクラスメイトが来るように祈り始めてる自分がいて、もう臼井くんに乱されないようにするほうが難しいことにやっと気付いた。 「そうか」 きゅ、と外の廊下を擦る音がした。その音に異様に身体が反応して最後の一冊が大袈裟な音を立てて床に落ちる。慌ててしゃがみ込むと視界に清潔そうな上履きが映り込んだ。臼井くんはわたしのすぐ目の前にしゃがみ込むと「俺はしてる」と小さく呟いてからノートを雑に机に置いてからわたしを見つめる。廊下を擦る音が近づいて来て、そして通り過ぎていく。 「……うそばっかり」 「言うと思うのか?」 「言う」 「心外だな。うそを吐くようなやつだと思われてたのか」 臼井くんの腕が伸びてわたしの手首を掴む。それから見た目からはあまり感じられない、厚みのある胸にわたしの手を押し当てた。シャツの生地の向こうで臼井くんの心臓が動いている。少し早いのは、わたしでも何となくわかった。 「ほら、わかっただろ。うそじゃないって」 今までにないくらいの距離で臼井くんが笑う。朝からの行動一つ一つ、わたしが臼井くんのことを好きなことを知っていて、やっている。それもわかってるのに。 「わたしは、臼井くんといるといつもこうだよ」 臼井くんといる時だけ鼓動が早くなる。目が合えば嬉しかったり恥ずかしかったりする。声を聞いたらドキドキして重心が揺れる。これ以上どうしろっていうの。 「、悪いけど」 わたしの手首を掴んでいる手は思っていたよりもずっと厚い。臼井くんの人差し指がわたしの手の甲を優しく滑る。 「そうなってるのが自分だけだと思ったら大間違いだぞ」 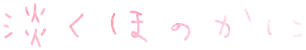
|