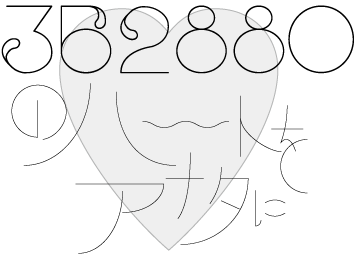ま、を言う前に破裂音がした。何が起こったのかまったく理解できないせいで五感が一瞬だけ全部の機能を停止させる。数秒経ってから火薬の匂いがしてきたけど、痛みがあるわけでも熱いわけでもない。本当に何ともない。瞼を持ち上げると、クラッカーから数本のリボンを垂らしたままにこにこと笑うが目に入った。
「驚きました?」
そりゃあそうだろう。帰っていきなりこんなことされたら。……と、言う気にもなれない。「すごく」とだけ返すとは両手を上げて喜んだ。付き合ってから毎年日付が変わる瞬間に「おめでとう」と言ってくれていたのに今年は何も言わない、まさか忘れたのか……?と思っていたら……そうか、こういうことだったのか……。朝から抱えていた不安のような寂しさのような何とも言えない気持ちが晴れて一日中重かった足取りがやっと軽くなる。今朝俺の顔を見るや否や元気がないんじゃないか?と心配してくれた忍田さんには明日お礼を言わないと。何もかも俺の早とちりで、は俺の誕生日を忘れたりしていなかったと話したら笑われるだろうか。いや、あの人なら良かったなの一言で笑って済ませてくれるだろう。そうであってほしい。玄関に散らばった紙吹雪を見下ろすと、俺の意識を逸らそうとしたのかは慌てて俺の手を引いた。
「あの、片付けるのは後でやりますから」
「え?……ああ、怒ってるわけじゃないぞ」
「……ほんとに?」
「うん。クラッカーなんて久しぶりに見たから新鮮で」
最期にクラッカーを向けられたのはいつだったっけ。確かボーダーで本格的に仕事をする前、最後の東隊に所属していた時だったはずだ。思い返してみるとあの時も作戦室に入った瞬間にクラッカーを鳴らされたんだった。後輩達の悪戯っぽい顔が浮かんで笑みが零れるとが不思議そうに顔を傾げた。何でもないと誤魔化して靴を脱ぐとは握ったままの俺の手に指を絡ませる。左手の薬指に嵌められた指輪が廊下の電気を反射してきらりと光った。
「今日のご飯、春秋さんの好きなもの頑張って作ったんですよ!いっぱいあるけど全部食べてくださいね」
「はは。もちろん」
「ちなみにケーキはホールです!」
「……嘘だろ?」
「ふふ」
うそですよ、とが笑う。一瞬。ほんの一瞬だけ「まさか」と思ってしまった俺は胸を撫でおろす。そんな俺を見ては楽しそうに笑って、その拍子に髪がふわふわと揺れた。少し前まで「ちょっと切ってもらうつもりが春秋さんくらいの長さになっちゃった」と言っていたのに、もう鎖骨が隠れるくらいの長さになっている。いつの間にこんなに伸びていたのだろう。……考えてみればが髪を切ったのは夏頃だった気がしてきた。半年近くも前のこととは思えずにに聞いてみると確かに髪を切ったのは七月だったようで、月日が過ぎるスピードに眩暈がした。日月逾邁とはこのことだろう。そりゃあ俺も三十四歳になるわけだ。この調子じゃあっという間に五十歳になって、そのうち死ぬんだろうか。そんなことを考えての手の甲を親指で撫でると、「くすぐったいからやめてください」と小さく抗議をされた。
「くすぐったいからってだけの理由じゃないだろ」
「う……分かっててやらないでもらえますか、……」
「……」
「ひぇ、っちょ、っと」
バッグを床に落とすと重苦しい音がした。が何か言っているのを無視して、自分よりも一回りも二回りも小さい身体を腕の中に収める。これ以上したら怒るだろうな。でも嫌とは言わないはずだ。はそういう子だ。背中を丸めて柔らかい首筋に噛みつくように歯を立てる。そのまま吸うとまっさらな肌の中で出血が起きた。赤と紫の中間のような色合いの痣が出来上がると、大人しくなりかけていたがまた暴れ始める。
「い、今何しました!?」
「キスマークつけた」
「何してるんですか!わたし明日から仕事、」
「タートルネック着て行くから見えないだろ?」
「っそ、……う、いう話じゃなくて!」
上手く懐柔できるかと思ったけど駄目だった。でも「嫌だったか?」って聞けばそれで終わる。口を開いて言ってみると、俺の予想通りは顔を赤くしたままごにょごにょと言葉を濁していった。本当によく今まで悪い男に騙されてこれずに生きてこれたものだ。まあ俺みたいな悪い男には騙されてしまったけど。でも俺が最初で最後だ。この子は俺が墓まで連れていく。何があっても途中で手を離してはやらない。するすると服の中に手を滑らせるとの身体がびくりと跳ねて俺の身体をぐいぐいと押しのけようとする。
「だ、だめ!だめです!」
「何で?玄関だからか?」
「そうじゃなくて!ご飯作ったんだから食べてください!っそ、それに、お腹空いてるでしょ!?」
「……じゃあ、飯の後だったらいいんだな?」
「ぇ、あ……う……。……お風呂、は……」
「飯の前に入るから。……それとも、飯の後に一緒に入る?」
「っひ!?ちょ、ちょっと!そこで喋らない、で、……っ!」
の耳を唇で食みながら話すとの身体が小さく震える。その反応に免じて腕の力を抜いてやるとはほっと息を吐きながら俺と少しだけ距離を取った。無駄なことするな、それで抵抗したつもりなのかな、なんて考えながら笑って見せるとは首筋を押さえて俺を恨めしそうに睨んだ。
「もう……二、三日は続けないと……」
「セックスを?」
「タートルネックです!」
わざと言ってみるとがムキになって言い返してきた。それが可笑しくて笑うとはさらに頬を膨らませる。どうしてこんなに可愛いんだろうな。同じ反応を別の子がしてもこんなに愛しいとは思わないだろう。年々、のことが可愛くてしょうがなくなってきている。手を伸ばしてもう一度と手をつなぐと、固く結ばれていたの唇がだんだん緩んでいった。その隙を見計らってもう一度、風呂に一緒に入りたいとさっき返事をもらえなかったことを強請ってみる。はしばらく視線をあちらこちらに泳がせて黙っていたけど、そのうち視線だけを上げてこくりと頷いてくれた。ずるいよなあ、本当に。堪らなくなって触れるだけのキスをするとは恥ずかしそうに、でもほんの少しだけ笑った。俺はの手を引いて、やっと玄関から歩き出す。
「なあ、一つだけ頼みがあるんだけど……次からは夜祝う時はそう言ってくれないか?」
「嫌ですよ。サプライズの意味がなくなっちゃうじゃないですか」
「そうなんだけど、心臓に悪いんだよ」
「春秋さんいっつもわたしの心臓に悪いことしてくるんですからたまには我慢してください」
「いつもって言うほどしてないだろ」
「……それ本気で言ってるなら怒りますよ」