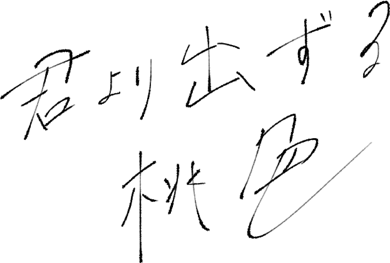そう言って笑う顔に複雑な感情を抱くようになったのはいつだったか、もはや思い出せない。
戯けた表情が好きだった。真剣な眼差しが好きだった。あらゆる仕草のすべてが好きだった。いつまでも見つめていられると思っていた。
それなのに、今となっては。

「」
薄い唇が動いたのと同時に目の前から声が聞こえてきた。硬直しきった身体がうまく動かなくておそるおそる視線だけを上げる。睫毛がぶつかりそうなほど近くにある二つの瞳と目が合って、逃げたい気持ちでいっぱいになる。こんな至近距離で話すなんて、やめてほしい。どこを見たらいいのかわからなくなる。シーツの上で放心していた自分の手が動いて、何かから耐えるように布を握りしめた。
「あの、……こっち見ないでください」
「このタイミングでそれを言うか」
「だって見てくるから」
「を見るしかないだろ」
「じゃあしたらいいじゃないですか」
「何を?」
ばか。中学生みたいなこと言わないでください。
そう言おうとして、中学生はこういうことするのかな、あんまり自信がないな、という思考に行き着いた。黙り込むわたしにそれまで真面目だった目がふっと緩む。
「可愛い」
息ができなくなる。前はもっと純粋に愛せていたように思う。好きだとかかっこいいとかもっといろんな表情が見たいとか。そういうことばかり考えていた。でも、今はどうしたって正反対の気持ちが一緒についてくる。何でだろう。ちゃんと答えを見つけなきゃいけないはずなのに、柔らかいスプーンで頭の中までかき混ぜられて、だんだん思考が痺れてくる。
「余計なこと考えてたろ」
長いキスの後に叱るような口調で言われた。呼吸を整えながらちらりと上を見ると春秋さんの真面目ぶった目と視線がぶつかる。慌てて目を逸らすと、こら、と今度はしっかりと叱る時の言葉で怒られた。
「考えてない」
「嘘つけ」
「春秋さんのことだから、余計なことじゃない」
はあ、と春秋さんはため息を吐いた。「またそんな屁理屈言って」のため息だと思う。たぶん。
「俺のことって言ったって、良くないことだろ」
「何で?」
「キスの仕方がそうだった」
「……そんなに違うんですか?」
「違うよ。……どう違うか教えてやろうか?」
「っい、いらない!」
春秋さんが迫ってくるから必死に身体を押し返すけど全然びくともしない。そのまま春秋さんは楽しそうに笑いながらわたしを覆うように抱き締めてくる。こういう強引なところも、前は好きだったんだっけ。……ううん、前はこういうことをそもそもしてこなかった気がする。……もしかしてわたしが変わったから春秋さんも変わったんだろうか。春秋さんの手に頭を撫でられながら、肩に額を押し当てて目を閉じる。
「また変なこと考えてるだろ」
「……キスしてないのにわかるんですか」
「わかるよ」
ずるい。わたしは春秋さんのことあんまりわからないのに。何なら今は自分のことだってわからないくらいだ。無性に腹が立ってきて首筋を甘噛みすると耳元で珍しい声がした。
「何するんだよ」
「仕返し」
「ええ?」
仕返しも何も俺はまだ何もしてないだろ、という声が聞こえてきそうだけど春秋さんは何も言わない。かわりに、ちゅ、と耳元で可愛らしい音がした。腰にまわっていた腕の力が緩んで春秋さんとの間にぽっかりと空間が生まれると、わたしは真正面から春秋さんの目を見なきゃいけなくなった。まるで慈しむみたいな目を。
「そんなに俺のこと好きになるのが嫌なのか?」
「……嫌ですよ」
「どうして?」
「……」
本当に、どうしてこんなに伝わってしまうのか。わたしってそんなにわかりやすい?黙ってるだけなのにわたしの考えてることがここまで筒抜けになってしまうのが不思議でしょうがない。春秋さんの仕草一つひとつを目の当たりにするたびにこれ以上好きにならないように行動してしまう理由なんて、
「わたしばっかり好きになっちゃう」
頭の中でその答えに辿り着く前に言葉が勝手に踊り出した。でも、その声を自分で聞いてやっと腑に落ちる。
春秋さんは唇を薄く開けたままわたしを見つめた。そして何を思ったか大声で笑い出した。まさかそんな反応をされるとは予想もしてなくて、わたしはぽかんと春秋さんを見つめる。笑い声を聞いているうちに素直に話したことを笑われたのが気に入らなくなってきて、ベッドから下りようとしたら相変わらず可笑しそうにしている春秋さんに引き戻された。バランスを崩して背中からベッドに倒れ込んだわたしを春秋さんは抱き締めて、わたしは変な体勢のまま春秋さんの檻に閉じ込められる羽目になる。
「何で笑うんですか」
ムキになるわたしに、春秋さんは返事もせずにまだ笑っている。それが本当に嬉しそうで、一人だけ怒っていることが馬鹿馬鹿しくなった。ひとしきり笑い尽くしてもまだ春秋さんは笑いが込み上げるようで、たまに小さく笑いながらわたしの肩やら腰やらを撫で回す。可愛いもの見るとだって笑うだろ?と尋ねられたけど、それとこれは話が違う気がして「はい」とも「いいえ」ともとれない返事だけをした。
「可愛いなって思った時にいじめたくなる感覚ってわかるか?」
「え?いえ……わかりません、けど……」
「まぁそうだよな」
「小学生がやることじゃないですか?それ」
「はは、小学生か」
俺がのこと揶揄う時って大体そういう時なんだけど、小学生、小学生か。なるほどな。
春秋さんは何かを納得した様子でわたしをぎゅうぎゅう抱き締めて、わたしはよくわからないままぎゅうぎゅう抱き締められた。春秋さんの身体が大きくて力もあるせいで、身体がほとんど動かせない。動かせたとしてももう離れたいという気持ちは消えたから、されるがままになっていたんだろうけど。
「っひえ、」
突然、鎖骨から耳にかけて柔らかいものが這った。不意打ちもいいところだ。間抜けな声が春秋さんのシャツに滲んでいって、恥ずかしさを掻き消そうと暴れてみたけどやっぱり春秋さんの力には敵わなかった。
「やめてください!」
「小学生だから許してくれよ」
「小学生はこんなことしません!」
「そうなのか?」
「ひっ……そ、そこで喋らないで!」
わたしが春秋さんの声に弱いのをわかっていて耳の近くでわざと変な喋り方をしているらしい。脳みそがじんじんして、身体の力が抜けていく。本当に意地が悪い。もしかして、これも小学生みたいな行動の一つなんだろうか。いや、さっき言ったとおり小学生は絶対こんなことしないけど。
「前はこんなこと思ってなかったんだよ」
「な、なに、」
「可愛すぎていじめたくなるなんて、よくわからなかったんだ」
「は、……?」
「子どもみたいだよなぁ。俺」
たぶん好きになりすぎたんだろうなぁ、なんて耳元で本当に子どもみたいな声で言うものだからわたしは何も言えなくなってしまった。しかもさっきより強い力で抱き締められて、肺が潰されてるのか本格的に息がし辛い。どんな顔してるのか知りたいのに、しっかりと後頭部を固定されているせいで視界には黒い生地しか映っていない。それでもなんとか外に腕を一本だけ出して、不恰好な体勢で春秋さんの頭を撫でてみる。さっきまで笑ってたのに急に黙り込んじゃって。変なの。でも……そっか。この人もそうなることあるんだ。なんだ。わたしだけじゃなかったんだ。今この瞬間も「可愛い」と「可愛くない」がせめぎ合っている。けど、自分がわからない感覚はマシになった。
「春秋さん」
「……うん」
「もしかして、春秋さんってわたしのことすっごく好きなんじゃないですか?」
「何だよ今更……」
ずっと前からそうだよ、と今度は不貞腐れた声が聞こえてくる。その瞬間頬が緩んで、さっき春秋さんが笑ってた理由が何となくわかった。それでもいじめたくなるのはわからないけど。
春秋さんの髪の上に手を滑らせていると、身体に絡んでいた腕から力が抜けてやっと息苦しさが和らいだ。それでも呼吸はまだ浅くて、春秋さんに抱き締められていたせいじゃなかったことにようやく気がつく。久しぶりに見る春秋さんの目は少し幼くなっていて、口元も心なしか寂しそうだった。春秋さんってこんな顔もするんだ。いつもこれくらい可愛げがあればいいのに。でも、そういう春秋さんだったら今ほど好きになってなかったかも。……ううん、そういう春秋さんでも好きになってたと思う。わたしは結局、春秋さんだったら何でもいいみたいだ。
日に焼けた頬を撫でてみると春秋さんは気持ち良さそうに目を閉じた。下がりきっていた口角は、いつの間にかほんの少し上を向いている。
「わたし、春秋さんのことずっと好きなままなのかな」
「そうじゃないと困る」
「でも、そしたら春秋さんから一生離れられなくなりません?」
「それでいいんだよ。離すつもりもないからな」