|
さて、随分遅くなってしまった。 精一杯愛想よく店長に挨拶をして店を出る。タイムカードは三十分前に押したけれど、結局こんな時間に帰ることになってしまった。店長は生気のない顔で私を送り出してくれたが、時間が遅くなったことへの言葉は特に何も無しだ。まあ、仕方がないだろう。社員というのは大層大変らしい。 スマホの電源を入れても時間は巻き戻ったりしてくれない。表示されたのは午前二時の五分前。明日も昼からランク戦があるのを考えると、憂鬱な気持ちになる。そろそろこの店でのアルバイトは見直した方が良いかもしれない。 吐く息は少し濁っている。暖房を切った厨房で片付けをするのは正直きつい季節になってきた。すっかり冷え切ってしまった指先を擦り合わせながら、一番近くの信号まで辿り着いたその時のことだ。 「さん」 左の方から唐突に声が投げられた。それも男の声。びくりと跳ねた肩はそのままに左をそっと振り向くと、そこにいたのはボーダー内でも指折りのイケメンだった。強張った肩からふっと力が抜ける。 「烏丸くん」 先日ランク戦で当たったときも、私たちの隊は玉狛第一に負けてしまった。私はオペレーターだから直接渡り合ったわけではないのだけれど、彼が強かったことは確かである。カッコよくて強い。そりゃあモテるはずだ。 「こんな時間に何してるの?」 「……さんこそ」 少し細められた目が私をじろりと見る。なんだか不機嫌そうに見えるので、素直に私から「バイトだったの」と答えた。「へえ」色の無い返事が返ってくる。「そういう烏丸くんは?」訊ねたら、「俺もバイトすよ」と何でもないように答えられた。 「えっ……こんな時間まで? 大丈夫なの?」 私の記憶違いでなければ烏丸くんはまだ高校生だったはずだ。私とは四つほど年下ということになる。さすがにこんな時間までバイトをやらせてくれる店はないだろう。私の訝る声に烏丸くんは合点が言ったようで、「ああ……」と声を零した。 「知り合いの店なので遅くまで出してもらえるんです」 「そっ……か」 なんだか微妙にはぐらかされた気がする。私が本当に聞いているのはそういうことではない。でも、それを咎めたり心配したりするほどの仲ではない、と思う。正直ちょっとどうかと思ったけれど、口を噤んでおいた。 「さん」 お疲れ、と声をかけて立ち去ろうとしていたけれど、それを言う前にまた名前を呼ばれてしまった。この子の呼ぶ「さん」はやけに丁寧な音で、私を無暗に落ち着かない気持ちにさせる。 「途中まで一緒に帰りましょう」 抗えない響きで持って告げられた言葉は提案ではなく、宣言だ。 互いの家路を照らし合わせて、三つ先の信号まで一緒に歩くことになった。私はこれまでのボーダー隊生活を振り返ってみても、彼とそこまで親しくした記憶がない。だからこんな深夜に彼と草臥れたスニーカーを並べて歩いているのが大変不思議だった。今日はいったい何が起こってるというのだろう。明日友達に冗談めかして報告しよう。 静かな夜の空気が鼻先をどんどん冷やしていく。マフラーを高くしながら隣の高校生をちらと見上げれば、彼もまた寒そうに白い息を吐き出していた。 「烏丸くん、マフラーは?」 師走の今にしては、彼はかなり軽装に見えた。以前本部で見かけた折はマフラーを着けていたような気がするから、余計に今が寒そうに見える。彼は寒々しい首元に今気づいたとでもいうように、首筋に片手を当ててから「忘れました」と簡潔に答えた。 「寒いでしょ。マフラー貸すよ」 私の方がコートも厚そうに見えたし、何より寒々しく見えるのが気になる。そう思って首元のマフラーに手をかけたら、彼は「いや、」と思わぬ速さで断った。同時に私の手に烏丸くんの手が伸びて、マフラーを解こうとする手を止めた。コートの上から私の手首を掴む彼の指先は冷たそうに色を失っている。 「だめです。さんが風邪ひきますよ」 俺は大丈夫なので。 あと信号一つ分。そう重ねて言われると、無理にマフラーを貸すような距離でもないような気がしてくる。それに、掴まれた手が少し苦しい。痛いわけではないのに。 「わ、わかった」 うなずく。彼はほっとしたように手を離して、それから一歩後ろに下がった。スニーカーの靴底が夜の歩道を擦る音。顔を見たいけれど何故か見上げられなくて、うつむいて爪先を見つめる。もうあと数メートルで別れる信号へ到着する。時折通る車の走行音、アスファルトを叩くスニーカーの音、それ以外は何の音もしない。さっきまでそこまで気になる沈黙ではなかったのに、急に静寂が息苦しくなってしまった。 「えっと、それじゃあ……」 信号を渡って、私は左へ曲がらないといけない。このまま別れてしまったら、この烏丸くんと一緒に歩いた静かな家路がすべて幻になってしまうような気がした。でもどうしたらいいのか分からない。 振り仰いだ先、歩行者信号の青の光を肩に浴びながら、烏丸くんは何か言いたげな顔をしていた。吐く息が白く白く濁っている。気温はますます下がっているような気がする。 「あの、」 カチカチ。青信号が点滅する。それが眩しくて、烏丸くんの顔が直視できない。眩しくて、胸がつまる。いや、本当にそれは光のせいなのか。 「さん、って呼んでもいいですか」 初めて烏丸くんの声で聴いた自分の名前は、ずいぶんと心を揺らした。彼の肩越しに眩しく点滅していた青信号が、赤になる。言い終えて、躊躇うように視線を落とした烏丸くんの睫毛の一本一本まで見える気がするのはどうしてだろう。目に映る彼のすべてがやけに鮮明だ。 「……いいよ」 バチッ。 承諾したとほぼ同時に、目を上げた烏丸くんと目が合う。目が合ったその瞬間、火花が散ったような気がした。気がしただけだ。きっと私にしか見えない火花。 烏丸くんはその端正な顔にふんわりと笑みを浮かべて、オレンジ色の外灯の中に立っていた。私と視線を合わせたまま。私の謎の息苦しさなど知らない顔をしている。 「さん」 彼の背中にある横断歩道を運送用のトラックが走り抜けて、一陣の風が烏丸くんの猫っ毛を揺らす。さっき不意に掴まれた手首の感覚がよみがえる。 「やっぱり、家の近くまで送らせてください」 思うに私はこの声に否を言えないようにできているのだ。 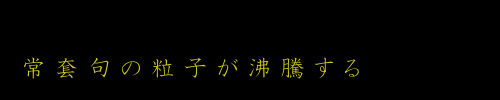
(15/12/10) Thank you!! title:alkalism / pict:HELIUM |