|
の部屋に来るのはこれで何度目だろうか。 先週も来たな、あのときは何を食べたんだっけか。 酔っ払いの脳みそというのはどうもまともな動き方をしてくれない。自分で承知なのに酔っぱらった状態で思考をあれこれめぐらすのをやめられないからどうしようもない。 が熱そうに白菜を咀嚼しているのを見るともなく見ていたら、ふと視線を上げた彼女と目が合った。耐えきれず、口を開く。 「、肉」 「またですか? いい加減野菜も食べてくださいよ」 「しょーがねえだろこっちは仕事帰りなんだよ」 「お仕事ですか」 「仕事だよ」 いまいち腑に落ちない顔をしていやがる。 俺が動こうとしないものだから、彼女がこちらへ身を乗り出してきて俺のとんすいを取って攫っていった。なんだかんだ言いながら、俺の意見を尊重して肉を土鍋から選り出してくれている。 「やっぱり冬は鍋ですよねえ」 のんきな声が、いかにも平和そうな鍋の湯気とともに天井へ立ち上る。 「だから使える日が来るっつったろ」 「先輩最初からわたしの家で食べる気だったでしょ」 「さあな」 「いいですけど、この土鍋結構したんですよ」 「だから材料は全部俺が買ってきてやったじゃねーか」 差し出されたとんすいには肉の他に橙や緑の野菜も並べられていた。俺が文句を言っても、はまったく意に介さない。澄ました顔で自分のとんすいから豆腐を掬い出している。野菜も食べなきゃ健康に悪いですよ、とその顔が語っている。お前いったい俺の何のつもりだよ。そう反論したくても彼女が声に出して何も言わないから俺に反論の隙はない。 仕方なく、とんすいから肉と水菜を一緒に撮んで口に放り込む。別に嫌いじゃないのだ。肉の方を食べたいというだけであって。 鍋の湯気で室内はさらに暖かくなる。熱い鍋を食べているのだから、胃袋からも身体は温まっていく。目の前のも暑くなってきたのだろう、袖をまくりあげたり髪をくくり直したりしている。そうしながらも自分のとんすいに具材を追加するついでに、「何か取りますか?」と俺へ気を遣ってきたりする。俺は白い首元の肌や手首に目を奪われたり、彼女へ「いや……大丈夫だ」と答えたりと忙しい。表には決してそれを出さないけれど。意地でも出さない。 「どうかしました?」 目が合ってしまった。 「……お前さぁ、……」 「何です?」 「いや。やっぱ何でもねえ」 忘れろ、と続けてビールを呷る。目が合ってしまったら口を開かずにはいられないもんだから、言いかけたのがまずかった。は妙に気になるらしく、その後も何度か「何ですかってば」と訊ねてきたが、俺は頑なにはぐらかし続けた。喉をくぐるビールが苦い。やがて諦めた彼女が、ふっとひとつ息をついてテレビを向いた。ようやく俺もビールのペースを落とせる。 テレビの中ではほとんど名前もよく分からないようなタレントたちが騒いでいる。テレビはいい。話題に困らないから。大事なことなんて何一つない会話が出来る。 「先輩、ビールちょっとください」 会話の中に大事なことなんてないもんだから、が急に突拍子もないことを挟んでくるのも仕方のないことだ。こいつはビールが苦手だ。いつも「おいしくない」と言って甘くて度数の低いものばかりを飲む。 「はあ? 何言ってんだ、お前ビール飲めねえだろ」 「いいからください」 否定されると押し通したくなる性格らしい。俺はこの状態のこいつを説得できた試しがないので早々に諦めた。「どうなっても知らねーぞ」と一応形だけの忠告はしておいて、ビールのコップを送り出す。は躊躇わずにそれを手に取って、口を付けた。ちょっとは躊躇ってほしかった。口をつけたものの、少し飲んだだけですぐに彼女はまずそうな顔で口を離した。案の定、だ。 「だから言ったろ」 口直しと言うように自分のグラスに口をつける彼女に、思ったとおりだと告げる。苦手だ苦手だと言ってるのにどうして興味なんか湧いちまったんだろうか。突っ返されたビールは普段と変わらず喉を潤す。 眉を顰めた彼女が、何も言わずに足をぶつけてくる。反撃してるつもりなんだろうが別に反撃になってやしない。「ガキみてぇなことすんな」と腕を伸ばして軽く小突く。彼女のささやかな反撃に見合う程度のささやかな力加減のつもりだ。 恨めし気な彼女の丸い瞳が俺と視線を合わせてくる。そうなると俺はやっぱり耐えられなくて口を開いてしまう。 「土鍋の採算がとれるくらいは鍋やんねーとな」 「ほんとですよ。頼りにしてますからね」 「今年何回やったらいいんだろうな」 「週一くらいじゃないですか?」 「マジで言ってんのかお前」 「マジですよ」 マジで分かってんのか。 のんびりとそう提案する彼女に何の下心も悪気もないのは分かってる。分かってるのは俺の方だ。俺はやれやれとため息を吐くと、「じゃあ毎週金曜日の夜な」と適当に言った。適当に言ったら「はあい」とか間抜けな声で承諾しやがった。何も考えてないのか、考えた上でそう言っているのか。 いや、考えてるんだろう。そうすれば余裕で土鍋の採算が取れるということを。でもまあ、俺もそれでいいかなんて思ってる。毎週末にこうやってこいつの部屋で鍋をつつく。俺は俺でビールを飲んでるし、こいつはこいつで何か好きなもんを飲むだろう。それで適当なテレビを見ながら適当な会話をする。 重要なものなんて何一つないけれど、重要なものが何一つないこの空間が当たり前に存在することが重要なのだ。それを俺はもう分かってる。 「」 「はい」 「お前いい嫁になりそうだな」 目が合っていたわけではないけれど、ぽろりと口から言葉が出てきていた。素直な純度で発された言葉は素直に彼女に届く。の頬がそっと綻ぶ。 「先輩にとってだけ、ですよ」 あんまり可愛いこと言うな。 そう思ったことは今度は口から出てこなかった。代わりに「お前嬉しそうな顔してんなあ」と笑った。そう笑っている自分の顔こそ嬉しそうだということには気づいている。 と分かれて自分の部屋に戻ったのは、23時を少し回った頃だった。 間取りの同じ部屋でもの家とは全く違う。しんとした自室で煙草に火をつける。ふわりと立ち上る匂いは、の部屋には決してないものだ。俺が持ち込まないせいもあるが、彼女と俺の部屋で決定的に異なっていることの一つだ。 煙草を燻らせながら、座椅子に腰を下ろして目を瞑った。嫌に静かに感じる。理由は分かってる。 そう、俺は分かってることの方が多いんだ。 が俺に何を言ってほしいのか、何をどうすれば喜んでくれるかなんて俺が持ってる答えがきっと正解だ。いや、正解であってほしい。俺こそがそれを望んでいる。 なのにどうしてその答え合わせができないのか。俺は、いったい何を恐れているのか。いや、恐れているのか? 何が躊躇わせているのか? それともこの、一見平和そうに見えるぬるま湯の状態に俺が満足しているせいなのか? 案外と酔った頭では思考が苛々する縺れ方しかしない。 煙草の火を衝動のままに揉み消して、俺は座椅子に背を預けたままもう一度深く深く目を瞑った。まぶたの裏でがやたら幸せそうに笑っていた。 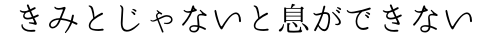 はっと目を開ける。デジタル時計はもうすぐAM2:00に変わろうとしていた。 目を覚ましてもの顔が妙に鮮やかに脳裏に残っていて、俺は一瞬自分がどこにいるのか分からなくなる。 眠る前の苛立ちはどこかへ行っていた。 頭はすっきりとしている。 たぶん、俺が恐れていたものはたくさんある。 本当に答え合わせの先に俺の欲しいものがあるのかどうか確信ができなかったこと、彼女をなにがしかの枠に縛りたくなかったこと、俺が答えを得たことで縛り付けてしまうのではないかということ、今得られているある程度の幸福すら消えてしまうのではないかということ。 恐れていたものが見えてくると、それらは返って俺の背中を押した。 ここで足を止めて、思考を自己満足の為に縺れさせて、そんなことで本当にのことを思いやれているわけがない。 いつになくクリアな気持ちで目覚めた俺は、その勢いのままに電話を掛ける。たぶん寝ているだろう。でも、これで出てくれたなら、それなら。 通話が繋がった。 「まだ起きてたのか」 ひっそりと口元が弧を描く。彼女はぼんやりした声で「寝てました」と正直に答えた。ふわふわした、いかにも起き抜けの声は素直だ。「じゃあ、そのまま聞いとけ」と言った俺の声にも、素直にむにゃむにゃと「はい」とも「うん」ともつかない返事が返ってくる。素直なの声は、俺の素直な言葉も引き出した。 「、俺お前のこと好きなんだよ」 「……わたしもですよ」 「知ってる」 「わたし、先輩以外はいやですよ」 「ああ。だから付き合わねえか」 「……遅いですよ、言うの」 「うるせえ。こっちだってタイミング見計らってたんだよ」 「何でこのタイミングなんですか」 「お前が高い土鍋買ってまで俺と飯食ってくれたからだよ」 に拗ねた声を出されると、どうしても少しだけ誤魔化してしまう。 俺は軽く目を瞑って、さっき眠る前に浮かんだ彼女の笑みをもう一度思い浮かべた。今、電話口で同じ表情を浮かべていると、そう期待しながら。 「じゃあ明日の朝会いに行きますから、その時また言ってくれたら交際の件考えてあげます」 「バカ、いつでも言ってやるよ」 俺の即答に彼女が笑い声で応える。その笑い声につられて俺も笑いながら、この笑い声が聴けたことでますます明日の朝でもいつでも言うことができると、確信できた。ふわふわした声で「それじゃあおやすみなさい」と言うに、口元は笑ったまま俺も返事を返す。 通話を切った、その手の中の端末をじっと眺めながら、自室に感じた嫌な静かさがもうなくなっていることに気付いた。 (16/02/02) |