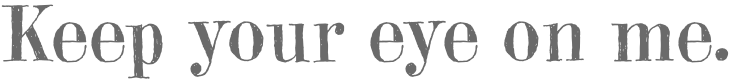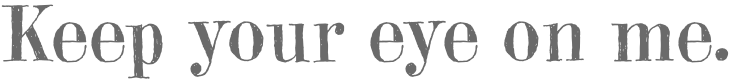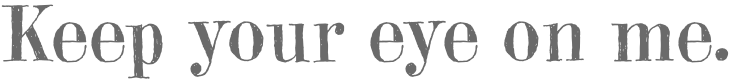
紙パックに入ったオレンジジュースを思いっきり吸ったせいでムンクの叫びみたいな顔になったと思う。そんなわたしのひどく驚いたリアクションが気に障ったのかリコの方は呆れたような引いたような変な顔をしてみせたけど、吸った勢いのまま飲み込んだそれが気管に入らなかっただけよしとしてほしい。もしここでゲホゲホとむせたら面倒くさいことになってたぞと内心ひやっとする。リコとは長い付き合いだからこうしてお昼休みにご飯を一緒に食べる回数もかなり多い。その中でわたしがむせてリコに背中をさすってもらった回数も片手くらいはありそうだ。
という現実逃避をしてたらリコは変な顔をすっと引っ込めた。それからはあ、との溜め息をオプションに、机に両肘をついて手の甲に顎を乗せてみせた。可愛いポーズもリコがやると様になるなあ。「…とにかく、」
「私が言うのも何だけど、うちの男どもはほーんとバスケばっかよねえ」
伊月くんが女の子をフッたらしい。リコから聞かされたその情報はわたしにとってムンクのモノマネを余儀なくさせるほどの衝撃だったのだ。隣のクラスの伊月俊くんも中学からの付き合いで、リコつながりで中学二年の頃に知り合った。でも知り合う前からかっこいいって周りの友達が話してたのは知ってたし、知り合ったあとから意識していたら、伊月くんに告白したって噂が流れた女の子はそれなりの人数がいた。わたしがリコの前でむせた回数より多いんじゃないかなあ。それなのに依然彼に彼女ができたという噂はなく、今度こそ有力なんじゃないかと思っていただけに、わたしは少し、少し……なんだろう?リコの肘あたりに目を落としながら、オレンジジュースをもう一口だけ口に含む。……伊月くんは、B組のあの子をフッたのだ。
「でもその子、伊月くんと仲いいって聞いたことあるよ」
「仲がいいだけで伊月くんにとってはそれ以上の対象じゃなかったんじゃない?」
「うーん……やっぱり、そういうものなのかなあ」
前にも提示された結論を改めて考えてみるけれど簡単には頷けなかった。うまく納得できなくて、首をかしげて斜め上に視線をやる。「はそもそもあんまり男子と話さないし仲がいい男子ほどよく話すから、よく話す男子が恋愛対象になるのよね」続くリコの台詞には迷わずうんと首を縦に振る。そう、その通りだ。好意と親密さって、イコールで結ばれるものなんじゃないかなあ。わたしはすきな人と仲良くなりたいと思うよ。
それに、ただでも高校生って、あっちでもこっちでも惚れた腫れたの色恋話が溢れ返ってるから、乗り遅れたくないって、かわいい女の子がいたら付き合いたいって、男の子は思うんじゃないかなあ。…でも伊月くんがそういうのに乗りたいと思うタイプには見えないから、やっぱりリコの言う通りなのかも。
「第一、だって伊月くんと仲がいいじゃない」
「えー、そうかなあ?」
「そうよ!だって伊月くんと同じかそれ以上に仲がいい男子っている?」
「小金井くん」
「ああ小金井くんね……そっかあいつがいたか…」
なぜか悔しそうに頭を押さえるリコがおかしくてちょっと笑ってしまった。面白半分でなんでそんな悔しそうなのと聞いてみれば、「いえ…」と気まずそうに目を逸らされる。なんだなんだ、わたしと小金井くんが仲良いことくらい、リコならよく知ってるだろうにね。伊月くんは、そうだね、小金井くんの次に仲がいいかも。それは素直にありがたいことだ。
小金井くんとは高校で知り合った仲でリコや伊月くんたちに比べたら短い期間だけど、やけに馬が合って意気投合した。今度小金井コーチによるテニス教室を開いてもらう約束をしているのだけど、あいにくバスケ部のみんなは部活が多忙なので予定がうまく合わないでいるのだ。それは仕方ない。彼らは今、冬の大会に向けて一生懸命なのだ。それを邪魔することはできないし、きっと誠凛高校バスケ部の誰もが邪魔することを許さないだろう。彼らはひたむきにバスケに打ち込んでいる。その姿がみんな眩しいから、わたしは部外者ながら応援をしたくなる。
そう、本当に忙しいのだ。伊月くんが、女の子の告白を断る理由にするくらいに。
「ねえ」
紙パックを机に置いたところで固まっていたらしい。我に返ったのは、リコがわたしの手元をじっと見ていたのに気付いてからだった。
「うん?」
「この流れで聞くのもおかしいかもしれないけど……って小金井くんのことすきなの?」
「えっ?!」
ぎょっとしてしまう。「違う違う!!そんなことないよ!!」手をブンブン振りながら否定すると必死さが伝わったのかリコはちょっと引き気味に背筋を反らしながら、そうなの?と確認の相槌を打った。それにはそうだよと語気を強めに返せばわかったわかったとなだめられる。本日二度目のびっくりだ。一気に顔が火照った気がして、振った手で自分の顔を扇ぐ。そんなに勘繰られるような何かを見せたつもりはないし、事実わたしと小金井くんの間にそういった気配は微塵もないのだ。うんうんと一人頷いて、それから心に違和感を覚えた。
「…そういえば誰かに似たようなこと聞かれた気がする……誰だっけ…」
違和感を口にしても思い出せなくて少しもやもやする。顎に手を当てうーんと首をひねっていると、リコは合点がいったようにああと声を漏らした。
「バスケ部の誰かじゃない?実は一時期うちの部員たちの中で話題になってたのよ」
「え」
なんと…。口をぽかんと開けてしまう。その話は初めて聞いたよ。一時期ってことはもう終わった話題なんだろうけど、それはちょっと居た堪れないぞ。「小金井くんのことそういう風に考えたことないよ…」話すのはとっても楽しいけど、と付け足す。本当のことだ。ここまで考えて、さっき自分が考えていた、好意と親密さのイコール関係との矛盾に気が付いたけれど、好意にもラブとライクがあるんだとすぐに結論付いた。そう考えると伊月くんが告白を断ったことに対するリコの見解も納得ができる。
「小金井くんもまったく同じこと言ってたわ」
「でしょ?」
ほらねとホッとして笑うと、リコも頷いて笑い返した。彼女の手が顎を乗せる仕事から解放され、お弁当箱を片付ける任務を課される。その白い両手を見ながら、さっきから忙しなかった心臓が、まだ落ち着いてないのを感じていた。無意識に机の片隅に置かれたオレンジジュースへ手を伸ばすと「あっ」上手に掴めなくてあわや落とすところだった。大丈夫?と心配してくれたリコに目を向けて頷くと、彼女はぱちぱちと目を瞬かせたあと、眉をハの字に下げた。
「の顔すごく赤い」
それは、どうしてだか、コイバナというのはそういうものなんだと思う。自分が登場するそれは頬を紅潮させ、その熱がわたしを干からびさせる。のどが渇いてしまうのだ。パクリとくわえたストローを吸い上げて飲み込むオレンジジュースはしかしもうぬるくなっていて、あまり潤うことはなかった。
ええと、どうしてこうなったんだっけ。伊月くんの話をしてたはずなのに、いいやでも、よく考えたらそこからすでに心臓は忙しかったような気がする。どうだっけ。
そこでわたしは、ちょっとだけ、さっき感じた違和感の正体を掴みかけるのだった。
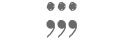
「あれ、」
スクールバッグを肩にかけて正門への道を歩いていると、向かいから歩いてきたその人と目が合った。誰だかわかったときには先に声を掛けられていて、開いた口のまま、「伊月くん」と返した。半袖と黒いズボンの練習着に、スポーツタオルを片手に持つ彼が今部活中なのは一目瞭然だった。お互い歩み寄り、ちょうど体育館脇の水道のところで足を止める。どうやら彼の目的は水道だったようだ。伊月くんの髪の毛が汗でまとまっているのを見上げて、水もしたたるいい男という言い回しを思い出していた。
「休憩時間?」
「ああ、十分休憩。は……教室の掃除が終わったのか」
「えっ」
思わず目を見開く。まさか伊月くんにそんなピタリと言い当てられると思っていなかったのだ。だって伊月くんは隣のクラスで、掃除場所は今週変わったばかりだ。もちろん彼にそんな話はしてない。まるでマジシャンだ。ぽかんと口を開け何も言えないでいると、その反応がよかったのか伊月くんは満足げに笑って、それからもったいぶるように、タオルを持った右手の人差し指をわたしに向けた。やや低い位置を指し示すそれを辿るようにゆっくりと視線を自分の手に落とすと、わたしの指先は赤と白と黄色でうっすらと染まっていた。「あ、」それで合点がいく。さっき黒板消しの掃除をしたときについたのが残ってたんだ。終わったあと手を払ってきたはずなのになあ。恥ずかしくて指先を隠すように両手を揉む。おもむろに流れ出したチューリップの歌は頭の片隅に追いやり、くすりと笑った伊月くんに目線を上げる。
「中学のときから思ってたけど、こんな時間まで掃除してるなんて、ってほんと真面目だよな」
目を細めて笑う伊月くんはそう言うと、わたしが何て返そうか考えてる間に水道と向かい合って、頭から水をかぶり始めた。他の当番の人がみんな部活とか委員会あるって言うから、帰宅部のわたし一人しかまともに残れなかったの。なんとか返した言葉は水の音でかき消されたのだろう、伊月くんは返事をしなかった。それには苦笑いをして、わたしも一つ空けた水道に手を伸ばして洗うことにした。今度は綺麗になるように、しっかりとこする。
「ぐっ!」
「?!」
突然鈍い音と同時に伊月くんが呻き声を上げた。驚いて顔を向けると、伊月くんがよろよろと横に移動し、後頭部を押さえうずくまったではないか。…あ、なるほど…?どうやら蛇口に思いっきり頭をぶつけてしまったようだ。「だ、」大丈夫、声をかけようと一歩踏み出す、のとほとんど同時に、伊月くんはバッと顔を上げた。
「チョークが手について超悔しい……キタコレ!!」
ぽかんと口を開ける。彼に対して本日二度目だ。伊月くんのダジャレ。もしかして、これを思いついたから言いたくて顔を上げようとしたら、蛇口の存在を忘れて思いっきりぶつけちゃったのか。心配した気持ちが一気に脱力していく。伊月くんのダジャレ聞くの、すきだけど、自分の身体は大事にしてほしいかなあ…。わたしがそう考えているのとは裏腹に、患部を掻きながら蛇口をキュッキュとひねる伊月くんはやたら満足げだ。その様子がおかしくて思わず笑い声を漏らしてしまうと、伊月くんはハッと目を輝かせた。「も今のいいと思うか?!」それに対してはどうだろうねと曖昧な返事をする。肯定と受け取ったらしい伊月くんはタオルで頭を拭きながら、戻ったらネタ帳に書かなきゃいけないなと呟いていた。さっきのマジシャンのような美しさを醸す彼とはまた違った一面だと思う。無邪気な伊月くんを見てるのはすきだった。
わたしも流しっぱなしだった蛇口を閉じ、カバンからタオルを取り出す。今度こそ綺麗になった。力を入れすぎて赤くなった指から水を拭き取りながら、そういえばと思いつく。聞いていいものかな、うん、いいよね。逡巡してすぐに顔を上げる。
「伊月くん、リコから聞いたんだけど」
「ん?」
「B組の子に告白されて、断ったんだって?」
「あー……」
水もしたたるいい男である伊月くんは髪を拭くのをやめ、やや気まずそうに首にかけたタオルで口元を隠した。この時点でリコの情報は正しかったことが決まり(元から疑ってはなかったけれど)、ついでに伊月くんが知られたくないとは思ってないこともわかった。
「そういえば昨日カントクに、に話していいかって聞かれたな」
「うん」
それに、相手の子は伊月くんに告白して、振られたことまでもいろんな人に言っているらしい。それならリコ直々に聞かなくとも、いつかはわたしの耳にも入ったんじゃないかと思う。用のなくなったタオルは再びカバンに戻してしまう。
「まあ…そうだな。告白されて断ったのは本当だ」
「あんなにかわいい子なのに?」
「確かにかわいい子だよな。俺じゃもったいないくらいだ」
「本当だよ」
軽口を叩くと伊月くんはおっと嬉しそうに目を大きく開いたあと、今度は満足げに、目を細めて深く笑みを浮かべた。綺麗な笑顔だ。わたしはよく、この笑顔に見とれていると思う。それに乾いてない髪の毛が重力に逆らって少し乱れてるのが、いつものサラサラな彼の髪には見慣れなくてよい。「なあ」だからその彼の口が開いたのに気付くのが、ワンテンポ遅れた。
「ん?」
「話変えちゃって悪いんだけどさ、って手小さいよな」
とっさに自分の手に目を落とす。まだ赤い指先に目は行くけれど、もうチョークの粉の姿は見えなかった。「ほら、」顔を上げると伊月くんが右手をパーの形に開いていた。彼の意図することがわかったわたしは、なんでもないように意識しながら、そこに自分の左手を重ねた。伊月くんの手の感触が伝わる。それと同時に何か別の物質が全身の血管を通って伝わってくる感覚を覚えた。
どうしてだろう、のどが渇いてる。
「ほら、やっぱり小さい」
そんなことない、と渇いた声で返したものの、強がりだってことはバレてるだろう。重ねた左手の向こうから、きれいに第一関節分、伊月くんの指先が見えていた。
自分の手に関して特別何か感想を抱いたことはないけれど、リコの手は、白くてスラッと長くて綺麗だと思ったことがある。伊月くんのも綺麗だと思うけど、リコとは違って、男の子らしく輪郭のはっきりした手だ。骨ばってるわけじゃないけど、肉の少ない細い手。体温は、少し低いかもしれない。
そこにたどり着いて、自分の手がいかに熱いかに気付いた。それが緊張から来ていることは言わずもがなで、自覚すると心臓の動悸まで指先に響いてくるようだった。ど、どうしよう、伊月くんに伝わっちゃってるかもしれない。泳がせた目線を一瞬伊月くんに向けるとぴたりと合ってしまった。それに更に動揺して指先を動かしてしまうと脳内は大パニックだ。次に取るべき行動が何なのかわからずいよいよ心臓も大忙しで目が回る。
そんなお手上げ状態だったわたしとは反対に伊月くんは冷静を保っていたのだろう。彼の指がするりと動いた。離れると思ったそれはわたしの手の甲を撫で、それから掴むような形で軽く握る。
「」
ほら君の声は落ち着いてる。「……うん?」わたしも努めて何でもないように返すけど、どうだろうか。伊月くんにバレてないといいけれど。
「手と手を繋いだ部分の粒子って、最大限拡大して見ると混ざり合ってるんだって」
「……粒子?」
「ああ。二人の手の粒子の境目がなくなるらしい」
「……そうなの?」
「まあ水素イオンとか酸素・CO2レベルの交換だから、本人の一兆……もしかしたら一京分の一って比率らしいんだけどな」
「…………でも、」
それでも、すごいことだね。繋がった手だけを見ながら、返す。今にもわっと爆発しそうになる衝動をこらえながら返す相槌はことごとく間の抜けたものだった。ここでわたしも手に力を込めて握り返したら、どうなるんだろう。残念ながら、意気地なしのわたしにはそんな勇気はないけれど。ゆっくりと一度だけ瞬きをして、目の前の伊月くんを見上げる。目が合う。と、今度は伊月くん、参ったって言いたそうに、眉尻を下げて小さく笑ったのだ。
「、あんまりそういう風に男のこと見ない方がいいぞ」
「え、……どうして?」
「上目遣いで見られるとドキッとするから」
あはは。「何言ってるの、ばか」伊月くんの冗談に少しだけ緊張がほぐれた。ちょっと笑うこともできた。
そうしてこのタイミングで、昼に覚えた違和感の正体が、ようやく判明した。小金井くんとの関係を最初に聞いてきたのは伊月くんだったのだ。そのときわたしは勘違いされてたことに驚くばかりで、必死で否定して納得が得られたあとはすぐに忘れてしまった。でも、改めて考えると。ある疑問が湧き上がる。
繋がれたままの手に目を落とした。伊月くんの右手はまだ、しっかりとわたしの左手を握っていた。それをじっと見る。瞬きを忘れていたかもしれない。
「……伊月くん」
「うん?」
「B組の子、フッちゃったってやつ」
「……うん」
「理由は、部活だけ?」
今度は伊月くんの指先がぴくっと動いた。わたしと同じ意味なら、今は彼が動揺を見せたのだろう。かくいうわたしの方も心臓がばくばくとうるさい。変なことを聞いた自覚は、ある。どうしよう、何を勘違いしてるんだとか、言われそうだ…。
「……本当は、」
「…うん」
「もちろん部活のことは本当だ。本当だけど……もう一つ理由があると言えば、あって…」
すきな子がいる、から。今日初めて見る彼の歯切れの悪い物言いに、心臓の鼓動は確実に指先まで伝わっていた。ああちょっと、待って、聞くタイミングを間違えたかもしれない。こんなときに聞くのはよくなかった。伊月くんの意図してない意味まで勝手に受け取ってしまう。
だって受け取りたいと思ってしまったのだ。好意と親密さのイコール関係を裏付けるように、わたしは、伊月くんを、……もしかしたらリコはわかってて言ったのだろうか。同じ仲良しな男の子であるはずの小金井くんと伊月くんが、わたしの中で根本的に違うってこと。わたしなんて今気付いたのに、さすがだ。
「そう、なの」
伊月くんも、昨日告白した女の子のことは、ライクの次元だったんだ。それで、ラブの次元ですきな子じゃないと付き合えないと思った彼は、体のいい断り方として、「部活が忙しいから」と返した、のだろう。
するりと手が離れる。自由になった手は、けれど彼の前ではどうしてもダメな気がして、わたしは身体の横に戻すことしかできなかった。伊月くんがわたしを見下ろしているのがよくわかった。助けを求めるように彼を見上げるけれど、伊月くんはわたしの救助なんか考えてないようで、やっぱり静かに口角を上げて笑っているだけだった。
「俺、すきな子としか手繋ぎたくないんだ」
ああ君、さっきの歯切れの悪い物言いはどこいったの。わたしだけ置いてけぼりだ。「じゃあそろそろ休憩終わるから、行くな」そう言った彼には、うんと頷くだけだ。普通に返せただろう。結局伊月くんには助けてもらえず…いいやこの場から解放されることは救助に当たるのかもしれない。けれど助けてもらったことよりもっとひどい、ミサイルのような言葉で貫いた彼は、踵を返して体育館に戻っていくようだった。「いづきくん」反射的に顔を上げ、呼び止める。
振り返った彼の頬が、赤くなって見えるのは夕焼けのせいだろうか。
「部活、応援してるね」
今出せる精一杯の声で激励を送ると、伊月くんは嬉しそうに頷いた。軽く手を振ったのが彼の右手で、さっきわたしはあの手から彼の粒子を受け取ったのだと思うと、こらえきれなくて破顔してしまった。
体育館の角を曲がった彼を見送ってから、わたしも歩き出す。(すきな子としか手繋ぎたくないんだ)伊月くん、さっきわたしにそんな目で男を見ない方がいいって言ったけど、伊月くんこそ手を繋いだ女にそんなこと言っちゃダメだよ。ドキッとするどころじゃない、勘違いしてしまうよ。
振り返ると体育館から誰かの声が聞こえる。バスケ部のみんな応援したい。でも伊月くんだけは、特別応援したいのかもしれない。だって伊月くんはどうやら、わたしの特別らしいのだ。
それで、ねえ、もし伊月くんも、わたしのことすきだったらどうしようか。彼と合わせた左手はまだ熱いのだ。
|
|