|
「お前らってなんかおかしいよ」 大学で同じゼミの男の子が眉を顰めてそう私に告げてきたのは、二宮がゼミ室へ現れてから一分足らずで退室してすぐのことだった。 その時の私は随分久しぶりに彼の顔を見れたことをただただ喜んでいたのだが、そう鹿爪らしい顔をされると私もなんだか浮かれてはいけないような気がして、ひとまず頬を弛めないよう気を配りながら「なにが?」と返した。 運がいいのか悪いのか、部屋には私と彼以外の誰も居ないので会話の内容を気にする必要もない。恐らく彼はかなり前からそのことを言いたかったのだろう。用意していたかのような言葉が深刻そうな口ぶりでつらつらと並べられた。 「だって、お前ら付き合ってるんだろ? なんであいつのパシリみたいなことしかしてねぇんだよ」 考えるよりまず苦笑が零れてしまった。それを見た彼がますます眉を顰めてしまう。どうも外野から見るとパシリ《しか》してないように映るらしい。 「そんなことないよ」 苦笑した後では全く効果がない。彼は怪訝な顔を崩さずに、「そうかなぁ」と疑わしい目をこちらに向け続ける。私は、今受け取ったばかりのUSBを大事にコートのポケットにしまってから、「ホントにホント」と念を押して立ち上がった。やるべきことが出来てしまったからだ。 「パシられながら言われてもなぁ」 「パシリとかってつもりじゃないんだよ」 時計は午後三時二十分を指している。二宮くんに渡されたレポートは四時が締切だから今から印刷して、教授の部屋へ持っていけば間に合うだろう。学内で印刷できるパソコンルームの空室状況をスマホで確認しながら、「じゃあまた来週ね」とかなり強引に会話を切り上げた。切り上げられた方はまだ不服そうな顔をしている。 「なあ、ホントに大丈夫か?」 「だから、何も心配されるような感じじゃないって」 「……なんかあったら言えよな」 「うん、ありがとうね」 お節介。 心の中の一番意地の悪い部分がそう言った。 ゼミ室を出て、パソコンルームに向かいながらコートのポケットに手を突っ込む。指先でUSBを撫でながら、ポケットに手を突っ込む癖のある彼の歩き方を自然と思い浮かべていた。一緒に並んで歩くことなんて滅多にないことなんだけれど。 彼は《パシリ》と呼んだが、二宮くんは正しくないことはしていない。 USBに入っているレポートもきちんと彼が彼自身で書いたもので、私は代筆なんて一切したこともない。ただ時間的な余裕がないから印刷して教授の部屋に提出するという煩わしい部分を私が担うだけだ。双方ともに《パシリ》だなんて思ってないし、思いたくない。 授業で配られた資料を渡したり、教授からの伝言を伝えたり、掲示板に出ていた情報を二宮くんに伝えたり、こうやって課題を教授へ手渡したり。 ……ああ、他人から妙な指摘を受けてしまったものだから、恋人らしからぬ行動しか思い出せない。 そんなこと、ないのに。 ボーダー隊員としての二宮くんはとても忙しい。私はあまり詳しく訊ねたことがないのだけれど、隊長という役目を背負う彼は恐らく私の想像以上に大変だろう。私は彼を困らせたくないので、その仕事内容も深く追わないし、もっと時間を作ってくれとも言わない。言えば妙なところで真面目な彼だから、時間を捻出してくれるかもしれない。でも私が見たいのは、私が一緒にいたいのは、そんな無理をする二宮くんじゃないのだ。 『』 パソコンルームで印刷をしていたら、手元のスマホの画面が明るくなって、ぴょこんと二宮くんからの呼びかけのメッセージが表示された。立て続けにもうひとつ。 『今日、夕飯そっちに行く』 伺い立ての語尾ではないが、彼に悪気はない。私がここで『用がある』とかなんとか言えば彼は無理強いはしないから、たぶんこういう言い回しも癖なんだろう。 『いいよ』 待ってるね、と付け加えるか数秒考えて結局消した。 片想いをするのは簡単だけれど、恋愛をするのって難しい。 大学一年生の春、初めて入った大きな講義室で偶然隣り合わせた彼の、凛とした横顔。その涼やかな顔に一目惚れしたときのことを妙に鮮やかに思い出した。 そういえば、夕飯を二宮くんと一緒に食べるなんてずいぶん久しぶりだ。 そんなことに気付いてしまうと、途端に夕飯をどう用意すればいいのか分からなくなってしまった。外に食べに行った方が余程楽なんだけど、『そっちに行く』と書いていた限り、私の家で食べるつもりなのだろう。 「……どうしよう」 ちょっと早めに帰宅した自分のアパートの前で、鍵をサムターンに入れて手を止めてしまう。買い物には行くつもりだった、というか今うちには大した食材がないので行かざるを得ない。時間は六時前。買い物をしながら献立を考えていても間に合うだろうか。 逡巡していたのは大した時間ではなかったと思う、が、私の思考を妨げて部屋の中からそっとドアが開けられた。音もなく開いたそれに、思わず肩が跳ねる。 「?」 現れたのは、今私が思考をぐるぐる巡らせる原因になっている彼だった。 「えっ……えっ?」 「驚かせたか」 「いや、えっと、うん」 二宮くんには一応合鍵を渡していた。どうして堅物の二宮くんに合鍵なんか渡しているのかというと、渡しておかないと本気で会える時間はなくなってくるからだ。かと言って、そう四六時中この合鍵が活躍しているわけではない。二宮くんの本当に気まぐれのようなものでこれは活用されている。その気まぐれが今日発動したらしい。 「えーっと、今日何食べたい? 買い出し今から行くんだけど」 「いや、もう夕飯は作り始めている」 今度こそ仰天した。 私が玄関先でぽかんと口を半開きにしたまま、突っ立っているのを見た二宮くんはほんの少し眉を動かして「どうしてそんなに驚く」と若干不思議そうな声を出した。 「悪いが勝手に台所を使わせてもらった」 「そ、れはいいけど……いや、ごめん、いいよ大丈夫」 《“けど”何なんだ?》と二宮くんの顔に書いてあったので、慌てて語尾を撤回して明確に承諾した。私の了承を確認して、くるりと彼は踵を返してしまう。 我が家の狭い狭いキッチンスペースとその先の一間の部屋を玄関から目隠ししている扉が開くと、確かに彼がキッチンスペースの前に立っているのが見える。いつも以上に狭く見えた。その狭い空間で二宮くんはどうやら玉ねぎを刻んでいるようなのである。 「何作ってくれてるの?」 ひょいと肩口から覗き込んでも、刻まれた玉ねぎしか分からない。二宮くんはこちらを振り返りもせずに、「荷物を置いて手を洗ってこい」と私に言った。答えになっていないけれど、二宮くんが正しいので「はぁい」と返事を返しておく。 きちんと手を洗って洗面所から戻ってくると、二宮くんは難しい顔をしてまな板の上の豆腐と睨み合っていた。豆腐は端の方がぼろりと崩れてしまっている。様子を見るに、上手く切るのに失敗したらしい。 「何作ってくれてるの?」 豆腐には触れずに再度問いかける。二宮くんはようやくこちらを振り返ると、「麻婆豆腐だ」と簡潔に答えてくれた。答えて、また豆腐に向き直ってしまう。麻婆豆腐。何でまたそんな微妙に初心者らしからぬものに挑戦しているのだろうか。 「……麻婆豆腐好きなんだ?」 「……」 黙ってしまった二宮くんを、あれ? と思いながらななめ後ろから観察する。沈黙してしまった彼の手元は動いていない。あんまり見たことのない姿に、そんなに変な質問だったろうかと首をかしげていると、手を止めたままの彼が顔を顰めてこちらを振り向いた。 「が好きなんだろう?」 ――またぽかんと口が開いてしまった。 麻婆豆腐が好きだなんて二宮くんに言ったこともないし、そもそも大好物というわけではない。いやいや、嫌いではないんだけども。 「えっと……?」 「……この前、中華料理屋でやたら美味そうに食べてただろ」 顰めたままの顔で言う彼の言葉に、また言葉を失う。確かに、先月行ったお店では麻婆豆腐を食べた。とても美味しかった。それを見て、今日麻婆豆腐を作ろうと、そう決めてくれたのだろう。 じわじわと頬が火照っていく。今、どうしようもなく嬉しい。二宮くんの推測が当たってるとか当たってないとかではなく、そうやって彼が考えてくれたことが。 「嫌いだったか?」 「嫌いじゃないよ。あの、ありがとう」 照れながら伝えた言葉に返事はなかった。彼の顰め面の眉間のしわが緩んで、けれど表情が変わり切る前に無言で豆腐へ顔は向けられてしまう。 二宮くんの顔が、きちんと見られないのは残念だったけれど自分の今の顔が見られなくてよかった。今、嬉しさに弛みきった顔をしているのが自分でも分かる。頬が熱い。 外から見たら私ばかり尽くしているように見えるのかもしれない。でも、そうじゃない。昼間、不安になった心はこんな単純なことであっという間に満たされた。とっても単純で、でもだからこそ二宮くんでないと満たせない。 「、今日レポート、ありがとう」 背中を向けたままの二宮くんが、さも今思い出したかのように言った。彼はいつもきちんとお礼を言ってくれる。私に二宮くんが与えてくれるものの一つ。 なんだかたまらない気持ちになって、ちょっとばかし勇気を出した私は向けられたままの背中にぎゅっと抱きついたのだった。 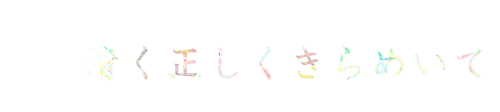 (16/01/28) Thank you!! title:エナメル / pict:moss |