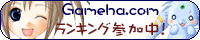作品ID:1139
あなたの読了ステータス
(読了ボタン正常)一般ユーザと認識
「神算鬼謀と天下無双」を読み始めました。
読了ステータス(人数)
読了(67)・読中(0)・読止(0)・一般PV数(213)
読了した住民(一般ユーザは含まれません)
神算鬼謀と天下無双
小説の属性:一般小説 / 未選択 / 感想希望 / 初級者 / 年齢制限なし / 連載中
前書き・紹介
そえのネタバレ解説! バッサラーヌ平原
| 前の話 | 目次 | 次の話 |
ども、そえです。
今回はバッサラーヌ平原での一戦を解説します。
まず、この戦場のネタは「カンネーの戦いです」
かなり有名な戦いです。
以前、解説にも出したカルタゴの名将、ハンニバル・バルカ
彼の真骨頂とも言うべき戦いです。
またハンニバルをネタにしたの?(’’
と、言われると思って、当初、レノーク湖畔の戦いを変更。もしくは、この戦いを変更しようと思いました。
が、やはり今後の展開では必要な一戦だと考え、今回の運びとなりました。
さて、カンネーの戦いとはなんぞや? そんなの知るわけねぇだろボケ!
と、様々なご批判が此処彼処から聞こえますので解説を始めたいを思います。
興味が湧きましたら、ググるか、ウィキペディアなので調べて下さい。
この戦いは紀元前216年8月2日、アブリア地方のカンナエ(カンネー)で、行われた共和国ローマとカルタゴの最大の決戦です。
さて、以前の解説でレノーク湖畔のモデルとなったトラシメヌス湖畔の戦いなどで大打撃を被った共和国ローマは、新独裁官ファビウスの方針によって持久戦を挑みました。
さすがのハンニバルも敵地での持久戦は望むところでは無く、ましてや遠く本国から離れている為、まともに補給を受ける事もできない状況でした。
よって、ハンニバルとしては一刻も早くローマと決戦を挑みたいという願いがありました。
そこで、ハンニバルはイタリア全土を略奪しました。引っ込むなら、全てを焦土にするぞ? という、脅しです。
しかし、ファビウスは懸命に耐えました。これが、ハンニバルが決戦を挑むための挑発である事が明らかだった為です。
が、他の者達は違いました。ファビウスの持久戦は臆病であると散々に罵り、共和国全体で決戦を挑むべきだ! という声が上がりました。
そして、ファビウスの独裁感の任期が終了したと同時に、ファビウスの方針に大反対していた二人の男が執政官に選ばれました。
ルキウス・アエミリウス・パウルス
ガイウス・テレンティウス・ウァロ
この二人は、ローマ史上、最大規模の兵を動員する事を決定しました。
その数、四個軍団、約八万です。
二人は戦う事を望んでいましたが、戦う方針が違いました。
パウルスは正面決戦は回避すべきと主張
ウァロは決戦をするべきと主張
結局当日最高指揮官であるウァロが決戦を挑み、カンネーの戦いは発生しました。
ローマ軍は野営地の警備に一万を残し、残る約七万を戦場に展開。
重装歩兵 55000
軽装歩兵 8?9000
騎兵 6000
布陣: 中翼 主力重装歩兵を中央、その前面に軽装歩兵 64000
右翼 ローマ騎兵 2000
左翼 ローマ同盟国騎兵 4000
ハンニバル率いるカルタゴ軍も戦場に展開 その数五万。
重装歩兵 32000
軽装歩兵 8000
騎兵 10000
布陣: 中翼 重装歩兵、その前面に軽装歩兵
中央部はガリア歩兵&スペイン歩兵
左右はカルタゴ歩兵
右翼 ヌミディア騎兵 4000
左翼 スペイン・ガリア騎兵 6000
ここで、一つ ん?(’’ と思われると思います。
ローマは騎兵が少ないのです。というのも、歩兵が主力であり、馬の保有数が少ないのです。(ローマの騎兵は当時は弱小だった)もっぱら、騎兵は同盟国(従属国)から借り出していました。
一方、カルタゴはガリアやら、スペインやら、ヌミディアなどなど、なんで複数なのか?
カルタゴは軍隊は少数であり、傭兵を雇う事で数を補っていました。無論、それだけでは足りないので、ハンニバルはローマに反抗するガリア部族を味方に引き入れていました。ちなみにスペインはハンニバルの本拠地です。
ガリア部族は現在で言うフランスで生活する住民と考えて頂ければ宜しいかと。遠征の途上で味方に引き入れていました。
ローマは歩兵は自前の当時世界最強の訓練を積み重ねた歩兵軍団。
カルタゴは傭兵やら、ガリア部族との混成という烏合の衆。
うん、普通勝てない(’’
さて、この戦いがどのように行われたか。
ハンニバルの意図は最初から包囲殲滅でした。彼は包囲殲滅にこだわっていました。それは、ローマを屈服させる為には殲滅が一番だと考えていた。と私は考えています。過去、数度の戦いは全て殲滅戦でした。
よって、今回も殲滅するつもりでしたので、まずハンニバルが考えたのは、圧倒的兵数を誇る歩兵部隊の攻勢をどのように耐えるか、でした。
ハンニバルは弓形の湾曲陣形を作り、縦深陣形にしました。そして被害が大きいと考えられた中央部隊は主力のカルタゴ兵では無く、ガリア兵でした。
そして、もう一つ注目すべき点は、騎兵の圧倒的兵数の有利でした。
ローマ六千に対して、カルタゴは一万でした。
そして、ヌミディア騎兵は最強の騎兵として名高かった。
そこで、4000に対して6000を 2000に対して4000 それぞれぶつける事で、有利にしました。
戦いの展開は本編と同じです。これは、変更することすら憚れました。
まず、騎兵部隊が突撃。左翼スペイン・ガリア騎兵は二つに分かれて挟撃。
その後、再編成してヌミディア騎兵と戦っている左翼騎兵部隊の後背を攻撃してまた挟撃。
この間、ローマ軍は歩兵部隊を前進。カルタゴ軍を圧倒しましたが、弓形の湾曲陣形の為、ローマ軍の前進速度は緩やかでした。しかし、圧倒的兵力を用いて中央部隊を激しく攻撃。しかし、戦列両翼は熟練のカルタゴ兵に阻まれて前進できませんでした。
結果、陣形は Vの字のようになっていました。
この時点で、ローマ騎兵部隊を壊滅させたカルタゴ騎兵がローマ軍の後方を襲撃。
スペイン・ガリア騎兵 ヌミディア騎兵
↓ ↓
カルタゴ歩兵左翼 → ローマ軍 ← カルタゴ歩兵右翼
↑ ↑
ガリア&スペイン歩兵
まぁ、最終的にはこのような状況でしょうか。うん。完全包囲。
結果ですが
ローマ軍 死傷者 60000(大半は戦死)
野営地 10000 捕虜
執政官パウルス 戦死
執政官ウァロ 逃亡
元老院議員約80名死亡(当時300人程度なので1/4が死亡)
カルタゴ軍 死傷者約6000(大半は中央のスペイン・ケルト兵)
烏合の衆であり、兵力的に劣勢のカルタゴ軍が世界最強のローマ軍殲滅したという戦史上稀にみる快挙でした。
元老院の1/4も死亡。
事実上、ローマ共和国が崩壊寸前まで追い込まれた瞬間でした。
せっかくなので、その後どうなったかを解説します。
この戦いに参加して、辛くも生き残った一人の青年がいました。
まだ、この時は若干20歳。
その名はプブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス・マイヨル
一般的にはスキピオ・アフリカヌス、大スキピオと称される人物です。
彼はカルタゴの戦いにカンネーの前から参加しては辛くも生き残り、カンネーでも生き残りました。
天才的な用兵を駆使する敵将ハンニバル。
個人的な推測ですが、恐れ、同時に尊敬したのでは無いでしょうか。
名将、名将から学ぶ。と、言えるでしょう。
スキピオの最大の特徴はその優れた戦略眼と私は思っています。
5年後、25歳で軍団指揮官に抜擢された後、彼はハンニバルの弱点を的確に捉えていました。
ハンニバルの弱点
1、カルタゴ兵は少なく、傭兵に頼っている
2、騎兵はヌミディア兵に頼りっぱなし
3、ハンニバルの遠征はカルタゴにとって本意で無く、ハンニバルとカルタゴ本国に深い溝がある。
4、ハンニバルの兵站は本拠地であるスペインと現地調達で賄っている。
5、カルタゴ本国の内情は政治の腐敗が進み、敵にならない。また、ハンニバルの勝利を自分の勝利と勘違いしている為、カルタゴ本国の防備は薄い
6、カルタゴはハンニバルに救援、補給を一切しない。よって、攻城兵器、兵力、物資共に不足している。その為、ローマに直接攻撃できない。
この六つをスキピオは狙いました。対策は以下の通り。
1、ハンニバルの本拠地であるスペインを五年かけて攻略。
狙い:ハンニバル軍の兵站にさらなる負荷をかける
2、シチリア島で軍を編成。惰弱なローマ騎兵を徹底的に鍛え上げる。
狙い:弱点であるローマ騎兵の強化
3、アフリカ遠征を断行。カルタゴ、ヌミディア連合軍を撃破
狙い:ヌミディアを降伏させ、ヌミディア騎兵を引っこ抜く
狙い:カルタゴ本国を孤立化させ、ハンニバルを本国に召還させる
これらの的確な対策により、カルタゴ軍は徹底的に弱体化、さらに、ハンニバルをカルタゴに強制撤退に追い込む事に成功します。
そして、紀元前202年10月19日。カンネーの戦いから実に十四年後。
ザマの戦いが発生。(詳しくは調べてね 長くなるから)
この戦いでスキピオは自身の集大成であるカンネーの再現を行い、ハンニバルを打ち破る。
最後にこれだけ記載して解説を終えたいと思います。
ハンニバル・バルカ
ザマの敗戦後、カルタゴはローマに降伏。莫大な賠償金の支払いを命じられ、地中海の覇権を失う。しかし、ハンニバルが陣頭に立ち、不可能と思われた賠償金を本気で完済させ、政治でもその実力を発揮したが、反ハンニバル派に命を狙われ、逃亡。紀元前183年、最後の逃亡先ビテュニアにて追い詰められて服毒自殺。
スキピオ・アフリカヌス
ザマの勝利後、カルタゴを降伏させる。帰国後、救国の英雄として称えられるが、特に地位を求めず隠遁生活を送る。対立が深かった政敵カトの謀略により政治の舞台から追放される。ローマに居場所が無い事を悟ったのか、カンパニア地方のリテルヌムで晩年余生を過ごす。紀元前183年、死去。
正面を歩兵で受け止め、騎兵の機動力を用いて敵軍背後を突く。包囲殲滅という現代の陸軍士官学校で必ず教材になる戦術を確立した二人の英雄は、身内から妬まれ、身内に足を引っ張られ、奇しくも紀元前183年、同じ年に死去。
人の妬みほど恐ろしいものは無い。稀代の名将でも勝つ事叶わず。
今回はバッサラーヌ平原での一戦を解説します。
まず、この戦場のネタは「カンネーの戦いです」
かなり有名な戦いです。
以前、解説にも出したカルタゴの名将、ハンニバル・バルカ
彼の真骨頂とも言うべき戦いです。
またハンニバルをネタにしたの?(’’
と、言われると思って、当初、レノーク湖畔の戦いを変更。もしくは、この戦いを変更しようと思いました。
が、やはり今後の展開では必要な一戦だと考え、今回の運びとなりました。
さて、カンネーの戦いとはなんぞや? そんなの知るわけねぇだろボケ!
と、様々なご批判が此処彼処から聞こえますので解説を始めたいを思います。
興味が湧きましたら、ググるか、ウィキペディアなので調べて下さい。
この戦いは紀元前216年8月2日、アブリア地方のカンナエ(カンネー)で、行われた共和国ローマとカルタゴの最大の決戦です。
さて、以前の解説でレノーク湖畔のモデルとなったトラシメヌス湖畔の戦いなどで大打撃を被った共和国ローマは、新独裁官ファビウスの方針によって持久戦を挑みました。
さすがのハンニバルも敵地での持久戦は望むところでは無く、ましてや遠く本国から離れている為、まともに補給を受ける事もできない状況でした。
よって、ハンニバルとしては一刻も早くローマと決戦を挑みたいという願いがありました。
そこで、ハンニバルはイタリア全土を略奪しました。引っ込むなら、全てを焦土にするぞ? という、脅しです。
しかし、ファビウスは懸命に耐えました。これが、ハンニバルが決戦を挑むための挑発である事が明らかだった為です。
が、他の者達は違いました。ファビウスの持久戦は臆病であると散々に罵り、共和国全体で決戦を挑むべきだ! という声が上がりました。
そして、ファビウスの独裁感の任期が終了したと同時に、ファビウスの方針に大反対していた二人の男が執政官に選ばれました。
ルキウス・アエミリウス・パウルス
ガイウス・テレンティウス・ウァロ
この二人は、ローマ史上、最大規模の兵を動員する事を決定しました。
その数、四個軍団、約八万です。
二人は戦う事を望んでいましたが、戦う方針が違いました。
パウルスは正面決戦は回避すべきと主張
ウァロは決戦をするべきと主張
結局当日最高指揮官であるウァロが決戦を挑み、カンネーの戦いは発生しました。
ローマ軍は野営地の警備に一万を残し、残る約七万を戦場に展開。
重装歩兵 55000
軽装歩兵 8?9000
騎兵 6000
布陣: 中翼 主力重装歩兵を中央、その前面に軽装歩兵 64000
右翼 ローマ騎兵 2000
左翼 ローマ同盟国騎兵 4000
ハンニバル率いるカルタゴ軍も戦場に展開 その数五万。
重装歩兵 32000
軽装歩兵 8000
騎兵 10000
布陣: 中翼 重装歩兵、その前面に軽装歩兵
中央部はガリア歩兵&スペイン歩兵
左右はカルタゴ歩兵
右翼 ヌミディア騎兵 4000
左翼 スペイン・ガリア騎兵 6000
ここで、一つ ん?(’’ と思われると思います。
ローマは騎兵が少ないのです。というのも、歩兵が主力であり、馬の保有数が少ないのです。(ローマの騎兵は当時は弱小だった)もっぱら、騎兵は同盟国(従属国)から借り出していました。
一方、カルタゴはガリアやら、スペインやら、ヌミディアなどなど、なんで複数なのか?
カルタゴは軍隊は少数であり、傭兵を雇う事で数を補っていました。無論、それだけでは足りないので、ハンニバルはローマに反抗するガリア部族を味方に引き入れていました。ちなみにスペインはハンニバルの本拠地です。
ガリア部族は現在で言うフランスで生活する住民と考えて頂ければ宜しいかと。遠征の途上で味方に引き入れていました。
ローマは歩兵は自前の当時世界最強の訓練を積み重ねた歩兵軍団。
カルタゴは傭兵やら、ガリア部族との混成という烏合の衆。
うん、普通勝てない(’’
さて、この戦いがどのように行われたか。
ハンニバルの意図は最初から包囲殲滅でした。彼は包囲殲滅にこだわっていました。それは、ローマを屈服させる為には殲滅が一番だと考えていた。と私は考えています。過去、数度の戦いは全て殲滅戦でした。
よって、今回も殲滅するつもりでしたので、まずハンニバルが考えたのは、圧倒的兵数を誇る歩兵部隊の攻勢をどのように耐えるか、でした。
ハンニバルは弓形の湾曲陣形を作り、縦深陣形にしました。そして被害が大きいと考えられた中央部隊は主力のカルタゴ兵では無く、ガリア兵でした。
そして、もう一つ注目すべき点は、騎兵の圧倒的兵数の有利でした。
ローマ六千に対して、カルタゴは一万でした。
そして、ヌミディア騎兵は最強の騎兵として名高かった。
そこで、4000に対して6000を 2000に対して4000 それぞれぶつける事で、有利にしました。
戦いの展開は本編と同じです。これは、変更することすら憚れました。
まず、騎兵部隊が突撃。左翼スペイン・ガリア騎兵は二つに分かれて挟撃。
その後、再編成してヌミディア騎兵と戦っている左翼騎兵部隊の後背を攻撃してまた挟撃。
この間、ローマ軍は歩兵部隊を前進。カルタゴ軍を圧倒しましたが、弓形の湾曲陣形の為、ローマ軍の前進速度は緩やかでした。しかし、圧倒的兵力を用いて中央部隊を激しく攻撃。しかし、戦列両翼は熟練のカルタゴ兵に阻まれて前進できませんでした。
結果、陣形は Vの字のようになっていました。
この時点で、ローマ騎兵部隊を壊滅させたカルタゴ騎兵がローマ軍の後方を襲撃。
スペイン・ガリア騎兵 ヌミディア騎兵
↓ ↓
カルタゴ歩兵左翼 → ローマ軍 ← カルタゴ歩兵右翼
↑ ↑
ガリア&スペイン歩兵
まぁ、最終的にはこのような状況でしょうか。うん。完全包囲。
結果ですが
ローマ軍 死傷者 60000(大半は戦死)
野営地 10000 捕虜
執政官パウルス 戦死
執政官ウァロ 逃亡
元老院議員約80名死亡(当時300人程度なので1/4が死亡)
カルタゴ軍 死傷者約6000(大半は中央のスペイン・ケルト兵)
烏合の衆であり、兵力的に劣勢のカルタゴ軍が世界最強のローマ軍殲滅したという戦史上稀にみる快挙でした。
元老院の1/4も死亡。
事実上、ローマ共和国が崩壊寸前まで追い込まれた瞬間でした。
せっかくなので、その後どうなったかを解説します。
この戦いに参加して、辛くも生き残った一人の青年がいました。
まだ、この時は若干20歳。
その名はプブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス・マイヨル
一般的にはスキピオ・アフリカヌス、大スキピオと称される人物です。
彼はカルタゴの戦いにカンネーの前から参加しては辛くも生き残り、カンネーでも生き残りました。
天才的な用兵を駆使する敵将ハンニバル。
個人的な推測ですが、恐れ、同時に尊敬したのでは無いでしょうか。
名将、名将から学ぶ。と、言えるでしょう。
スキピオの最大の特徴はその優れた戦略眼と私は思っています。
5年後、25歳で軍団指揮官に抜擢された後、彼はハンニバルの弱点を的確に捉えていました。
ハンニバルの弱点
1、カルタゴ兵は少なく、傭兵に頼っている
2、騎兵はヌミディア兵に頼りっぱなし
3、ハンニバルの遠征はカルタゴにとって本意で無く、ハンニバルとカルタゴ本国に深い溝がある。
4、ハンニバルの兵站は本拠地であるスペインと現地調達で賄っている。
5、カルタゴ本国の内情は政治の腐敗が進み、敵にならない。また、ハンニバルの勝利を自分の勝利と勘違いしている為、カルタゴ本国の防備は薄い
6、カルタゴはハンニバルに救援、補給を一切しない。よって、攻城兵器、兵力、物資共に不足している。その為、ローマに直接攻撃できない。
この六つをスキピオは狙いました。対策は以下の通り。
1、ハンニバルの本拠地であるスペインを五年かけて攻略。
狙い:ハンニバル軍の兵站にさらなる負荷をかける
2、シチリア島で軍を編成。惰弱なローマ騎兵を徹底的に鍛え上げる。
狙い:弱点であるローマ騎兵の強化
3、アフリカ遠征を断行。カルタゴ、ヌミディア連合軍を撃破
狙い:ヌミディアを降伏させ、ヌミディア騎兵を引っこ抜く
狙い:カルタゴ本国を孤立化させ、ハンニバルを本国に召還させる
これらの的確な対策により、カルタゴ軍は徹底的に弱体化、さらに、ハンニバルをカルタゴに強制撤退に追い込む事に成功します。
そして、紀元前202年10月19日。カンネーの戦いから実に十四年後。
ザマの戦いが発生。(詳しくは調べてね 長くなるから)
この戦いでスキピオは自身の集大成であるカンネーの再現を行い、ハンニバルを打ち破る。
最後にこれだけ記載して解説を終えたいと思います。
ハンニバル・バルカ
ザマの敗戦後、カルタゴはローマに降伏。莫大な賠償金の支払いを命じられ、地中海の覇権を失う。しかし、ハンニバルが陣頭に立ち、不可能と思われた賠償金を本気で完済させ、政治でもその実力を発揮したが、反ハンニバル派に命を狙われ、逃亡。紀元前183年、最後の逃亡先ビテュニアにて追い詰められて服毒自殺。
スキピオ・アフリカヌス
ザマの勝利後、カルタゴを降伏させる。帰国後、救国の英雄として称えられるが、特に地位を求めず隠遁生活を送る。対立が深かった政敵カトの謀略により政治の舞台から追放される。ローマに居場所が無い事を悟ったのか、カンパニア地方のリテルヌムで晩年余生を過ごす。紀元前183年、死去。
正面を歩兵で受け止め、騎兵の機動力を用いて敵軍背後を突く。包囲殲滅という現代の陸軍士官学校で必ず教材になる戦術を確立した二人の英雄は、身内から妬まれ、身内に足を引っ張られ、奇しくも紀元前183年、同じ年に死去。
人の妬みほど恐ろしいものは無い。稀代の名将でも勝つ事叶わず。
後書き
| 作者:そえ |
| 投稿日:2012/08/11 06:22 更新日:2012/08/11 06:22 『神算鬼謀と天下無双』の著作権は、すべて作者 そえ様に属します。 |
| 前の話 | 目次 | 次の話 |
読了ボタン

 小説鍛錬室
小説鍛錬室