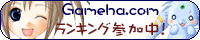作品ID:2048
あなたの読了ステータス
(読了ボタン正常)一般ユーザと認識
「感想批評の書き方講座」を読み始めました。
読了ステータス(人数)
読了(98)・読中(1)・読止(0)・一般PV数(287)
読了した住民(一般ユーザは含まれません)
感想批評の書き方講座
小説の属性:随筆・コラム / 未選択 / お気軽感想希望 / 初投稿・初心者 / 年齢制限なし / 連載中
前書き・紹介
【初めの注意事項】
「です。ます。」調か、「である。」調か、どちらにしようか悩みましたが、簡潔に伝えたいという意図から、「である。」調にすることにしました。ただ、あまり言い切って考えているのではなく、こういった考え方もあるのではないか、といった思いで書いていますので、そのあたりは、皆さんの脳内変換でお願いいたします。では以下本文。
1:感想を書くとは何か
| 目次 | 次の話 |
◇本記事の目的
読書感想文は、夏休みの宿題で面倒くさいもののトップクラスである。
まず、本を読むのが面倒くさいし、読んだ後に「感想」とかいう得体のしれないものを要求されるなど言語道断だ。
もしくは、本を読むこと自体は嫌いではない、むしろ好きという人もいるかもしれない。しかし、自分の頭から出てくるのは、「面白かった」とか、「つまらなかった」その程度である。400字も書くなんて、「そんな無茶な」となる。
本連載は、そんな人たちに、感想を書くというのは、見方を変えれば、
・それほど厳しい修行でも苦行でもない
ということと、
・感想を書くのは、自分のためにもなる
ということについて、少しでも感じていただくことを目的にしたい。
◇感想を書く必要性
次に、感想を書くというのは、そもそも何故必要なのかを考えてみたい。
それは、アウトプットしないものは、「ゼロ」だからだ。
人とかかわるとき全般において、「言語」を用いないことはない。
テレパシーや電脳通信の技術が発達しようと、「言語」というプロトコル(規格)が廃止されるのは、相当未来であるはずだ。もし仮にあるとしても、少なくても、我々が生きている間はありえない。
人は言葉を用いて、コミュニケーションをはかり、理解し、思考し、行動する。
これは動かしえない事実だ(なるほど、感情的な行動や脊髄反射的なのもあるかもしれないが、「意図して何かをしたり、伝えたりする」ということが本記事の取り扱う範囲なので、ここでは除外する)。
つまり、いくら「素晴らしい」とか「感動した」ないしは、「つまらない」「もっとこうした方が良い」ということを思ったとしても、それを言葉にして発信しなければ、世界(社会・環境・周囲の人)は変わらない。
だから、自分の思いをしっかりと伝えるために、感想を書くことが必要なのである。
◇感想を書くのは良いことか
と、前置き的なことを書いてきたけれども、そもそも、この記事を少しでも読もうと思って頂いた方々は、「感想を書きたくない」と強く思っているわけではないだろう。
むしろ、「書いた方がいいんだろうなぁ、でも……」となっているのだと思う。
書いた方がいい。
このことが伝わったら、本記事およびその連載は十分に役割を果たしたと思える。
しかし、何故、感想を書いた方がいいのか。
詳細は、今後の記事に任せたいけれども、感想を書くというのは、自分のためにもなるということだ。そして、これは、作品に対してのコミュニケーションにとどまらず、その他の文章を書くだとか、対面的なコミュニケーションにおいても十分役に立つことであるのだ。
◇事例
例をもって少し考えてみよう。
あなたは、とある作品を、インターネットの小説投稿サイトで読んだ。
それほど感動するまでもなかったが、時間があったのと、展開が少々気になったこともあって、最後まで読んだ。
読み終わった後の「感想」は、「まぁまぁかな」だった。
極端な例でいけば、この「まぁまぁでした」という感想だって、十分な感想文なのである。
学校の宿題の感想文は字数指定があるが故、感想文はある程度長く書かなければならないと思っている人が多いだろうが、そんなことはない。一言、二言だって、立派な感想文であるということを、まず認識して頂きたい。
ただし、さすがに、「まぁまぁでした」ということを、その小説投稿サイトの感想欄で書くことはお勧めしない。
まだ、「さいっこうに面白かったです!」ならいいかもしれない。しかしましてや、「面白くなかった」という一言だけならば、それは絶対に投稿すべきではない。誹謗中傷や、荒らしのように捉えられるだろう。
(ちなみに、良くなかった点を挙げて、改善案を示すというのが「批評」とか「レビュー」である。感想との違いなどについても、今後の記事で折を見て書いていきたい)
さて。
良かった感想でも、悪かった感想でも、この一言感想において共通した問題点は何か。
それは、「理由がない」ということである。
◇最低限「何故」を書く
先の事例において、「まぁまぁでした」という感想を抱いたケースを想定した。
しかしこれを受け取った作者さんは、「何が」「何故・どうして」「どの場面が」「どのように」、「まぁまぁ」だったのかさっぱり分からないのである。
5W1Hという言葉を聞いたことがあるだろう。感想を書く際に、それを置き換えて考えれば、
・何故=Why
・何が=What
・どの場面が=Where
・どのように=How
が必要であるということだ。
なお、5W1Hの残りの「When」「Who」については、
・いつ=When→感想を読んだとき
・誰が=Who→自分が(感想を書く人)
と確定しているので考える必要はない。
小難しい話になってきた、わけではないので、もう少し聞いて頂きたい。
もちろん、最終的には、「何故」「何が」「どの場面が」「どのように」を意識して感想を書くことが大事であるのだけれども、いきなりそんなことができる人は、この記事自体を読んでいないと思う。
大事なのは、その中で「何故」である。
◇自分に問う
そろそろ3000字に近づいてきた。そうそう、本連載記事の一つずつは、基本的に3000字にしていこうと思っている。何故かというと、たぶんそれぐらいが一まとまりの文章として読みやすいからだ。
少し飛躍するけれども、基本的な文章の書き方といったものは、基本的に、そのまま感想を書くことについても当てはまると思う。物語でいうところの起承転結なんてのがあるが、感想を書く際もそれを意識した方がいい。けれども、いきなりそんなことを考える必要はない。
事例を思い出してほしい。そもそも今は、「まぁまぁだった」という感想しか絞り出せていないのだ。
次にやるべき作業とは、「何故」を自分に問うことである。
自分はその作品を読んで、「何故」「まぁまぁ」という感想を抱いたのか、ということを考えてみる必要がある。ここでもう一つ思い出すべきは、「まぁまぁ」という感想も、立派な感想であったということだ。要するに、自分の中に沸き起こった感情を、言語化するというのが、感想を書くという行為そのものなのである。
そうしたとき、何か行動をして(ここでは、作品を読んで)何も感じないということは、殆どないのではなかろうか。「いやいや、本当に何も感じなかったんだって」という場合もあるかもしれない。ただ、今回の事例では、「まぁまぁ」という感想までは発生しているのだ。
何故か。
それを掘り起こすための具体的な作業について、今後触れていきたいけれども、一つ事例的な流れを書き出して、本記事は終わろうと思う。
◇ファーストステップ
「まぁまぁだった」
↓
「文章作法は十分だし、描写も、人物や情景のイメージが想起しやすかった」
↓
「でも、特に『まぁまぁ』という感想しかでてこなかった」
ここまで絞り出せたら、もう一言感想を卒業している。
初めに行う作業としては、ある程度自分の中でテンプレート(定型)化しておくとよいと思う。
私の場合は、まず、「技術的な」面を考えるようにしている。
もっと具体的に書けば、上の、「文章作法」と「人物描写」「情景描写」である。
それらに、「自分が」満足できたかを考えるということである。大事なことを書いた。「自分が」満足できるかどうか、である。
感想が書けない理由の一つに、「こんなこと思っていいのか」「こんなこと書いていいのか」というのがある。
いい!
しょうがない!
だって思ってしまったんだもの。
いろいろ大事なことが散在してしまっているが、感想を書くのに大事なことの一つに、「素直であること」というのもある。
上の事例でいけば、「文章作法が十分だ」なんて、「初心者素人アマチュアが、何を恐れ多い」と考えてしまうのも仕方がないだろう。
でも、自分を基準にしていいのである。「自分は、これぐらいの内容や描写がないと面白いと思えないな」というものを基準にして構わないのだ。だって感想だもの。
もちろん、歯に衣着せず、毒舌になるのがいいということではない。
どうしたら、ちゃんと作者に自分の思いが伝えられるのか、といったことも、今後触れていきたいと思うけれども、……おっと、3000字をゆうに超え始めてしまっている。
◇まとめ
・感想を書くことは良いことだ。一言感想だって立派な感想だ。
・感想を書くにはまず「何故」を考える。
・感想を書くときは「素直」になる。
読書感想文は、夏休みの宿題で面倒くさいもののトップクラスである。
まず、本を読むのが面倒くさいし、読んだ後に「感想」とかいう得体のしれないものを要求されるなど言語道断だ。
もしくは、本を読むこと自体は嫌いではない、むしろ好きという人もいるかもしれない。しかし、自分の頭から出てくるのは、「面白かった」とか、「つまらなかった」その程度である。400字も書くなんて、「そんな無茶な」となる。
本連載は、そんな人たちに、感想を書くというのは、見方を変えれば、
・それほど厳しい修行でも苦行でもない
ということと、
・感想を書くのは、自分のためにもなる
ということについて、少しでも感じていただくことを目的にしたい。
◇感想を書く必要性
次に、感想を書くというのは、そもそも何故必要なのかを考えてみたい。
それは、アウトプットしないものは、「ゼロ」だからだ。
人とかかわるとき全般において、「言語」を用いないことはない。
テレパシーや電脳通信の技術が発達しようと、「言語」というプロトコル(規格)が廃止されるのは、相当未来であるはずだ。もし仮にあるとしても、少なくても、我々が生きている間はありえない。
人は言葉を用いて、コミュニケーションをはかり、理解し、思考し、行動する。
これは動かしえない事実だ(なるほど、感情的な行動や脊髄反射的なのもあるかもしれないが、「意図して何かをしたり、伝えたりする」ということが本記事の取り扱う範囲なので、ここでは除外する)。
つまり、いくら「素晴らしい」とか「感動した」ないしは、「つまらない」「もっとこうした方が良い」ということを思ったとしても、それを言葉にして発信しなければ、世界(社会・環境・周囲の人)は変わらない。
だから、自分の思いをしっかりと伝えるために、感想を書くことが必要なのである。
◇感想を書くのは良いことか
と、前置き的なことを書いてきたけれども、そもそも、この記事を少しでも読もうと思って頂いた方々は、「感想を書きたくない」と強く思っているわけではないだろう。
むしろ、「書いた方がいいんだろうなぁ、でも……」となっているのだと思う。
書いた方がいい。
このことが伝わったら、本記事およびその連載は十分に役割を果たしたと思える。
しかし、何故、感想を書いた方がいいのか。
詳細は、今後の記事に任せたいけれども、感想を書くというのは、自分のためにもなるということだ。そして、これは、作品に対してのコミュニケーションにとどまらず、その他の文章を書くだとか、対面的なコミュニケーションにおいても十分役に立つことであるのだ。
◇事例
例をもって少し考えてみよう。
あなたは、とある作品を、インターネットの小説投稿サイトで読んだ。
それほど感動するまでもなかったが、時間があったのと、展開が少々気になったこともあって、最後まで読んだ。
読み終わった後の「感想」は、「まぁまぁかな」だった。
極端な例でいけば、この「まぁまぁでした」という感想だって、十分な感想文なのである。
学校の宿題の感想文は字数指定があるが故、感想文はある程度長く書かなければならないと思っている人が多いだろうが、そんなことはない。一言、二言だって、立派な感想文であるということを、まず認識して頂きたい。
ただし、さすがに、「まぁまぁでした」ということを、その小説投稿サイトの感想欄で書くことはお勧めしない。
まだ、「さいっこうに面白かったです!」ならいいかもしれない。しかしましてや、「面白くなかった」という一言だけならば、それは絶対に投稿すべきではない。誹謗中傷や、荒らしのように捉えられるだろう。
(ちなみに、良くなかった点を挙げて、改善案を示すというのが「批評」とか「レビュー」である。感想との違いなどについても、今後の記事で折を見て書いていきたい)
さて。
良かった感想でも、悪かった感想でも、この一言感想において共通した問題点は何か。
それは、「理由がない」ということである。
◇最低限「何故」を書く
先の事例において、「まぁまぁでした」という感想を抱いたケースを想定した。
しかしこれを受け取った作者さんは、「何が」「何故・どうして」「どの場面が」「どのように」、「まぁまぁ」だったのかさっぱり分からないのである。
5W1Hという言葉を聞いたことがあるだろう。感想を書く際に、それを置き換えて考えれば、
・何故=Why
・何が=What
・どの場面が=Where
・どのように=How
が必要であるということだ。
なお、5W1Hの残りの「When」「Who」については、
・いつ=When→感想を読んだとき
・誰が=Who→自分が(感想を書く人)
と確定しているので考える必要はない。
小難しい話になってきた、わけではないので、もう少し聞いて頂きたい。
もちろん、最終的には、「何故」「何が」「どの場面が」「どのように」を意識して感想を書くことが大事であるのだけれども、いきなりそんなことができる人は、この記事自体を読んでいないと思う。
大事なのは、その中で「何故」である。
◇自分に問う
そろそろ3000字に近づいてきた。そうそう、本連載記事の一つずつは、基本的に3000字にしていこうと思っている。何故かというと、たぶんそれぐらいが一まとまりの文章として読みやすいからだ。
少し飛躍するけれども、基本的な文章の書き方といったものは、基本的に、そのまま感想を書くことについても当てはまると思う。物語でいうところの起承転結なんてのがあるが、感想を書く際もそれを意識した方がいい。けれども、いきなりそんなことを考える必要はない。
事例を思い出してほしい。そもそも今は、「まぁまぁだった」という感想しか絞り出せていないのだ。
次にやるべき作業とは、「何故」を自分に問うことである。
自分はその作品を読んで、「何故」「まぁまぁ」という感想を抱いたのか、ということを考えてみる必要がある。ここでもう一つ思い出すべきは、「まぁまぁ」という感想も、立派な感想であったということだ。要するに、自分の中に沸き起こった感情を、言語化するというのが、感想を書くという行為そのものなのである。
そうしたとき、何か行動をして(ここでは、作品を読んで)何も感じないということは、殆どないのではなかろうか。「いやいや、本当に何も感じなかったんだって」という場合もあるかもしれない。ただ、今回の事例では、「まぁまぁ」という感想までは発生しているのだ。
何故か。
それを掘り起こすための具体的な作業について、今後触れていきたいけれども、一つ事例的な流れを書き出して、本記事は終わろうと思う。
◇ファーストステップ
「まぁまぁだった」
↓
「文章作法は十分だし、描写も、人物や情景のイメージが想起しやすかった」
↓
「でも、特に『まぁまぁ』という感想しかでてこなかった」
ここまで絞り出せたら、もう一言感想を卒業している。
初めに行う作業としては、ある程度自分の中でテンプレート(定型)化しておくとよいと思う。
私の場合は、まず、「技術的な」面を考えるようにしている。
もっと具体的に書けば、上の、「文章作法」と「人物描写」「情景描写」である。
それらに、「自分が」満足できたかを考えるということである。大事なことを書いた。「自分が」満足できるかどうか、である。
感想が書けない理由の一つに、「こんなこと思っていいのか」「こんなこと書いていいのか」というのがある。
いい!
しょうがない!
だって思ってしまったんだもの。
いろいろ大事なことが散在してしまっているが、感想を書くのに大事なことの一つに、「素直であること」というのもある。
上の事例でいけば、「文章作法が十分だ」なんて、「初心者素人アマチュアが、何を恐れ多い」と考えてしまうのも仕方がないだろう。
でも、自分を基準にしていいのである。「自分は、これぐらいの内容や描写がないと面白いと思えないな」というものを基準にして構わないのだ。だって感想だもの。
もちろん、歯に衣着せず、毒舌になるのがいいということではない。
どうしたら、ちゃんと作者に自分の思いが伝えられるのか、といったことも、今後触れていきたいと思うけれども、……おっと、3000字をゆうに超え始めてしまっている。
◇まとめ
・感想を書くことは良いことだ。一言感想だって立派な感想だ。
・感想を書くにはまず「何故」を考える。
・感想を書くときは「素直」になる。
後書き
次回、「感想と批評・レビューの違い」予定。
| 作者:遠藤 敬之 |
| 投稿日:2018/11/04 13:29 更新日:2018/11/07 20:42 『感想批評の書き方講座』の著作権は、すべて作者 遠藤 敬之様に属します。 |
| 目次 | 次の話 |
読了ボタン

 小説鍛錬室
小説鍛錬室