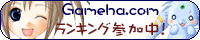作品ID:2049
あなたの読了ステータス
(読了ボタン正常)一般ユーザと認識
「感想批評の書き方講座」を読み始めました。
読了ステータス(人数)
読了(80)・読中(1)・読止(0)・一般PV数(292)
読了した住民(一般ユーザは含まれません)
感想批評の書き方講座
小説の属性:随筆・コラム / 未選択 / お気軽感想希望 / 初投稿・初心者 / 年齢制限なし / 連載中
前書き・紹介
【前回の復習】
前回は、
・感想を書くことは良いことだ。一言感想だって立派な感想だ。
・感想を書くにはまず「何故」を考える。
・感想を書くときは「素直」になる。
ことを書きました。今回は、その「素直」になる、という点と、感想と批評の違いについて触れていきたいと思います。
あと、本講座は、簡潔に伝えたいという意図から、「である。」調にすることにしています。上から目線に感じられるかもしれませんが、「こういった考え方もあるのではないか」という思いで書いていますので、そのあたりは、皆さんの脳内変換でお願いいたします。では以下本文。
2:感想と批評・レビューの違い
| 前の話 | 目次 | 次の話 |
◇前回事例を思い出す
前回、とある作品を小説投稿サイトで読んだと仮定して、
「まぁまぁだった」
↓
「文章作法は十分だし、描写も、人物や情景のイメージが想起しやすかった」
↓
「でも、特に『まぁまぁ』という感想しかでてこなかった」
といったことまでは考えた場合を想定した。
ここまでくれば、「まぁまぁだった」という感想を一言投稿するよりかは、格段に良くなっている。
「文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです」
と、「です。ます。」調にして少し自分の言葉に改編してみたらどうだろう。十分感想として成り立っているのではないだろうか。
いやいや、本記事読者のあなたが仰ることは分かる。さすがに寂しかろうと。
本記事では、これをもう少し膨らませるためにどうしたらいいかということと、感想と批評の違いについて触れていきたい。
◇5W1H
前回の記事で、感想においては、5W1Hのうち、
・何故=Why
・何が=What
・どの場面が=Where
・どのように=How
を意識することが大切だと書いた。
一方、今僕らの武器は、
「文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです」
これだけである。
文章作法が守られているかどうかは、「いる」「いない」のどちらかである。だから、膨らませることが難しい。
目をつけるべきは、描写部分である。
「人物や情景が浮かびやすかった」
とある。
これは、どこのことなのか。
そう、ここで、「Where」という武器を使おう。
「村で忌み嫌われていた大男のドボルザが、濡れ衣を着せられて村人たちに殺されそうになった場面のイメージがよく浮かんできました」
と、具体的な作品の場面、シーンをピックアップするのである。
この、具体的な場面や、主人公など登場人物を感想に盛り込ませられるかが、ファーストステップとしては非常に重要である。
これがあるかどうかが、意義の多い感想になるかの分水嶺でもある。
さらに合わせ技を使おう。「Why」、「何故?」である。
「~場面のイメージがよく浮かんできました。何故かというと、村人たちの口々に『怪物!』だの『村の災厄だ!』ひどい言葉を浴びせられて、これまでずっと耐え忍んできたドボルザの心が徐々に壊れていく心情の描写が旨いと思ったからです」
といった具合である。
印象的な場面を具体的に挙げて、それに対して、「何故自分はそのシーンをピックアップしたのか」ということを書いてみるのである。
◇素直になろう
基本的には、これだけで感想は十分に書ける。
ここまでの内容をまとめると、
1. 文章作法・描写がどうだったか定型的に考える
2. 具体的なシーンを挙げる
3. 具体的なシーンを挙げるに至った理由を書く
ということであり、あとは、2.~3.を繰り返してボリュームを増やしてもいいし、3.の理由を掘り下げていくのでもいい。
その際、大事にするべきは、「素直さ」である。
「なんかいいことを書こう」とか、「かっこいいことを書こう」なんて思わなくていいのである。
素直に、読んで、どう感じたか。
それが、作者にとっても気になることだし、知りたいことなのである。
◇読書感想文的にしてみる
さて次に、もう一度、前回事例を思い返してみる。
そもそもの感想は、「まぁまぁ」だったのである。しかし、今のところできあがった感想は、
「文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです。特に、村で忌み嫌われていた大男のドボルザが、濡れ衣を着せられて村人たちに殺されそうになった場面のイメージがよく浮かんできました。何故かというと、村人たちの口々に『怪物!』だの『村の災厄だ!』ひどい言葉を浴びせられて、これまでずっと耐え忍んできたドボルザの心が徐々に壊れていく心情の描写が旨いと思ったからです」
ちなみに、ここまでで195字である。
学校の宿題として400字だとしたら遠いようであるが、原稿用紙だったら感想文のタイトルと自分の名前とかもあるし、そもそも、その読んだ作品の概略を最初に書くだろうから、400字などあっという間である。
例えば、以下のような感じ。
『スティヒオの理法に支配された都』を読んだ感想
遠藤 敬之
僕が、『スティヒオの理法に支配された都』を読もうと思ったきっかけは、偶然、新着作品に表示されていたからで、深い理由はありませんでした。これまで読んだ作品の中で、特筆するほど感動したというわけではありませんが、読み進めていくうちに、展開が少々気になったことで、読み終えることができました。
この物語は、スティヒオという魔法のような力によって支配されている世界で、とある小さな村での凄惨な事件が発生してから、やがて首都をも巻き込む大きな事件に発展していくという流れで進みます。
文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです。特に、村で忌み嫌われていた大男のドボルザが、濡れ衣を着せられて村人たちに殺されそうになった場面のイメージがよく浮かんできました。何故かというと、村人たちの口々に『怪物!』だの『村の災厄だ!』ひどい言葉を浴びせられて、これまでずっと耐え忍んできたドボルザの心が徐々に壊れていく心情の描写が旨いと思ったからです。
ここまでで450字程度となる。
ただし、小説投稿サイトでは、感想自体も多くの人に読まれるだろうので、ネタバレになるような「あらすじ」は不要だろう。ただ、興味を持たれるだろう物語の流れというのは書いても差し支えないと考えられる。
◇感想と批評の違い
さて、そろそろ、目安としている3000字に近づいている。最後に、今回のサブタイトルである、「感想と批評の違い」について書いていこうと思う。
感想も、「何故」が必要だ、と書いてきた。
そうすると、批評(レビュー)との違いは難しい。
そもそも、批評や評論というのは、何か事実とされているものや、一般論だとされているものや、科学的根拠があるものと、その対象(ニュースだったり映像作品だったり文芸作品だったり色々)との「ズレ」を指摘するものである。
辞書的にそんなことが書かれているわけではない。辞書的には、「良い悪いの価値を決めること」ぐらいの意味で書いてある。
しかし、具体的にその「決める」ということをするのは、どういうことなのか。判断することである。判断とは何か? 誰かがそう思ったら、それで決めていいのか。判断といっていいのか。
テレビのワイドショーとか友人たちとの会話の中で、やれ政治家はダメだとか、最近の若者はなってないとか、老害が云々とか、大企業は傲慢だとか、そんなことをあーだこーだ言っているだけでは、批評でも評論でも何でもない。
基準となるものと「ズレ」ているからおかしい、というものでなければ、「ふーん。君はそう思うのね」とか、「そういう意見もあるね」となるだけである。
というのが、一般的な話であって、あまり重要ではない。大事なのは、小説という作品に対しての感想なり批評なりをするにあたって、感想と批評はどのように違うのか、という点である。
そもそも、多種多様な価値に基づいて紡がれる作品の世界において、科学的根拠やら、一般論やらが成り立つものなのだろうか?
(確かに、〇〇賞とか、文壇とかは、一定の基準があるだろう。それとの乖離についての指摘は、立派な批評やら評論である。ただし、今回の記事では、もっと個別具体的な僕たちの身近な小さな活動について考えたい)
◇代案が示せるか否か
私が考える感想と批評の違いは、感想は、個々人の思ったことを適切に伝えるものであるのに対して、批評はそこに加えて、「代案」を提示する点である。
「〇〇という理由で、まぁまぁでした」
ここまでが感想。
「〇〇という理由で、まぁまぁでした。▽▽という要素を加えれば、より良かったと思います」
こうなると批評。ということだ。
◇素直でよいのは変わらない
「いやいや、そんなんじゃあ、自分は批評なんてできないよ。まだ初心者なんだもの……」
という気持ちは良く分かる。僕もそうだ。自分のサイトだけではなく、他のサイトなども含め、結構な数の感想や批評を書いたと思う。そんな今でも、「こんなこと書いていいのか」「こんな風に書くと作者を怒らせないか」「的外れなこと書いて恥をかかないか」などなど、いつも思っている。
それでも。
であっても。
いやだからこそ、僕は、感想や批評を、恐れずに書いていっていいと思う。
(逆に、そういった気持ちがないままに、ただ無思慮に並べ立てた感想などは、本当にただの誹謗中傷に成り下がる場合がある)
理由その一。
講座1の冒頭で書いた通り、アウトプットしないものは、「ゼロ」だからだ。
理由その二。
的外れかどうか等々は、所詮は自分の解釈に過ぎないからだ。その何気ない指摘が、作者にとって目からうろこかもしれない。
理由その三。
絶対的基準などないからだ。これも講座1で書いたけれども、素直でよいのだ。自分を基準にして考えていいのだ。
◇まとめ
・感想も批評も「何故」の部分は大切だ
・感想と批評の違いは「代案」(こうしたらもっとよくなる)があるかないかだ
・感想や批評に絶対的基準なんてないんだから、恐れず素直に書いていい
前回、とある作品を小説投稿サイトで読んだと仮定して、
「まぁまぁだった」
↓
「文章作法は十分だし、描写も、人物や情景のイメージが想起しやすかった」
↓
「でも、特に『まぁまぁ』という感想しかでてこなかった」
といったことまでは考えた場合を想定した。
ここまでくれば、「まぁまぁだった」という感想を一言投稿するよりかは、格段に良くなっている。
「文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです」
と、「です。ます。」調にして少し自分の言葉に改編してみたらどうだろう。十分感想として成り立っているのではないだろうか。
いやいや、本記事読者のあなたが仰ることは分かる。さすがに寂しかろうと。
本記事では、これをもう少し膨らませるためにどうしたらいいかということと、感想と批評の違いについて触れていきたい。
◇5W1H
前回の記事で、感想においては、5W1Hのうち、
・何故=Why
・何が=What
・どの場面が=Where
・どのように=How
を意識することが大切だと書いた。
一方、今僕らの武器は、
「文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです」
これだけである。
文章作法が守られているかどうかは、「いる」「いない」のどちらかである。だから、膨らませることが難しい。
目をつけるべきは、描写部分である。
「人物や情景が浮かびやすかった」
とある。
これは、どこのことなのか。
そう、ここで、「Where」という武器を使おう。
「村で忌み嫌われていた大男のドボルザが、濡れ衣を着せられて村人たちに殺されそうになった場面のイメージがよく浮かんできました」
と、具体的な作品の場面、シーンをピックアップするのである。
この、具体的な場面や、主人公など登場人物を感想に盛り込ませられるかが、ファーストステップとしては非常に重要である。
これがあるかどうかが、意義の多い感想になるかの分水嶺でもある。
さらに合わせ技を使おう。「Why」、「何故?」である。
「~場面のイメージがよく浮かんできました。何故かというと、村人たちの口々に『怪物!』だの『村の災厄だ!』ひどい言葉を浴びせられて、これまでずっと耐え忍んできたドボルザの心が徐々に壊れていく心情の描写が旨いと思ったからです」
といった具合である。
印象的な場面を具体的に挙げて、それに対して、「何故自分はそのシーンをピックアップしたのか」ということを書いてみるのである。
◇素直になろう
基本的には、これだけで感想は十分に書ける。
ここまでの内容をまとめると、
1. 文章作法・描写がどうだったか定型的に考える
2. 具体的なシーンを挙げる
3. 具体的なシーンを挙げるに至った理由を書く
ということであり、あとは、2.~3.を繰り返してボリュームを増やしてもいいし、3.の理由を掘り下げていくのでもいい。
その際、大事にするべきは、「素直さ」である。
「なんかいいことを書こう」とか、「かっこいいことを書こう」なんて思わなくていいのである。
素直に、読んで、どう感じたか。
それが、作者にとっても気になることだし、知りたいことなのである。
◇読書感想文的にしてみる
さて次に、もう一度、前回事例を思い返してみる。
そもそもの感想は、「まぁまぁ」だったのである。しかし、今のところできあがった感想は、
「文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです。特に、村で忌み嫌われていた大男のドボルザが、濡れ衣を着せられて村人たちに殺されそうになった場面のイメージがよく浮かんできました。何故かというと、村人たちの口々に『怪物!』だの『村の災厄だ!』ひどい言葉を浴びせられて、これまでずっと耐え忍んできたドボルザの心が徐々に壊れていく心情の描写が旨いと思ったからです」
ちなみに、ここまでで195字である。
学校の宿題として400字だとしたら遠いようであるが、原稿用紙だったら感想文のタイトルと自分の名前とかもあるし、そもそも、その読んだ作品の概略を最初に書くだろうから、400字などあっという間である。
例えば、以下のような感じ。
『スティヒオの理法に支配された都』を読んだ感想
遠藤 敬之
僕が、『スティヒオの理法に支配された都』を読もうと思ったきっかけは、偶然、新着作品に表示されていたからで、深い理由はありませんでした。これまで読んだ作品の中で、特筆するほど感動したというわけではありませんが、読み進めていくうちに、展開が少々気になったことで、読み終えることができました。
この物語は、スティヒオという魔法のような力によって支配されている世界で、とある小さな村での凄惨な事件が発生してから、やがて首都をも巻き込む大きな事件に発展していくという流れで進みます。
文章作法はしっかり守られていて読みやすく、描写も、人物や情景が浮かびやすかったです。特に、村で忌み嫌われていた大男のドボルザが、濡れ衣を着せられて村人たちに殺されそうになった場面のイメージがよく浮かんできました。何故かというと、村人たちの口々に『怪物!』だの『村の災厄だ!』ひどい言葉を浴びせられて、これまでずっと耐え忍んできたドボルザの心が徐々に壊れていく心情の描写が旨いと思ったからです。
ここまでで450字程度となる。
ただし、小説投稿サイトでは、感想自体も多くの人に読まれるだろうので、ネタバレになるような「あらすじ」は不要だろう。ただ、興味を持たれるだろう物語の流れというのは書いても差し支えないと考えられる。
◇感想と批評の違い
さて、そろそろ、目安としている3000字に近づいている。最後に、今回のサブタイトルである、「感想と批評の違い」について書いていこうと思う。
感想も、「何故」が必要だ、と書いてきた。
そうすると、批評(レビュー)との違いは難しい。
そもそも、批評や評論というのは、何か事実とされているものや、一般論だとされているものや、科学的根拠があるものと、その対象(ニュースだったり映像作品だったり文芸作品だったり色々)との「ズレ」を指摘するものである。
辞書的にそんなことが書かれているわけではない。辞書的には、「良い悪いの価値を決めること」ぐらいの意味で書いてある。
しかし、具体的にその「決める」ということをするのは、どういうことなのか。判断することである。判断とは何か? 誰かがそう思ったら、それで決めていいのか。判断といっていいのか。
テレビのワイドショーとか友人たちとの会話の中で、やれ政治家はダメだとか、最近の若者はなってないとか、老害が云々とか、大企業は傲慢だとか、そんなことをあーだこーだ言っているだけでは、批評でも評論でも何でもない。
基準となるものと「ズレ」ているからおかしい、というものでなければ、「ふーん。君はそう思うのね」とか、「そういう意見もあるね」となるだけである。
というのが、一般的な話であって、あまり重要ではない。大事なのは、小説という作品に対しての感想なり批評なりをするにあたって、感想と批評はどのように違うのか、という点である。
そもそも、多種多様な価値に基づいて紡がれる作品の世界において、科学的根拠やら、一般論やらが成り立つものなのだろうか?
(確かに、〇〇賞とか、文壇とかは、一定の基準があるだろう。それとの乖離についての指摘は、立派な批評やら評論である。ただし、今回の記事では、もっと個別具体的な僕たちの身近な小さな活動について考えたい)
◇代案が示せるか否か
私が考える感想と批評の違いは、感想は、個々人の思ったことを適切に伝えるものであるのに対して、批評はそこに加えて、「代案」を提示する点である。
「〇〇という理由で、まぁまぁでした」
ここまでが感想。
「〇〇という理由で、まぁまぁでした。▽▽という要素を加えれば、より良かったと思います」
こうなると批評。ということだ。
◇素直でよいのは変わらない
「いやいや、そんなんじゃあ、自分は批評なんてできないよ。まだ初心者なんだもの……」
という気持ちは良く分かる。僕もそうだ。自分のサイトだけではなく、他のサイトなども含め、結構な数の感想や批評を書いたと思う。そんな今でも、「こんなこと書いていいのか」「こんな風に書くと作者を怒らせないか」「的外れなこと書いて恥をかかないか」などなど、いつも思っている。
それでも。
であっても。
いやだからこそ、僕は、感想や批評を、恐れずに書いていっていいと思う。
(逆に、そういった気持ちがないままに、ただ無思慮に並べ立てた感想などは、本当にただの誹謗中傷に成り下がる場合がある)
理由その一。
講座1の冒頭で書いた通り、アウトプットしないものは、「ゼロ」だからだ。
理由その二。
的外れかどうか等々は、所詮は自分の解釈に過ぎないからだ。その何気ない指摘が、作者にとって目からうろこかもしれない。
理由その三。
絶対的基準などないからだ。これも講座1で書いたけれども、素直でよいのだ。自分を基準にして考えていいのだ。
◇まとめ
・感想も批評も「何故」の部分は大切だ
・感想と批評の違いは「代案」(こうしたらもっとよくなる)があるかないかだ
・感想や批評に絶対的基準なんてないんだから、恐れず素直に書いていい
後書き
◆次回予告
今回は感想と批評の違いまでしか書けませんでしたので、次はもう少し具体的に、どうやったら批評(=代案を示すこと)ができるのかを考えていきたいと思います。
| 作者:遠藤 敬之 |
| 投稿日:2018/11/07 20:47 更新日:2018/11/07 20:47 『感想批評の書き方講座』の著作権は、すべて作者 遠藤 敬之様に属します。 |
| 前の話 | 目次 | 次の話 |
読了ボタン

 小説鍛錬室
小説鍛錬室