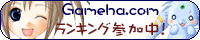作品ID:2051
あなたの読了ステータス
(読了ボタン正常)一般ユーザと認識
「感想批評の書き方講座」を読み始めました。
読了ステータス(人数)
読了(81)・読中(1)・読止(0)・一般PV数(332)
読了した住民(一般ユーザは含まれません)
感想批評の書き方講座
小説の属性:随筆・コラム / 未選択 / お気軽感想希望 / 初投稿・初心者 / 年齢制限なし / 連載中
前書き・紹介
【前回の復習】
前回の講座では、批評するときには、3つの観点(ストーリー・描写・ウィット)に着目しましょうと書きました。もちろんそれ以外の観点もあるのですが、いきなり多くを感想や批評に詰め込もうとしても大変ですので、初めは3つに絞って考えるのがよいと思います。
今回の講座では、その観点も含めて、もう少し具体的に感想や批評を書くための方法を考えていきたいと思います。具体的には、学校のワークシートのようですが、定型文――テンプレートについて提示したいと思います。
4:定型文を考える
| 前の話 | 目次 | 次の話 |
◇感想・批評のテンプレート
精神論が分かったとしても、実践が伴わない理論は机上の空論だ。
世の中には、「〇〇をしただけで-20kg」とか、「〇〇サプリで腹筋ばっきばき」などという広告が満ち溢れている。
時代の変化はめまぐるしい。科学技術の進歩も飛躍的だ。車の完全自動運転の普及だって目前だ。だから、画期的な一瞬で自分を変えてくれるような何かだって存在するはずだ。
しない。
「道具」は変わる。お金だって、宝くじに当たれば、一瞬で手に入るかもしれない。
しかし、「自分」はすぐには変わらない。すぐさま言っておかなければいけないが、「変えられない」のではない。変えられる。人は成長できる。考え方や価値観だって変わる。
だが、「すぐに」ではない。
世間では、若いうちは成長も早いといわれるかもしれない。確かに、年齢的に若ければ、変化の速度は大きいかもしれない。それでも、「すぐに」ではないのだ。赤ん坊が歩けるようになるというのはすごい変化かもしれないが、それでも1年ぐらいは必要なのだ。それも、ただ単に泣いていて突然変異するわけではない。バランス感覚や反射神経を試行錯誤して身体に覚えさせて、ようやく、歩けるようになるのだ。
夢も希望もなく、つまらないことを書いているかもしれないが、要するに、「継続は力なり」ということと、「実践あるのみ」ということだ。本講座の意義を自ら貶めるようなことを書くけれども、これを読んだからといって、感想や批評が「すぐに」自由に楽に書けるようになるなんてことはない。
少しずつでいい。一か月に1つとか、140字でとか、小さな目標でも決めて、実践して頂きたいと思う。
(すぐさま書いておかなければいけないのは、「継続は力なり」というのは重要なスローガンである一方で、その「継続する」ということ自体も、一つの才能であり、努力が必要なことである。逆に、「好きなもの」は続けることもそれほど億劫ではない。ということは、「続ける」ということについても、この「好き」というのを上手く活用する方法があるのではないか、ということだけれども、本講座と全然関係ないので、これらはいずれ機会があれば書きたい)
◇感想・批評の定型文
前置きが長くなったけれども、今回は、感想や批評を「実践する」上で参考にするための、定型文(テンプレート)について提示することとしたい。是非、何か対象の作品を決めて、ワークシートのように活用して頂けたら嬉しい。
大きく、項目出しを先にすると、以下のとおり。
1.作者への挨拶(作者名・作品タイトルを含める)
2.概要(率直な印象、ファーストインプレッション)
3.具体的な感想(場面→感想→理由)
4.批評(場面→感想→理由)
5.結び(お礼の挨拶・今後の期待)
最初に例として、昔に読んだ『いちご同盟』という小説作品をテンプレートに当てはめてみて、そのあと、各項目の説明を試みたい。
(例)
1.【作者への挨拶】三田さんこんにちは。『いちご同盟』読ませていただきました。
2.【概要】時間を忘れて読んでいました。面白かったです。冒頭、野球部エースで4番の羽根木くんが、いきなりやってきて野球の試合を撮ってくれと主人公に頼むわけですが、随分強引な奴だなと思いました。しかし、「命がかかっている」という真剣な物言いに、どういうことなのかと自然に引き込まれていったのでした。
3.【感想】印象に残った場面は複数ありますが、一つ挙げると、中学一年のときに一緒にいじめられて、やがて不登校になってしまった同級生と、不意に出会うシーンです。いじめられていた頃とは変わって、ぎらぎらした目つきになっていた彼に、バイクに乗らないかと誘われます。危ないんじゃないかと心配する主人公に彼は、「命なんか惜しくないさ」と言います。その言葉に対しての主人公の感じ方、思いといったものが、物語の序盤から大きく変化していることが、主人公の率直な言葉(心理描写)から伝わってきました。
4.【批評】逆に、気になった点は、その不登校になった同級生と会ってからの急展開です。上に書いたように、主人公の変化を表現するためには、まさにそのタイミングで、同級生と出会う必要があったと感じますが、「あんなこと」になるのが、少し予定調和に思われました。強烈な印象は下がってしまうと思いますが、時系列として、数日後の出来事だったとしたり、「あんなこと」が、その同級生に起こったことでなくしてもよかったのではないかと思いました。
5.【結び】『いちご同盟』という作品タイトルから、食べ物の「苺」が浮かんだわけですが、読み終わってみると、「15歳」という意味なんだと分かりました。三田さんは他にも作品を書かれているようなので、そちらも読ませて頂こうと思います。それでは、ご執筆ありがとうございました。
以上、例。では次に、各項目の内容を見ていこう。
◇◇作者への挨拶
挨拶――必ずしも必要ではないと思うが、感想や批評を書く際にも、まずは「相手がいる」ということの意識は重要だ。顔の見えない投稿サイトが多いが、それ故に、年齢も立場も関係なくフラットで意見を交わせられるのがインターネットのよいところの一つだ。とはいえ、それ故に、お互いの常識や前提も異なっているのが当たり前なので、まずは、画面の先にいるのも同じ人なのだと、念頭に置いておこう。
なので、別に難しいことを書く必要はない。上の例でも書いた通り、「〇〇さんこんにちは。作品読ませていただきました」といった程度でまずはよいだろう。応用で、「お久しぶりです」とか、「以前から〇〇さんの作品は読んでいましたが……」とか、いろいろ状況に応じて変えていければと思う。
また、作品タイトルも、作品の重要な一部だ。読み終わってから改めてタイトルを読むと、その新しい意味に気づくかもしれない。
◇◇概要
次に「概要」ということだが、その作品について、率直な印象を書く。ファーストインプレッション。ここは、良いところでも、悪いところでもよい。とにかく率直に、素直に。これを誤魔化してしまうと、良いことを書いても「迎合」「馴れ合い」のようになり、批評(代案)を目的にしても「誹謗中傷」になってしまう可能性がある。
◇◇具体的な感想部分
・場面
・その場面に対しての感想
・その感想が生じた理由
と分解して考えるといい。
留意したいのが、ここでは、特に良かった点を書くとよい。
◇◇批評部分
感想と同様に、
・場面
・その場面に対して気になった点
・気になった理由
と分解して考えるといい。感想を書くだけならこれは特に不要だ。
◇◇結び
作者へのお礼など。連載作品へなら、「続きも期待しています」とか、完結作品へなら、「次回作も読みたいです」とか。絶対必要ではないだろう。ただ、「以上です」という結びがないと、「終わったのか終わってないのか」がよくわからない場合があるから、簡単にでも結びの言葉はあったほうがよいと思う。
◇作者の希望に合わせて書く
思ったよりも長くなってしまった。
定型文の各項目の解説と説明も端折って書いてしまったので、次回にもう少し補足したいと思うが、本講座の残りは、そもそも感想や批評を、どのように使い分けて書いていこうか、ということを考えみようと思う。
小説投稿サイト『創作は力なり』では、どの作品も、それぞれ感想または批評希望の選択が必要である。それぞれの項目については、今後触れていきたいが、大きく、「感想希望」と「批評希望」の違いについて書いていきたい。
今回提案したテンプレートは、5つのパーツに分かれている。
挨拶、概要、感想、批評、結び――であるが、作者の希望に応じて、「感想」部分を多めにするのか、「批評」部分を多めにするのかを考えていけたらよりよくなると思う。
前回の講座では、
「〇〇という理由で、まぁまぁでした」
ここまでが感想。
「〇〇という理由で、まぁまぁでした。▽▽という要素を加えれば、より良かったと思います」
こうなると批評、ということを書いた。
そうすると、感想も批評も、それぞれ重複した部分があるのではないか、と思われるだろう。
本来、感想というと、「思ったこと」なのであって、そこに、良いも悪いも普通も、価値基準はないのである。「面白くなかった」という感想だってあってしかるべきだ。
ただし、敢えて面白くなかったという感想を書くべきなのか、ということは一度考えてみたい。
感想も批評も、どちらも「理由」は重要だと、本講座の最初の方でも書いた。
感想であっても理由がないと、作者にとっても、自分にとっても役に立たないのだ。
しかし、面白くなかった理由とは何だろうか?
例えば、学園ドラマに全く興味を持てない人が、そのジャンルを読んで「面白くなかった」と感じるのは当たり前であって、その理由は、「自分には合わない」からだろう。もちろんそこで、「何故自分は学園ドラマが好きではないのか。――なるほどもしかして、自分の青春時代と比べてリアリティがあまりにも感じられないからなのかもしれない。だったら、『友達いらない同盟』という作品は、普通の学園ドラマとはちょっと違うかもしれないから読んでみる価値はあるかもしれない」――とか、そこまで自己考察するのであれば、意味はあるかもしれない。
しかし残念ながら、それと、いざ感想を書こうとする対象作品とは、まったく関係ない。「自分は、学園モノが好みでないので、貴方の作品も面白くありませんでした」というのは、「面白くなかった」理由はあるけれども、「え……じゃあ何で読んだの」と疑問が疑問を呼ぶ(ただ単に、八つ当たりとかいちゃもんをつけたかっただけではないかと)。
であるがゆえに、感想を書く際には、できるだけ良かった点を書いた方がよいだろう。
◇まとめ
・感想&批評の定型文は5つのパーツ。挨拶、概要、感想、批評、結び、だ。
・作者が感想希望なのか批評希望なのか見極めよう。感想希望の場合は「良かった点」を中心にする。
精神論が分かったとしても、実践が伴わない理論は机上の空論だ。
世の中には、「〇〇をしただけで-20kg」とか、「〇〇サプリで腹筋ばっきばき」などという広告が満ち溢れている。
時代の変化はめまぐるしい。科学技術の進歩も飛躍的だ。車の完全自動運転の普及だって目前だ。だから、画期的な一瞬で自分を変えてくれるような何かだって存在するはずだ。
しない。
「道具」は変わる。お金だって、宝くじに当たれば、一瞬で手に入るかもしれない。
しかし、「自分」はすぐには変わらない。すぐさま言っておかなければいけないが、「変えられない」のではない。変えられる。人は成長できる。考え方や価値観だって変わる。
だが、「すぐに」ではない。
世間では、若いうちは成長も早いといわれるかもしれない。確かに、年齢的に若ければ、変化の速度は大きいかもしれない。それでも、「すぐに」ではないのだ。赤ん坊が歩けるようになるというのはすごい変化かもしれないが、それでも1年ぐらいは必要なのだ。それも、ただ単に泣いていて突然変異するわけではない。バランス感覚や反射神経を試行錯誤して身体に覚えさせて、ようやく、歩けるようになるのだ。
夢も希望もなく、つまらないことを書いているかもしれないが、要するに、「継続は力なり」ということと、「実践あるのみ」ということだ。本講座の意義を自ら貶めるようなことを書くけれども、これを読んだからといって、感想や批評が「すぐに」自由に楽に書けるようになるなんてことはない。
少しずつでいい。一か月に1つとか、140字でとか、小さな目標でも決めて、実践して頂きたいと思う。
(すぐさま書いておかなければいけないのは、「継続は力なり」というのは重要なスローガンである一方で、その「継続する」ということ自体も、一つの才能であり、努力が必要なことである。逆に、「好きなもの」は続けることもそれほど億劫ではない。ということは、「続ける」ということについても、この「好き」というのを上手く活用する方法があるのではないか、ということだけれども、本講座と全然関係ないので、これらはいずれ機会があれば書きたい)
◇感想・批評の定型文
前置きが長くなったけれども、今回は、感想や批評を「実践する」上で参考にするための、定型文(テンプレート)について提示することとしたい。是非、何か対象の作品を決めて、ワークシートのように活用して頂けたら嬉しい。
大きく、項目出しを先にすると、以下のとおり。
1.作者への挨拶(作者名・作品タイトルを含める)
2.概要(率直な印象、ファーストインプレッション)
3.具体的な感想(場面→感想→理由)
4.批評(場面→感想→理由)
5.結び(お礼の挨拶・今後の期待)
最初に例として、昔に読んだ『いちご同盟』という小説作品をテンプレートに当てはめてみて、そのあと、各項目の説明を試みたい。
(例)
1.【作者への挨拶】三田さんこんにちは。『いちご同盟』読ませていただきました。
2.【概要】時間を忘れて読んでいました。面白かったです。冒頭、野球部エースで4番の羽根木くんが、いきなりやってきて野球の試合を撮ってくれと主人公に頼むわけですが、随分強引な奴だなと思いました。しかし、「命がかかっている」という真剣な物言いに、どういうことなのかと自然に引き込まれていったのでした。
3.【感想】印象に残った場面は複数ありますが、一つ挙げると、中学一年のときに一緒にいじめられて、やがて不登校になってしまった同級生と、不意に出会うシーンです。いじめられていた頃とは変わって、ぎらぎらした目つきになっていた彼に、バイクに乗らないかと誘われます。危ないんじゃないかと心配する主人公に彼は、「命なんか惜しくないさ」と言います。その言葉に対しての主人公の感じ方、思いといったものが、物語の序盤から大きく変化していることが、主人公の率直な言葉(心理描写)から伝わってきました。
4.【批評】逆に、気になった点は、その不登校になった同級生と会ってからの急展開です。上に書いたように、主人公の変化を表現するためには、まさにそのタイミングで、同級生と出会う必要があったと感じますが、「あんなこと」になるのが、少し予定調和に思われました。強烈な印象は下がってしまうと思いますが、時系列として、数日後の出来事だったとしたり、「あんなこと」が、その同級生に起こったことでなくしてもよかったのではないかと思いました。
5.【結び】『いちご同盟』という作品タイトルから、食べ物の「苺」が浮かんだわけですが、読み終わってみると、「15歳」という意味なんだと分かりました。三田さんは他にも作品を書かれているようなので、そちらも読ませて頂こうと思います。それでは、ご執筆ありがとうございました。
以上、例。では次に、各項目の内容を見ていこう。
◇◇作者への挨拶
挨拶――必ずしも必要ではないと思うが、感想や批評を書く際にも、まずは「相手がいる」ということの意識は重要だ。顔の見えない投稿サイトが多いが、それ故に、年齢も立場も関係なくフラットで意見を交わせられるのがインターネットのよいところの一つだ。とはいえ、それ故に、お互いの常識や前提も異なっているのが当たり前なので、まずは、画面の先にいるのも同じ人なのだと、念頭に置いておこう。
なので、別に難しいことを書く必要はない。上の例でも書いた通り、「〇〇さんこんにちは。作品読ませていただきました」といった程度でまずはよいだろう。応用で、「お久しぶりです」とか、「以前から〇〇さんの作品は読んでいましたが……」とか、いろいろ状況に応じて変えていければと思う。
また、作品タイトルも、作品の重要な一部だ。読み終わってから改めてタイトルを読むと、その新しい意味に気づくかもしれない。
◇◇概要
次に「概要」ということだが、その作品について、率直な印象を書く。ファーストインプレッション。ここは、良いところでも、悪いところでもよい。とにかく率直に、素直に。これを誤魔化してしまうと、良いことを書いても「迎合」「馴れ合い」のようになり、批評(代案)を目的にしても「誹謗中傷」になってしまう可能性がある。
◇◇具体的な感想部分
・場面
・その場面に対しての感想
・その感想が生じた理由
と分解して考えるといい。
留意したいのが、ここでは、特に良かった点を書くとよい。
◇◇批評部分
感想と同様に、
・場面
・その場面に対して気になった点
・気になった理由
と分解して考えるといい。感想を書くだけならこれは特に不要だ。
◇◇結び
作者へのお礼など。連載作品へなら、「続きも期待しています」とか、完結作品へなら、「次回作も読みたいです」とか。絶対必要ではないだろう。ただ、「以上です」という結びがないと、「終わったのか終わってないのか」がよくわからない場合があるから、簡単にでも結びの言葉はあったほうがよいと思う。
◇作者の希望に合わせて書く
思ったよりも長くなってしまった。
定型文の各項目の解説と説明も端折って書いてしまったので、次回にもう少し補足したいと思うが、本講座の残りは、そもそも感想や批評を、どのように使い分けて書いていこうか、ということを考えみようと思う。
小説投稿サイト『創作は力なり』では、どの作品も、それぞれ感想または批評希望の選択が必要である。それぞれの項目については、今後触れていきたいが、大きく、「感想希望」と「批評希望」の違いについて書いていきたい。
今回提案したテンプレートは、5つのパーツに分かれている。
挨拶、概要、感想、批評、結び――であるが、作者の希望に応じて、「感想」部分を多めにするのか、「批評」部分を多めにするのかを考えていけたらよりよくなると思う。
前回の講座では、
「〇〇という理由で、まぁまぁでした」
ここまでが感想。
「〇〇という理由で、まぁまぁでした。▽▽という要素を加えれば、より良かったと思います」
こうなると批評、ということを書いた。
そうすると、感想も批評も、それぞれ重複した部分があるのではないか、と思われるだろう。
本来、感想というと、「思ったこと」なのであって、そこに、良いも悪いも普通も、価値基準はないのである。「面白くなかった」という感想だってあってしかるべきだ。
ただし、敢えて面白くなかったという感想を書くべきなのか、ということは一度考えてみたい。
感想も批評も、どちらも「理由」は重要だと、本講座の最初の方でも書いた。
感想であっても理由がないと、作者にとっても、自分にとっても役に立たないのだ。
しかし、面白くなかった理由とは何だろうか?
例えば、学園ドラマに全く興味を持てない人が、そのジャンルを読んで「面白くなかった」と感じるのは当たり前であって、その理由は、「自分には合わない」からだろう。もちろんそこで、「何故自分は学園ドラマが好きではないのか。――なるほどもしかして、自分の青春時代と比べてリアリティがあまりにも感じられないからなのかもしれない。だったら、『友達いらない同盟』という作品は、普通の学園ドラマとはちょっと違うかもしれないから読んでみる価値はあるかもしれない」――とか、そこまで自己考察するのであれば、意味はあるかもしれない。
しかし残念ながら、それと、いざ感想を書こうとする対象作品とは、まったく関係ない。「自分は、学園モノが好みでないので、貴方の作品も面白くありませんでした」というのは、「面白くなかった」理由はあるけれども、「え……じゃあ何で読んだの」と疑問が疑問を呼ぶ(ただ単に、八つ当たりとかいちゃもんをつけたかっただけではないかと)。
であるがゆえに、感想を書く際には、できるだけ良かった点を書いた方がよいだろう。
◇まとめ
・感想&批評の定型文は5つのパーツ。挨拶、概要、感想、批評、結び、だ。
・作者が感想希望なのか批評希望なのか見極めよう。感想希望の場合は「良かった点」を中心にする。
後書き
◆次回予告
当初、定型文の項目を挙げて解説するというだけを考えていましたが、「前置き」的なことを書いていたら思いのほか長くなってしまいました。そのせいでメインの定型文に関しての説明が少し足りていない気がしますので、次回はその補足をしていきたいと思います。また、「感想希望」か、「批評希望」か、という点は、実はとても重要で、今回の講座を書こうと思ったきっかけの一つでもありました。この辺りも、今後もう少し触れていきたいと思っています。
| 作者:遠藤 敬之 |
| 投稿日:2018/11/15 12:06 更新日:2018/11/15 15:12 『感想批評の書き方講座』の著作権は、すべて作者 遠藤 敬之様に属します。 |
| 前の話 | 目次 | 次の話 |
読了ボタン

 小説鍛錬室
小説鍛錬室