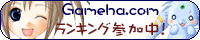あなたの読了ステータス
(読了ボタン正常)一般ユーザと認識
「感想批評の書き方講座」を読み始めました。
読了ステータス(人数)
読了(79)・読中(1)・読止(0)・一般PV数(292)
読了した住民(一般ユーザは含まれません)
感想批評の書き方講座
小説の属性:随筆・コラム / 未選択 / お気軽感想希望 / 初投稿・初心者 / 年齢制限なし / 連載中
前書き・紹介
【前回の復習】
前回、感想&批評の定型文は、挨拶、概要、感想、批評、結びの、5つのパーツに分けられると書きました。今回は、それをもう少し膨らませたり、補足を中心に書いていきたいと思います。
あと、本講座は、簡潔に伝えたいという意図から、「である。」調にすることにしています。上から目線に感じられるかもしれませんが、「こういった考え方もあるのではないか」という思いで書いていますので、そのあたりは、皆さんの脳内変換でお願いいたします。では以下本文。
5:定型文を考える2
| 前の話 | 目次 |
この部分については、前回も割と詳しく書いたと思う。
シンプルにいくならば、「〇〇さんこんにちは」だけで十分だ。
ただ、大事なことは、前回も書いた通り、「相手がいる」という意識をもつことだ。ロボット、A.I.相手に書いているわけではないのだ。
また、無理に凝ったことを書く必要もない。ユーチューブやニコニコ動画などの実況動画では、「おはようございます、こんにちは、こんばんは! どーも▲▲に最近はまっている〇〇ですッ!」とか言ったりしているが、自分のキャラクターと異なるようであれば無理する必要はまったくなかろう。
ただ、何度も何度も書いていると、不思議と文章には、自分のキャラクターが反映されてくるものである。この講座も、今回で5回目であるが、「なんだか回りくどいような面倒くさいような文章を書くやつだなぁ」と思われた方もいるはずだ。自分ではあまりそういう気はないのだが、そんな風に言われることもあるから、まぁそうなんだろうなと思っている。――と、自分語りはどうでもよいのだが、要するに、無理して面白い挨拶をしようとか考えなくても、継続して感想……というか文章を素直に書いていると、特徴が自然と反映されるものだということである。
◇概要
次に概要だ。
概要という言葉は、「要点」とか「さわり」といった意味合いであるが、ここでも、前回までに何度か書いている通り、「素直さ」は忘れないようにしたい。
具体的には、一つの例ではあるが、まず「二分法的思考」を試みてみよう。
要するに、「面白かったか」「面白くなかったか」。
面白いという感覚が自分の中にしっくりこないようであれば、「最後まで読めたか」「読めなかったか」でもいい。
面白かった場合や、最後まで一気に読めた場合は、あまり考えなくてもよいだろう。
「面白かったです! 最後までハラハラドキドキ読んでいきました!」
といった感想でも、概要部分としては十分である。
だが問題は、あまり自分には響かなかった場合である。
その時、「面白くなかった」とか「最後まで読めなかった」といったことを率直にアウトプットしてしまうのはよくない。もちろん、相手と自分との信頼関係ができているのなら別の場合もあるが(それでも、言葉は時に、古の鍛冶師により鍛えられた業物のように鋭い)、マイナスの印象を与える言葉をそのまま使うのは賢い方法とはいえない。
あまり例としてよくないが、裁判の判決は、重い刑ほど、結論が後に来ることが多いのだという。理由が先ということだ。
面白くなかったり、最後まで興味を尽かさず読めなかった理由を考えてみよう。
・文章表現が十分でなかった(文章作法が守られていなかったり、表現が稚拙、またはわかりにくいなど)
・内容が難解すぎて理解できなかった(理解する気になれなかった)
・そもそも内容・テーマが好みではなさそうだった
理由はそれぞれあるはずだ。残念だが、事実、面白くなかったのだ。そして面白くなかったということは、その作品は自分には合わなかったということだ。……であれば、「〇〇という理由で、自分には合いませんでした(難しすぎました)」といった書き方が望ましいだろう。もちろん、もっと自分にあった言葉で、まろやかにできればなお良いだろう。
◇感想
概要を書いたところで、感想の本題に入る(ちなみに、一言感想希望等であれば、概要部分のみでも十分だろう)。
さて前回、
・場面
・その場面に対しての感想
・その感想が生じた理由
に分解して考えるのがよいと書いた。
どんな作品でも、読んだからには、絶対に、必ず、間違いなく、印象に残った場面があるのである。
良い印象だろうが、悪い印象だろうが、何の印象も残らなかった作品というのはありえない。――逆に、あったとしたら、それが一番強い印象だ(皮肉のようだが、逆説的に事実である)。
◇◇場面
であるからにして、その印象に残った場面というのを、一つか二つか、まずは書き出してみよう。
大事なことを書いた。
書き出してみよう。
ここで、頭の中で浮かんだ状態にしていては、手が完全にストップしてしまう。
しゃべりながら考える――ということもあるように、書きながら考えがまとまっていくということも、実際にある。まぁ逆に、「すごいの思いついた!」と思って書き出してみたら、大したアイデアではなかった、ということもあるのだが。
それはそうと、感想や批評を書くにあたって、「すごいの書いてやる!」なんて思わなくてよい。批判を恐れず書けば、間違ったことを書いたって構わないじゃないかと思う。――もちろんすぐさま書いておかなければならないのは、間違わないようにすることは大事だ。しかし、「感想」なのである。自分の中で生じたことのアウトプットなのだ。そこに、間違いも正しいも、本来ないはずではないか。
なお、具体的に書き出す際に、もちろん、その作品をもう一度読んでみたってよい。精読せずとも、流し読みだって斜め読みだって飛ばし読みだってよい。読んでいるうちに、印象的な場面が浮かんでくるはずだ。
そうしたら、今度は間髪入れずに書き出してみる。
◇◇感想・理由
場面を書き出したら、それに対しての感想を書いていく。
前に自分が実際に書いた感想を少し編集しつつ引用してみようと思う。
【場面】主人公が最初にそのゲームを始めた瞬間から引き込まれました。
【引用】(実際の作品の一部を引用。あまり長くならないように、必要最低限にする。どれぐらいを引用すべきかというあたりも、今後触れられたらよいと思う)
【感想】上の場面の、小気味の良い疾走感あふれる描写が、「パソコンの前に座る私>作者さんの小説>主人公自身(主人公がプレイしている情景)>ゲームの世界」と、私の目の前の世界を一気に変えてくれたようでした。
以上例。
今回の例では、感想と理由がほぼ一緒になって書いているが、それで構わない。テンプレートに沿うために、必ずしも無理に分解して書こうとしなくてもよいのだ。思ったこと(=感想)を書いてみて、それを一度読み返したときに、「理由」がなさそうなら補足するといったやりかたでもよいと思う。
◇批評
批評の部分については、基本的には感想と同様に書いていく。感想と批評の違いについては、「こうしたらもっと良くなるんじゃないか」といった視点であった。なので、
・場面を書き出す
・その場面に対して気になった点と、その気になった理由を書く
といった流れで良いだろう。
◇結び
いきなりだが、「結び」は、なくてもよいと思う。
ただ、それほど負担と思わずに、実際それほど負担でもないし、あった方が感想&批評にまとまり(しまり)も出てよいと思うので、できるだけ書くようにしてはどうだろうか。
・読ませていただきありがとうございました
・これからも頑張ってください
・楽しい時間を過ごせました
・続きも楽しみにしてます
・拙い感想でしたが何かの参考になれば幸いです
・短いですが以上です
このように、一文程度でも構わないと思う。
◇まとめ
今回に関しては、特に「まとめ」といったものはない。
敢えて考えるならば、挨拶、概要、感想、批評、結びの、5つのパーツの優先度だろうか。
意外だろうし、反論も多い気がするが、個人的には、「挨拶」or「概要」>「感想」or「批評」>「結び」だと思っている。
「え、感想批評講座なのに、メインの『感想・批評』じゃなくて『挨拶』が大事なの??」
と思われるかもしれないが、第一印象、ファーストインプレッションは重要である。
「胡散臭い笑顔」というのはあると思うが、そうはいっても、不機嫌そうな人よりも笑顔の人のほうが何となく話しかけやすいだろう。
感想を書く場合でも、いきなりケンカ調であったら、その内容がいかに素晴らしくて理にかなっていたとしても、素直に受け取ってもらえるかどうかは怪しい。
とはいえ、それほど身構えて考える必要もない。
慇懃無礼にならない程度に、丁寧に書こうという気持ちがあれば十分だ。
とはいえ、そのために気を付けた方がよいこともいくつかあるため、次回はその辺りに触れていけたらと思う。
後書き
◆次回予告
前回から引き続き、定型文(テンプレート)を用いての、具体的な感想等の書き方について書かせていただきました。ただし、あくまでも今回の定型文は一例です。何度か書いていくうちに、自分流を身に着けていくのも楽しいことだと思います。
また、必ずしも、「挨拶」「概要」「感想」「批評」「結び」の5つのパーツが必要ということでもないと思います。気心知れた相手なら、「小面倒なことはどうでもいいから、さっさと結論をよこせ!」といわれるかもしれません。ただ、インターネット上(投稿サイト等)では、様々な人が同時に、そうした感想等を見て読んでいる可能性があると、注意する必要はあるでしょう。
さて次回は、本文中も少し触れましたが、できるだけ自分の思いを正確に・丁寧に伝えるにはどうしたらよいかを考えていきたいと思います。
| 作者:遠藤 敬之 |
| 投稿日:2018/11/28 23:18 更新日:2018/11/29 07:34 『感想批評の書き方講座』の著作権は、すべて作者 遠藤 敬之様に属します。 |
| 前の話 | 目次 |
読了ボタン

 小説鍛錬室
小説鍛錬室