 Technique ~早く強くなりたい人のための中級者テク・上級者テク~
Technique ~早く強くなりたい人のための中級者テク・上級者テク~戦闘がうまくこなせない、防衛がうまくこなせない。そういった悩みを解消するための場所です。
→早く強くなりたい人のための中級者テク
●軍操作と当て方について
・基本編
・大砲破壊編(騎兵包囲)
・大砲破壊編(スカミの千鳥モード)
●ホットキー配置のススメ 
●カバーモード 
●探索者逃走法
●肉撃ちキャンセル
●壁によるTC防御
●カウンター法
●探索法
●TC周囲の荒しについて
●操船技術
●搬送点移動先変更カウンター法・TC軍搬送点集合地点指定
●壁の張り方(常に最大の長さで)
軍操作と当て方について
・通常編
理想的な軍操作をこちらに書いておきます。(赤色は全て敵。)
まず、基本的な戦闘を簡単に説明します。テクニックは後ほど。
馬+軽歩兵 vs 重歩兵+軽歩兵
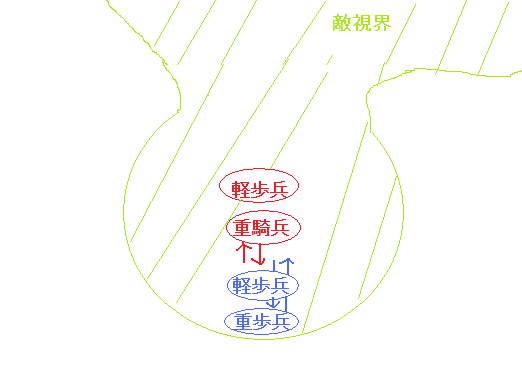
基本的に重歩兵側のほうが操作量は少ないですが、
実に槍の操作がシビアになってきます。
重歩兵はできるだけ前に出さないようにして、軽歩兵で上手く戦っていかないと、
最悪全滅してしまうということもあり得ます。
同様にして、よくある編成と当たり方として、軽歩兵+重騎兵 vs 軽歩兵+重騎兵
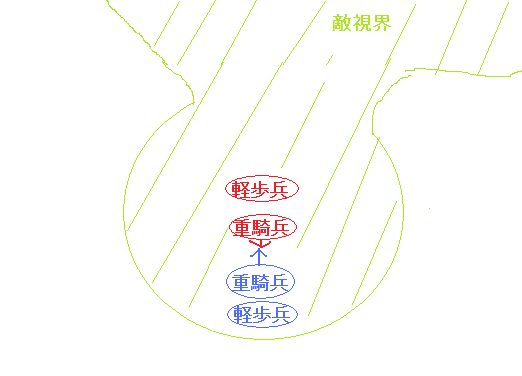
これは、重騎兵の数が勝っている側が勝ちます。
さて、ここに重歩兵が入ればどうなるでしょうか。
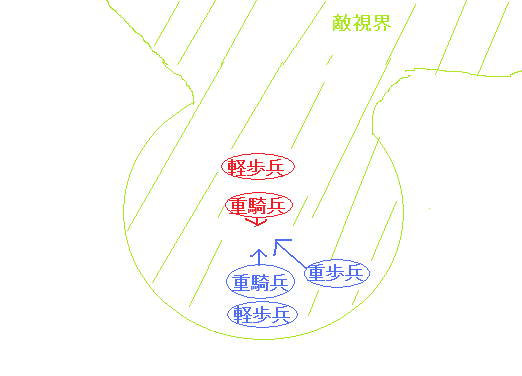
実は、ここの操作のときに一つテクニックがあって、
重騎兵と重歩兵を同時に前進させると、とても美味しいときがあります。
このとき、騎兵が退かざるを得なくなるわけですが、
騎兵が退くと軽歩兵が遅れがちになって追いつかれてしまいます。
だからと言って騎兵を上げると、全滅は免れなくなってしまう。
ここがミソなのです。
ちなみに、重歩兵も遅れがちになりますが、
騎兵が重歩兵より多い場合、離れがちの重歩兵を選択しながら騎兵を選択し、
移動させる(つまり、少し離れた重歩兵と一緒にドラッグ操作)と
隊列形成移動で後ろの重歩兵が走ってくれます。
これによって、重歩兵が一時的に騎兵並の速度で走ることができます。
次に、この当て方はtakuman氏の日記からの受け売りですが、
(takuman氏の日記に詳しい当て方が載っています)
以下のような戦い方があります。
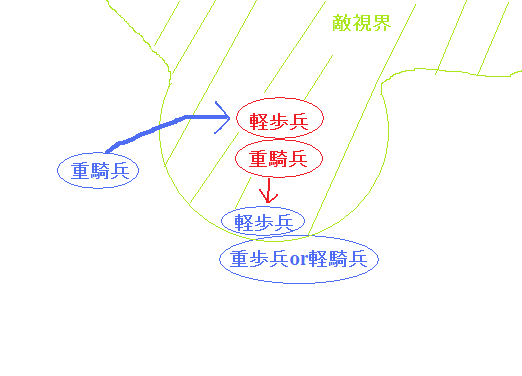
基本的に重騎兵は一直線に歩兵に当てたいものですが、
目の前から突撃すると、実に苦しい戦いになることがしばしばあります。
基本的に、重騎兵は機動力が高いので、できるならば
横から、あるいは後ろから当てたいものです。
さらに、この発展形として(takuman氏の日記にある兵の当て方がソースです)、
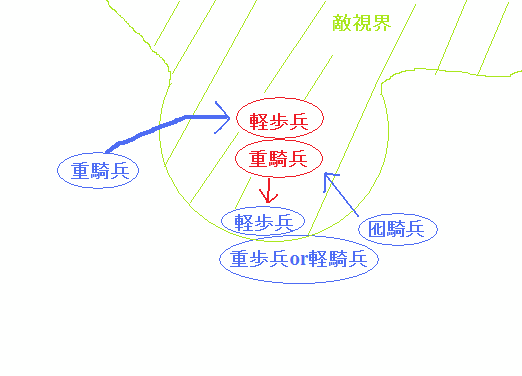
囮の重騎兵を使って、重騎兵及び重歩兵をひきつけ、
さらに重騎兵本隊で畳み掛けるという戦略です。
この戦略はチーム戦でも活用することが出来ます。
・大砲破壊編(騎兵包囲)
さて、皆さんはがっちがちに防衛された大砲に苦戦したことはありませんか?
お互い大砲が出ていればいいのですが、大砲で一方的に攻撃されそうなときや
文明的にファルコネット2カードを持っていない文明は、
早期のファルコネットに非常に苦戦します。私もよく苦しい思いをさせられます。
突撃してファルコネットを破壊することが出来ればいいのですが、
非常にリスキーで、最悪の場合全騎兵を失って為す術なしという状況にもなり得ます。
そこで私が提案したいのが、包囲する形で大砲を破壊する戦法です。
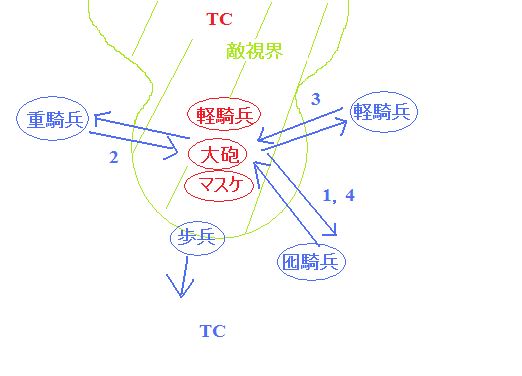
基本的に、カード大砲を用いた戦法や大砲を要にした戦法を用いると、
大砲を守るためのユニットが必要になります。
つまり、上のような対馬を揃えた大砲防衛軍が主な編成になるわけです。
こうなると、上級者であれば大砲を壊させてくれなくなってしまいます。
こちらが大砲カードを持っていない、あるいは生産できない状況だと
この大砲を破壊するのは難しくなってきます。
ではどうすればいいか・・・
それは相手以上の軍操作で圧倒することが鍵になります。
上の図のように、歩兵は大砲の餌食なので用いません。
騎兵のみで突撃する形になります。
理想の編成としては、
囮重騎兵(3~5、多くて8騎)、
本隊の重騎兵(5~、できれば10騎以上)、
軽騎兵(10騎以上、黒騎兵なら尚よし)、
軽騎兵が少なければ、軽騎兵を運用するのはあまり効果がありません。
しかし、囮と本隊のみでも十分効果があります。
具体的な操作としては、まず囮騎兵が突撃したと見せかけて、対馬を釣ります。
それより1秒~2秒遅れて本隊の重騎兵を送り込みます。できれば着弾させたい。
着弾できなければ当たると見せかけて戻ります。
(このとき囮騎兵をまた戻して当ててもOK。)
本隊の重騎兵に対馬や竜騎兵が向かえば、
とうとう大砲に隙がうまれます。ここがチャンスです。
ここで、竜騎兵をすかさず着弾させて、大砲を削り、あわよくば破壊します。
多分、マスケか槍かがすぐ戻ってくるので、それに追従する形で囮騎兵を戻し、
大砲に着弾させます。ここで破壊しきれば完璧です。
しかし、この時点で割れなければ、私なら囮騎兵は犠牲にして、
竜騎兵も使ってごり押しして破壊する場合が多いです。
あまり長い時間がかかると、大砲ダメージが蓄積してコスパがかなり悪くなります。
きっちり防衛された大砲を割ると、必ずといっていいほどコスパ負けします。
なぜか・・・。大砲は2門で資源量1000なのに対し、騎兵5騎(ウーランなら7)失えば、
すでにコスパ負けしていると言っていいでしょう。
しかし、大砲をそこまでして割る意義は、大砲を破壊することで
一気に相手の兵科バランスが崩壊してしまうことにあります。
大砲がなくても戦える編成にするとなると、大砲を守るのに非常に心許なくなります。
逆に大砲を守る編成にすると、大砲を失った途端何も出来なくなるわけです。
歩兵の損害もなく、大砲を割る。大砲をない場合はこういった戦略がとても有効です。
大砲は機動性がないから、的にしやすいというのもきっとあるでしょう。
いかがでしょうか。私もよくこの戦法を使いますが、
他にリスキーでなくて対等に大砲と戦える戦法を持っている方が
いらっしゃれば教えて頂けるとありがたいです。
・大砲破壊編(スカミの千鳥モード)
まず、千鳥モードについてみてみましょう(戦術ボタン)。
少数人数(大体20人以下)のときの千鳥モードです。

割と低密度で並んでますね。相手がファルコネット砲のときのように、
ダメージが中央から広がっていくタイプの攻撃に対して
効果を発揮する戦術なのです。が・・・
20人を越えた辺りから実はこのモードは密度が上がりだし、
大体30人を越えた辺りから通常のモードに近づき、
40人を越えるとそれを越える密度になります。

ですので、実際に千鳥モードを使うときは、数が20人以下である必要が出てきます。
さて、それでは本題です。
21人のスカミで千鳥モードを用いて大砲を破壊してみましょう。
いかがでしょうか。スカミを3部隊に分けて高密度化を防ぎ、
また最大射程で編隊が崩れないように若干近づく必要が出てきますが、
千鳥を使ったことによって大砲を割るのに5ユニット消費するだけで済みました。
スペインの即詰み戦略などでは、割と大砲がむき出し状態であることが多いので、
こういう風に割る機会も出てくるかなと思います。
Topへ
・ホットキー配置のススメ
自分が使いやすいようにオプションでホットキーの設定しましょう。
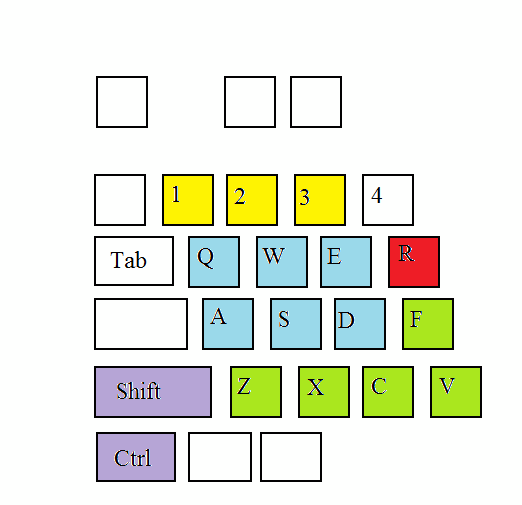
色を使って解説してみます。
まず、Z、X、C、V、Fは
キーに内政関連の操作を割り当てています。
次に、空色のキー、A、S、D、Q、W、Eは
軍関連の操作を割り当てられています。
赤色のキーであるRは、探索者の選択を割り当て、
黄色の1、2、3は育成所関連に割り当てています。
まず内政関連。
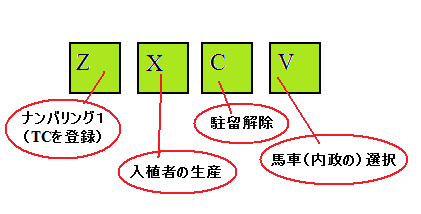
Z→Xの流れは非常にやりやすく、戦闘中でも入植者生産を継続させることができます。
Vは、工場車や前哨車がどこにいったかわからなくならないようにするために設定しています。
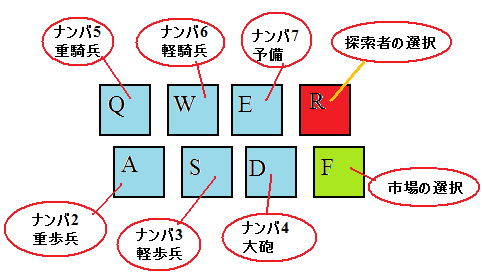
ここがホットキー配置の真髄だと思います。
shiftに近くなるように作られているため、ナンバリングの登録が楽であり、
また軍も非常に素早く操作することができます。
個人的には軍の割り当てをやりやすい形にしていますが、
この配置は人によって違ってもいいと思います。
Fは市場選択で、資源が余ったり足りなかったりしたときに
素早く資源バランスを取れるようにするためにキ-配置しました。
ちなみに予備のナンバーは、敵の入植者を狩るためのハサーや、
ハサーを2組に分けるときに使います。
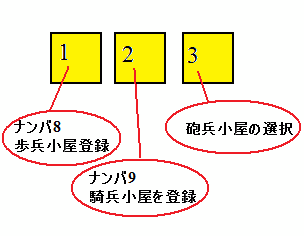
キーの3は、ナンバリングが不足したために「砲兵育成所の選択」を配置しました。
shiftキーに近いため、5体生産も楽に行うことができます。
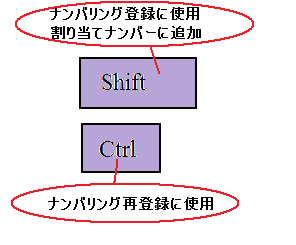
このホットキー配置の最も重要な部分ですが、
shiftを中心に作っているというのがポイントになります。
例えばshift+Aといったように、軍をすぐ登録できる、
shiftを押しながら複数生産をすることができるなどです
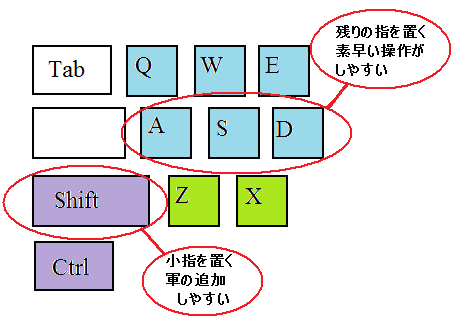
指の配置についてです。
shiftに常に小指を置いて、
小指を軸に全体を操作していくイメージになります。
人差し指、中指、薬指を各々D、S、Aにおくことで、
素早く操作することができます。
また、特殊例ですが、相手の軍を効率よく削るために、
以下に示すようなナンバリングをする場合もあります。
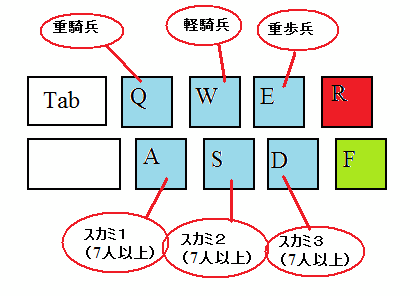
このように配置することで、相手の対ハサーを素早く削って、
対ハサーが少なくなったところで一気にハサーで畳み掛けるという戦法です。
このように、戦況に応じてナンバリングを変えることも重要です。
このように、自分のやりやすい位置にキーを持ってくると、
操作しやすさがぐっとあがるかもしれませんよ。
ちなみに、私のホットキー配置は某将官のホットキー配置を参考に、
自分の使いやすいように配置したものです。某将官様へ、感謝の意を込めて。
Topへ
・カバーモード
マスケ系を除く重歩兵はカバーモードという戦術ボタンを使うことが出来ます。
移動速度、攻撃力は実質半減しますが、遠隔系のダメージが半減します。

カバーモードにしたときの陣形がこれ。
カバーモードの利点は遠隔攻撃のダメージが半減することですが、具体的には
1. スカミや竜騎兵などの遠隔射撃を持つユニットの射撃
2. 大砲の砲撃ダメージ
3. 町の中心や前哨、トーチカなどの建物からの射撃
特に使うとするならば、町の中心やトーチカを破壊するときでしょう。
トーチカや町の中心から狙われているユニットのみカバーモードにすると
ユニットの損失を減らすことができるからです。
また、相手の重騎兵がいなくなって射撃戦になったとき
ダメージを吸収する役割も担うことができます。
Topへ
探索者で財宝を取っている時、敵の探索者に近接を取られて攻撃を受け続ける。
あるいは最悪の場合、帰還途中で倒れてしまうことがよくあります。
では、よく行われている逃走法を一度見てみましょう。
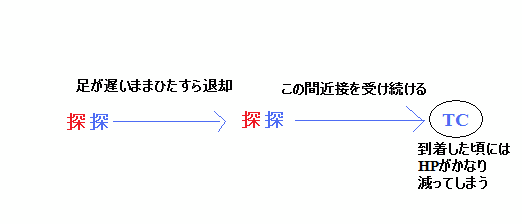
近接を受けたら、まっすぐTCに逃げる方が結構多いように思いますが、
実は結構効率が悪かったりします。
そこで、探索者逃走テクニックとして、このテクニックを提案したいと思います。
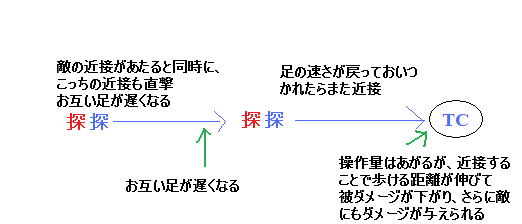
図を見てみましょう。敵の探索者が近接攻撃を行ってきました。
では、どうやって逃げるのか。それは、敵の探索者が近接攻撃をした瞬間に、
こちらの探索者も近接攻撃を行うということです。
(このとき、近接モードにしておくといい)
敵の探索者が近接攻撃を行った瞬間にこちらも近接攻撃をすることで
お互いの足が遅くなります。このとき、追いつかれることはありません。
足の速さが戻ったところで大抵追いつかれて近接攻撃を食らいますが、
また同様にして近接攻撃をすればいいわけです。
これによって、攻撃を食らう回数が減り、
さらに相手にもダメージを与えることができます。
運がよければ、近接地獄から逃れられる場合もあります。
Topへ
・肉撃ちキャンセル
入植者が動物を射撃するモーションをキャンセルすることができます。
まず、動物を射撃します。

射撃した直後、すぐ別の地点を選択、移動させます。

移動し始めた直後、肉をクリックします。

動物を撃ってから採集し始めるまで大体1秒から2秒程度かかるため、
このテクニックを使うことによって効率の上昇につながります。
特に2への進化までは操作に余裕があるので、是非使いたいテクニックです。
Topへ
・壁によるTC防御
コストが低くて済むもの。戦略的に使えるものを主に紹介。
1.敵の直進を防ぐ壁

敵の前線とTCを結ぶ直線状に、壁を張る方法です。
かかるコストが低く、意外に防衛力が高い壁ですね。
壁裏から軽歩兵で射撃を行うことが有効戦略の一つになります。
また、敵が内政地に入り込むのに時間がかかるようになり、
さらに、TCショットを長い時間与えることができるようになるので、
オススメの壁の張り方です。
2.兵で防衛しやすい壁

敵の侵略を横にそらせることによって、敵が内政地に入り込むときに
より長くTCショットを当てることができます。
さらに、軽歩兵が効率よく射撃することが出来ます。
門付近に前哨を建てると効果的です。
門がなくても十分効果が得られる壁の張り方です。
難点は、直進を防ぐ壁の2倍近くの資源が必要となることです。
3.TCに誘い込む壁

TCに誘い込むことによって、TC裏から軽歩兵の射撃が可能である張り方です。
敵が十分近づいてきたときに効果的です。
敵が後ろの軽歩兵と戦おうと思うと大きく迂回しなければならないので、
TC防衛というよりは、罠に近い壁の張り方になります。
後ろに回りこんで軽歩兵と戦おうとすると、
TCショットを長い時間受けなければならなくなるので
次第に歩兵がつらくなってくる壁の張り方です。
さらに、TC経由で入植者を前から後ろに逃がすことが可能なので、
軍を表に出さなければ、門を作る必要もなくなります。
非常に入植者にとって防衛と避難がしやすい壁の張り方です。
ただし、TC狙いの戦い方や、自分より射程の長い敵を相手にすると、
逆に不利になる場合があるので注意が必要です。
4.対騎兵用の壁

3.の誘い込む壁に加えて、更に後方に壁を伸ばした張り方です。
マップ際まで後方の壁を延ばすと非常に効果的。
あるいは、壁の長さを上げると効果があがります。
騎兵の突撃は、門をくぐることによって防ぐことが出来る仕組みになっています。
これによって、騎兵の突撃による被害を最小限にしたタートルをすることができます。
非常に防衛力の高い壁の張り方だといえるでしょう。
ただし、門を必要とするので、資源がかなり必要になります。
5.壁を使わない、建物密集防御

建物を密集させることによって、騎兵の突撃を防ぎます。
基本的に騎兵は狭いところで戦うと、あぶれ騎兵が出る上に、
上手く動けなくなって最悪何も出来なくなる場合があります。
つまり、上のような狭い地形で戦うと非常に厳しい状況なわけです。
なお、マナーハウスでない限り、基本的に家はTCより後ろに建てる事をオススメします。
というのも、家を破壊されると人口枠が確保できなくなるので
最悪の場合カード搬送や生産がとまるからです。
家は基本的に破壊されないようにしましょう。
Topへ
・カウンター法
1.搬送・進化・民兵増援カウンター
TCを狙われた、やばい!即3中に攻撃されたどうしよう!
そんな貴方にちょっとしたカウンター支援です。
ある時間を合わせれば一気にカウンターを決めるチャンスが生まれる場合があります。
それは、搬送時間、民兵生産時間、進化時間の3つ。搬送に要する時間は40秒、
民兵生産に要する時間は5秒、即3の場合3入りに要する時間は110秒なのです。
つまりこれらのタイミングを合わすことが出来れば・・・
ちなみに私もよくこのテクニックを使います。
それでは、画像で見ていきましょう。
まず、カウンターが最も効果的なのは進化中です。
特に3進化中は効果があるといえるでしょう。
しかし、慣れるまでタイミングが非常に難しいです。
そこで、画像から感覚を掴んでみてはどうでしょうか?ということなのです。
下の画像は、カード搬送が進化と同時に搬送されるようなタイミングです。

大体、左下の進化の具合が半分過ぎて、少しいったくらいからカード軍を搬送し始めます。
上のバーだと、Ⅱ:植民の時代の「時」くらいに搬送する感じでしょうか。
そうすることで、進化軍とカード軍が同時に出て、一気にカウンターすることが出来ます。
更に、民兵も追加してみます。

進化する直前5秒前に民兵を押します。
このタイミングはさほど難しくないので、大丈夫でしょう。
進化直後が下の画像です。

いかがでしょうか。一気に軍量が増えるということは、
カウンターの機会を一気に得たも同然なわけです。
2.TC前での大砲破壊法(滅多に使わない)

実は、入植者の射撃には砲兵ボーナスがついています。従って、
敵の大砲が近い場合は、TCショットで狙うよりも入植者で射撃したほうが、
有利な場合があります。また、入植者の近接は10もあるので、
大砲を囲って近接で一気に破壊することも可能です。
まぁ、滅多に使う機会はありませんがね。
Topへ
・探索法
探索というのはこのゲームにおいて非常に重要になってきます。
序盤は財宝や、未開地の踏破、自陣の資源地、敵陣の様子などを調べることができ、
2の時代以降は敵前線(FB)の発見、敵資源採集地把握、裏小屋の発見など、
探索によって得られる情報は様々です。
さて、具体的に言うと、序盤は下の図のようになると思います。
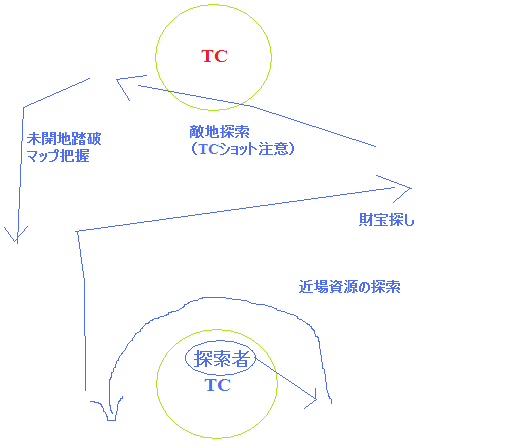
財宝探しや交易所建設で、
2の時代まで敵地探索や未開地踏破はできなくても大丈夫です。
序盤で最も重要なのは、自陣周辺の資源探索と財宝探し(羊含む)です。
ここでまずリードを分かつので、自分の探索者の動きを注視すべきでしょう。
次に、2の時代に入る直前から直後について。
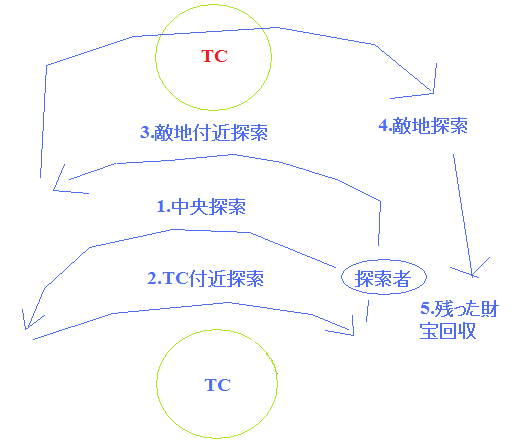
敵地探索は、意外に敵が2入りする直前あるいは直後がよい場合が多いです。
というのも、この時間帯は気付かれない場合がある上に、
気付かれたとしても、2入り直後の準備に追われるせいで、
TCショットを食らう場合が比較的少なくなるからです。
また、敵の2入り直前あるいは直後に最も行いたいことは、
敵FBの探索です。
これを怠ると、戦略の優劣で10分以内に決着がつく場合があります。
敵が何を狙っているのか、FBは建っているかということを、
2入り直前から直後にかけて(具体的には3入りまで)よく考える必要が出てきます。
あるいは、荒らすのであれば、敵TC付近を一度通ってみるといいかもしれません。
このゲームは時々刻々と状況が変わっているので、
その状況を把握するためにも、探索を怠ることはよくないですね。
特に、海があるマップの場合、港があるかどうかを調べるだけで、
対策の幅が広がるわけです。
多くの場合、敵兵に見つからなければ、常に探索をすべきでしょう。
新しい情報が一気に入っておいしい場合が多いです。
とにかく・・・
探索者は最初の10分間なるべく多く動かすようにしましょう。
Topへ
・TC周囲の荒しについて
h2hでセミFFを行うと、多くの場合重騎兵を生産して
敵地を荒らすことになるでしょう。
しかし、敵地を荒らそうと思っても荒らせない場合が結構あります。
なぜか。それは視界に入っている時間が長いからです。
私の場合、ミニマップをよく見ているので、他の色が視界に入ってくると、
意外に早く気付いて騎兵を当てられることもなく
TCに避難することができるのですが、
(資源採集もなるべく避難地に近いというのもある)
やはり視界に入っている時間が短い荒らしの対応は難しい場合があります。
また、2部隊に分けられた重騎兵の荒らしは、対応が非常に難しいことがあります。
それは、対応するのにそれだけ操作量が上がることに起因するわけですが。。
では、とりあえず図を見てみましょう。
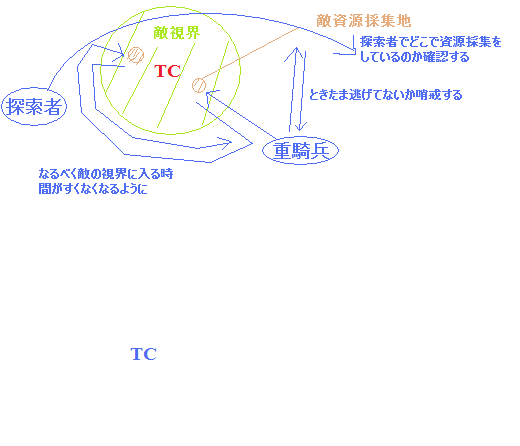
視界から敵資源採集地を見つけたら、
敵視界に入る時間が最短になるような場所から荒らします。
荒らしが失敗すればTCショットを食らわないように最短で
視界から外れます。
ここで、視界外での活動になるので、敵はどこに荒らし軍がいるか
予測はついても把握することができません。
敵の視界に入らないように、別の資源採集地を狙ってみたり、
同じ資源採集地を狙ってみたりして、敵がTCの視界から
出られないようにすると、意外に効果があるものです。
いわゆる、資源封鎖というやつですね。
また、TCに入る時間で資源採集も遅れるので、
たとえ入植者を倒せなくても意味があることをお忘れなく。
また、HPに余裕があれば、探索者もTC付近を一度歩くといいですね。
意外に木を採ってる入植者や、金を採ってる入植者を発見できる場合があります。
また、図では1部隊の重騎兵ですが、2部隊にして他の地点も同時にあらせると、
非常に効果があがることがあります。
Topへ
・操船技術
海戦での戦いは操作量を要する上に、
海支配による内政と打撃力は凄まじいものになります。
そこで、海戦における戦い方を見て、
海戦を有利に進めてみようというテクニックです。
結構他者のリプレイや動画を見て集めたテクニックもあるので、
テクニック作者に御礼を申し上げながらの紹介とさせて頂きます。
1.小型帆船2でフリゲートと戦った場合
攻撃タイミングがまちまちなので、
場合によってはダメージが全然入ってない場合がありますが、
逃げ方によってはHPがぎりぎりでも攻撃を受けずに、片方が攻撃し続けられるので、
操船方法で大分ダメージを加算することが出来ます。
とりあえず、HPギリギリ→逃走が大事です。
港で回復が出来るのをいかしましょう←ここがミソ。
Topへ
・搬送点移動先変更カウンター法・TC軍搬送点集合地点指定
即3中に攻められた、あるいはTC手前まで進軍されたとき、
搬送点を意識すると意外に返せたりするものです。
搬送指定するだけで、意外に戦況が変わります。
それでは、具体的に見ていきましょう。
まず、何も指定せずに搬送ユニットをTCから出した場合。

TC前に軍が並んで出てきます。民兵も同様です。
相手が重歩兵の場合、このままいくと近接に持ち込まれる可能性があり、
また、搬送してきたユニットの特性を活かせないまま全滅することもあり得ます。
では、実際に搬送点の移動先を指定しましょう。

右上の旗が経済活動ユニットの移動先指定です。
ほとんどの方は設定で、「経済活動ユニットの移動先のみ変更」をONにして
設定していると思いますので、
このままだと、搬送してきた軍はTC前に並ぶか、
あるいは時たま経済活動ユニット指定先に行ってしまう事もあります。
そこで、画像右下の「操作」と書いてあるところを見てください。
左から、
・経済活動ユニット移動先指定の旗アイコン
・軍ユニット移動先指定の旗アイコン
・駐留解除
・ベル
・DELETE
・回復
左から二番目のアイコンを操作することで、
軍ユニット移動先指定をすることが可能です。
移動先を指定すると、画面右下のような旗が立ちます。
次に移動先を指定してカウンターを行う場合。

左上のイェニに対して、左下方向に搬送したときの画像です。
このように、敵と距離をとる場合と、逆に距離を詰める場合の2通りが考えられます。
それでは、図解解説。
1.敵陣が南西方向にあり、敵が自陣TCに南から張り付いている場合。
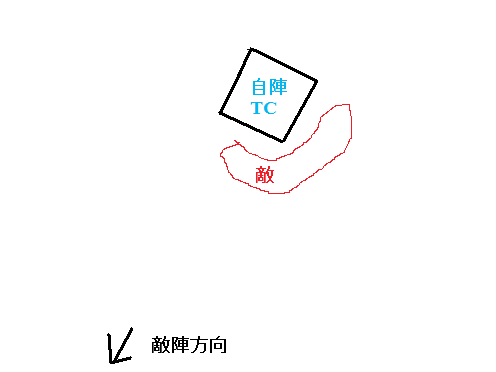
即3中などに攻められた場合はこのような状態によくなります。
それでは、搬送移動先指定をしないまま、搬送軍及び民兵を出した場合どうなるか。
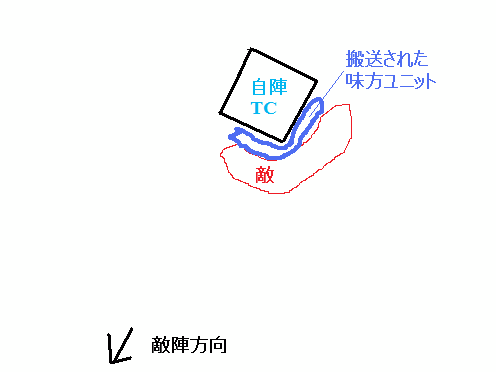
この状況が利点になり得る場合もありますが、それは後で解説します。
まず、この搬送ユニットが軽歩兵だった場合、
近接をとられて全滅をする可能性が出てきます。
また、十分に移動できずに押し込まれる場合もあるでしょう。
どちらをとっても、軽歩兵にとっては非常に厳しい状態といえるでしょう。
そこで、敵と反対になって距離が取れるように、
搬送移動先を後ろにとって見ましょう。
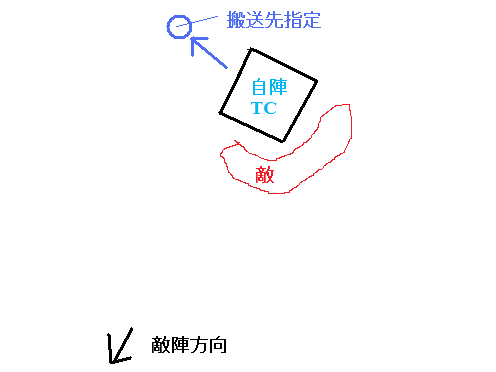
TCは大きな建物なので、搬送移動先を後ろに持っていくと、
割と距離が取れるものです。遠隔系ユニットはこのようにして距離をとるべきでしょう。
特にこれによって恩恵を受けるユニットは、
軽歩兵全般・軽騎兵全般・大砲全般・民兵・ためていた軍との合流
であるといえるでしょう。
2.敵陣が北東にある場合。
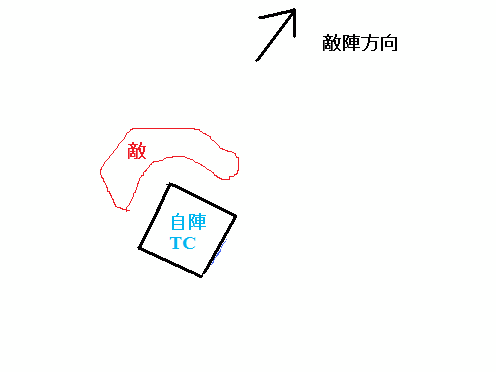
敵が北側にいる場合は、軽歩兵は南東側に出るので大丈夫なのですが、
重歩兵、あるいは重騎兵を出す場合はあまりいい状況といえません。
搬送点を変えなかった場合は以下のようになります。
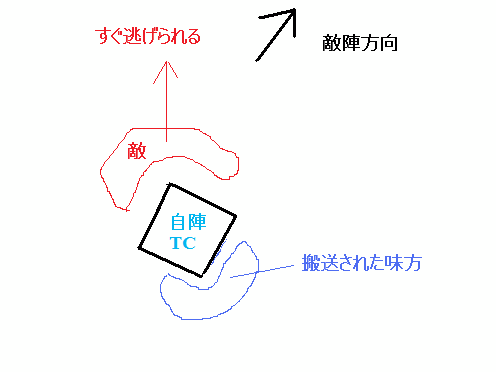
特に重歩兵を搬送した場合は、すぐに逃走されてしまい、
攻撃するどころか、退き撃ちなどを最悪食らってしまいます。
なので、重歩兵・重騎兵を搬送するときは以下のように指定します。
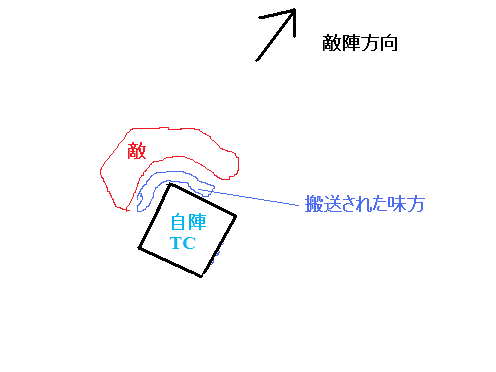
搬送移動先指定の指定先は自陣すぐ上か、遠めでも大丈夫です。
また、民兵は近接防御をもったユニットなので、
意外に一緒に出てきても効果がある場合が多いです。
また、民兵を見て退却すると言う場合も出てくるので、
なるべく敵に距離が近いほうがいい場合も出てきます。
特に、矛槍兵、ドッペル、ツクネ、浪人、スイスパイクといった、
敵に近接を食らわせればどんなユニットでも潰せるユニットを搬送する場合、
スイスパイクを除いて足が比較的遅いので、
搬送移動先を指定することで、その距離を一気に稼ぐ方がいいでしょう。
重騎兵は場合によりけりなので、じっくり考えて下さい。
特にこれによって恩恵を受けるユニットは、
矛槍兵・ドッペル・ツクネ・浪人・スイスパイク・重騎兵・民兵
と言えるでしょう。
また、搬送移動先をきっちり指定しておくと言うことは、
経済活動ユニット移動先指定でなぜか軍が移動してしまうということを
防ぐと言う目的で使うことも可能です。
これによって、自分が搬送したユニットがどこにいったか分からない、
という機会や場面が減ることでしょう。
Topへ
壁の張り方(常に最大の長さで)
普通に壁を張ると、なんだか短いところが出てきて無駄だなぁと感じているあなた。
そういうあなたにはこのテクニックを紹介したいです!
とっても簡単なテクニックです。それは壁を2枚ずつ張ることです。
そうすれば常に最大の長さで張ることができ、資源の節約をすることも可能です。
h2hでは特に使って損はないテクニックかなと考えています。
それでは、動画をご覧ください。
ずーっと伸ばしていくと、壁を2枚張れる状態に設定されます。
そのときの接合部を含めた壁の長さというのはすごく安定していて
ある程度自由に長さを変えられるということがわかっています。
これを利用して、壁をながーく張っていこうということなのです。
実は3枚ずつも張れるには張れるんですが・・・
動画後半にあるように、非常に微妙なタイミングです。
ですので、2枚ずつ張る方が、労力的にも速度的にも資源的にも、
プレイヤーにやさしいということですハイ!
Topへ
リプレイファイル(age3rec)の権利はmicrosoft社に帰属されます。
Microsoft product screen shot(s) and replay file (s) reprinted with permission from Microsoft Corporation.
 全メニュー
全メニュー
Copyright(C) suiu, All rights reserved.
 AoE紹介
AoE紹介